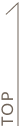1.「うちの子、前歯が噛み合っていない?」と気づいたら

開咬(オープンバイト)とはどんな状態?
「前歯が閉じない」「上下の歯が噛み合っていない」——お子さまの口元を見て、そんな違和感を覚えたことはありませんか? それは“開咬(オープンバイト)”と呼ばれる噛み合わせの異常かもしれません。開咬とは、奥歯が接触しているにもかかわらず、前歯に隙間があり、きちんと噛み合わない状態を指します。 この状態では、食べ物を前歯で噛み切ることが難しく、見た目の印象にも影響を与えるため、保護者の方が最初に気づくケースが多くあります。よくある見た目の特徴と初期サイン
開咬の子どもに多く見られる特徴のひとつが「笑ったときに前歯の隙間が目立つ」「前歯が閉じず、前に出ているように見える」といった見た目です。 また、前歯で食べ物をうまく噛み切れず、いつも奥歯だけで食べようとする様子もサインのひとつです。 そのほか、「口がポカンと開いている」「舌が前に出やすい」「滑舌が悪い」といった点も、開咬に関連している可能性があります。 これらの小さなサインを見逃さず、早期に対処することが大切です。“噛めていない”ことに子ども自身が気づきにくい理由
大人であれば「噛みにくい」「食べにくい」といった不便さに気づきやすいものですが、子どもは開咬であっても「これが普通」と思い込んでしまうことが少なくありません。 特に、幼児期や小学校低学年では、まだ噛む動作に対する意識が十分に発達しておらず、違和感や不自由さを自覚するのは難しいのが現状です。 そのため、保護者が日常の食事風景や話し方、口元の動きに注意を払い、「なんとなくおかしいかも?」と思ったら、すぐに歯科医に相談することが重要です。 開咬は、成長とともに自然に治るケースもありますが、多くの場合は癖や骨格、舌の使い方など複数の要因が関係しており、放置していても改善しないことがほとんどです。 特に、習癖(指しゃぶり、舌の突き出しなど)が原因となっている場合は、それが長期化することで歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。 開咬の治療は「できるだけ早く」が基本。骨の成長をコントロールしやすい時期に始めることで、抜歯や外科的処置を避け、自然なかたちで機能と見た目の改善が可能になります。 早期発見と適切な治療が、お子さまの将来の健康な噛み合わせと美しい笑顔につながる第一歩になるのです。2. 開咬の原因は?癖や成長の影響を知る

指しゃぶり・舌の癖・口呼吸の関係性
お子さまの開咬の背景には、日常的な「癖」が深く関係していることが少なくありません。代表的なのが、指しゃぶりや舌の癖(舌突出癖)、そして口呼吸です。 指しゃぶりは本来、乳児期には自然な行動ですが、3〜4歳を過ぎても続くと、前歯を前方に押し出す力が加わり、上下の歯が噛み合わなくなる原因となります。 また、舌を前に突き出す癖があると、常に前歯の間に舌が挟まる形となり、噛み合わせの形成に悪影響を及ぼします。 口呼吸も見逃せない要因です。鼻で呼吸せず口を開けて呼吸を続けていると、口腔内の筋肉のバランスが崩れ、舌の位置も下がりがちになり、開咬を助長することがあります。骨格のバランスと遺伝的要素も影響する
開咬の原因は、癖や習慣だけではありません。顎の骨格バランスや、遺伝的な要素も大きく関与します。 たとえば、両親のどちらかが開咬や受け口、出っ歯などの不正咬合を持っている場合、子どもにも似たような骨格的特徴が現れることがあります。 また、成長の過程で上顎の発達が遅れたり、下顎が前方に成長しすぎたりすることで、前歯が噛み合わず開咬が生じるケースも見られます。 こうした骨格性の開咬は、早期からの成長誘導によって改善が見込める一方で、適切な時期を逃すと矯正の難易度が高まるため注意が必要です。悪習癖がもたらす「機能性開咬」とは
開咬は、大きく分けて「骨格性開咬」と「機能性開咬」に分類されます。 機能性開咬とは、骨格には特に異常がないにもかかわらず、舌や唇、呼吸といった口周りの機能が正常に働いていないことに起因する開咬のことです。 たとえば、舌を突き出す癖があると、常に前歯が押されることで噛み合わせが開き、結果として開咬となります。 また、食べ方・飲み方・話し方など、口の使い方そのものに癖があると、無意識のうちに歯並びに影響を与えることもあります。 このような機能性開咬は、装置を使った矯正治療と並行して、習癖の改善や正しい機能のトレーニングを行うことで、より効果的な改善が可能になります。 つまり、開咬の原因は一つではなく、複数の要素が絡み合っていることが多いのです。 だからこそ、単に歯を動かすだけでなく、原因となっている癖や生活習慣、成長のバランスを総合的に評価し、根本から改善を目指すことが大切です。 矯正治療を検討する際は、歯だけでなく「機能」と「成長」に着目してくれる歯科医院を選ぶことが、成功の鍵を握っています。 「どうして開咬になったのか?」を知ることは、「どうすれば改善できるか?」を見極めるための第一歩です。 お子さまの健やかな成長と笑顔のために、まずは正しい知識から始めてみましょう。3. 放置するとどうなる?開咬がもたらすリスク

食べ物が噛みにくく、胃腸への負担に
開咬(オープンバイト)は、上下の前歯が噛み合わずに隙間が空いている状態を指します。この状態を放置してしまうと、日常生活の中でさまざまな問題が生じてきます。 まず第一に挙げられるのが「噛みにくさ」です。前歯でうまく食べ物を噛み切ることができないため、奥歯だけで噛む癖がつき、食べ物を十分に細かく砕くことができなくなります。 その結果、消化に負担がかかり、胃腸の不調や食べムラ、偏食といった問題が起こることも少なくありません。しっかり噛めないことは、子どもの栄養摂取や成長発達にも影響を及ぼします。発音・滑舌・表情筋の発達にも影響が
開咬を放置していると、発音や滑舌にも影響が出ることがあります。 特に「サ行」や「タ行」の音が不明瞭になったり、舌足らずな話し方になったりするケースが多く、これは前歯の隙間から空気が漏れてしまうためです。 また、上下の歯がしっかり閉じない状態が続くと、口を閉じるために必要な筋肉が発達しにくくなり、表情筋のバランスが崩れてしまうこともあります。 それによって、「口元がだらしなく見える」「笑顔がぎこちない」など、本人の表情や印象にも関わってくることがあるのです。 見た目のコンプレックスや発音への不安から、人前で話すことに自信を持てなくなるお子さまもおり、心理面での影響も無視できません。大人になってからの矯正は難易度が上がる
「乳歯だから、いずれ自然に治るのでは?」と思われる方も少なくありませんが、開咬の多くは放置しても自然に改善することはほとんどありません。 むしろ、悪い癖や噛み合わせのパターンが定着し、成長とともに骨格的なズレが顕著になる可能性があります。 こうした骨格性の開咬に進行すると、大人になってからの矯正治療では、歯だけでなく顎の骨そのものにアプローチする必要が出てくることもあります。 特に重度のケースでは、矯正治療に加えて外科手術が必要となる場合もあり、治療のハードルが一気に高くなります。 小児期の開咬は、成長を利用した矯正ができる貴重なタイミングです。 そのチャンスを逃さず、早期に適切な対応をすることで、将来の大がかりな治療を回避できる可能性が大いにあります。 噛みにくい、発音が不明瞭、口が閉じにくい——そんな些細なサインこそが、将来の健康を守るための重要な手がかりです。 「今はまだ小さいから大丈夫」と思わず、お子さまの将来のために、一歩踏み出す勇気を持っていただけたらと思います。4. 治療に“早すぎる”はありません

5〜8歳は顎の成長誘導がしやすい時期
「まだ乳歯だから様子を見よう」「永久歯が生えそろってから治療を考えよう」——そうお考えの親御さんは少なくありません。 しかし、開咬(オープンバイト)のような不正咬合は、まさに乳歯と永久歯が混ざり合う“混合歯列期(5〜8歳ごろ)”こそが、もっとも効果的な治療のタイミングとされています。 この時期は、顎の骨がまだ柔軟で成長の方向づけがしやすく、悪い癖や舌の使い方の修正もスムーズに行える時期です。 大人の骨とは異なり、成長中の子どもの顎には「誘導できる余地」があるのです。開咬の改善には“習癖のコントロール”が鍵
開咬の原因は、単に歯の並びの問題だけではありません。 指しゃぶり、舌を前に突き出す癖(舌突出癖)、口呼吸など、日常生活に潜む“悪習癖”が開咬の根本原因となっているケースが非常に多く見られます。 これらの癖は、成長とともに習慣化してしまうため、年齢が上がるほど矯正が難しくなっていきます。 一方、小児期のうちにこれらの悪習癖を見つけて適切に改善することで、将来的に大がかりな矯正を回避できる可能性が高まります。 つまり、歯を動かすだけでなく、「口まわりの筋機能」や「生活習慣の見直し」といった根本的な原因へのアプローチが、開咬改善には不可欠なのです。成長を活かしたやさしいアプローチとは
当院では、顎の成長を利用した“成長誘導”を重視しています。 たとえば、就寝時に装着する「プレオルソ」や「マイオブレース」などのマウスピース型矯正装置は、子どもの自然な発育をサポートしながら、舌の位置・呼吸・噛み合わせを正しい方向に導いてくれる優れた装置です。 痛みや違和感が少なく、取り外し可能なため、お子さまにもストレスが少ない治療法として人気があります。 さらに、悪習癖を正すためのトレーニングや、ご家庭でできる簡単な舌や口の体操を組み合わせることで、より効果的な治療が可能になります。 「早すぎるのでは?」と感じるかもしれませんが、むしろ“早期の対応”こそが、お子さまの負担を減らし、スムーズな矯正治療につながります。 放っておくことで後からより複雑で長期間に及ぶ矯正が必要になるより、今の成長のチャンスを活かすことの方が、結果的にご家族にとってもメリットが大きいのです。 「早く治療を始めること=早く終わる可能性が高まる」——そのことをぜひ知っていただきたいと思います。5. 当院が行う、子どもの開咬にやさしい治療法

プレオルソなど機能的マウスピースの特徴
開咬(オープンバイト)の治療において、当院では「機能的マウスピース」を中心とした“やさしい矯正”を提案しています。 特に使用頻度の高い「プレオルソ」は、就寝時を中心に1日1〜2時間ほど装着するだけで、顎の成長を正しく誘導し、噛み合わせや舌の位置、唇の力のバランスを整えていく装置です。 従来のワイヤー矯正とは異なり、取り外しができるため、歯みがきや食事の際にも不便がなく、お子さまの生活リズムを崩さずに治療が進められるのが大きなメリットです。 また、柔らかい素材でできているため「痛みが少ない」「見た目の違和感が少ない」といった特長もあり、矯正に対する心理的なハードルが下がります。指しゃぶりや舌癖をやめさせる工夫
開咬の原因には、指しゃぶりや舌を突き出す癖、口呼吸などの悪習癖が深く関係しています。 そこで当院では、単に装置で歯並びを整えるだけでなく、お子さまの“癖そのもの”にアプローチすることを重視しています。 たとえば、舌の正しい位置を教えるトレーニング、鼻呼吸を促す呼吸指導、生活環境の改善方法を保護者に丁寧にご案内するなど、多方面からのアプローチを行います。 また、指しゃぶりについては「叱ってやめさせる」のではなく、「やめたくなるような仕掛け」を一緒に考えるスタイルで、無理のない習慣改善をサポートします。抜歯せず、顎を育てて治す治療戦略
永久歯が生えそろってからの矯正では、歯を抜かないと並ばないケースもありますが、小児期に適切な治療を始めれば、そのリスクを大きく減らすことができます。 これは「歯を動かす」のではなく、「顎の骨の成長を誘導する」ことにより、歯が自然に並ぶスペースを確保できるからです。 こうした成長誘導型の治療を進めることで、将来的に抜歯や外科的矯正を回避できる可能性が高まり、お子さまにとって身体的・精神的な負担が少ない治療を実現できます。 当院では、矯正治療に対する不安を和らげることも大切にしています。 治療前には模型やアニメーションなどを用いてわかりやすく説明し、お子さま自身にも「なぜ治すのか」「どうして必要なのか」を納得してもらったうえでスタートします。 また、定期的な通院では「頑張ったね」としっかり褒めることで、お子さまの自信や継続意欲を育てていきます。 開咬は成長の過程で十分に改善できる症例が多く、早期に取り組めばそれだけ効果的に進めることが可能です。 お子さまの健やかな未来のために、負担が少なく、続けやすい“やさしい矯正治療”を一緒に始めてみませんか。6. こんな症状が見えたら、まず相談を

前歯が噛み合っていない・隙間が空いている
お子さまの笑顔を見ていて「なんだか前歯に隙間がある」「前歯が上下で当たっていないように見える」と感じたことはありませんか? これは、開咬(オープンバイト)の典型的なサインです。 通常、前歯は食べ物を噛み切る役割を持っていますが、開咬の場合は上下の前歯に隙間ができてしまうため、うまく噛み切れず食事にも支障が出てしまうことがあります。 一見して問題がなさそうに見えても、こうした微細なズレは将来的に歯列全体や噛み合わせ、さらには顎の成長に大きな影響を及ぼすため、早めの対処が肝心です。食べ物を前歯で噛み切れない
「お肉を前歯でかみちぎれない」「りんごを丸かじりできない」——そんな様子が見られる場合も、開咬の兆候と考えられます。 とくに幼少期は、食事の仕方に個人差があるため見落とされがちですが、明らかに前歯を使わず、奥歯ばかりで食べようとする傾向があるなら要注意です。 奥歯でばかり噛む癖がついてしまうと、前歯の発達が妨げられるだけでなく、顎全体のバランスにも悪影響を及ぼしやすくなります。 また、咀嚼が偏ることによって消化不良や顎関節への負担も大きくなるため、食べ方を観察することは重要なチェックポイントです。話しにくさや、サ行・タ行の発音の違和感
開咬の子どもに多く見られるもう一つの特徴が、「発音の不明瞭さ」です。 特に“サ行”“タ行”といった舌を使う発音で、舌足らずな話し方になったり、言葉が聞き取りにくくなったりすることがあります。 これは、舌の正しい位置が安定せず、空気が漏れたり舌が前に出たりしてしまうことが原因です。 発音の癖は、本人にとっても「うまく話せない」「伝わらない」といった不安につながり、自己肯定感の低下にもつながる可能性があります。 言葉の発達やコミュニケーション能力にも影響を及ぼすため、早い段階で専門家に相談することが大切です。 その他にも「口がぽかんと開いていることが多い」「唇を閉じにくそうにしている」といった様子も、開咬のサインかもしれません。 とくに、口呼吸が癖になっているお子さまは、舌の位置が低くなりがちで、開咬を引き起こすリスクが高くなります。 このような“何気ない癖”や“ささいな気づき”こそが、早期発見のカギとなります。 当院では、「治療が必要かどうか分からないけれど気になる」「今の状態を知っておきたい」といった段階でもお気軽にご相談いただけます。 お子さまの笑顔と健やかな成長を守るために、気になるサインがあれば早めにご相談ください。 専門医による丁寧な診断とわかりやすい説明で、ご家庭にとって最善の選択肢をご提案いたします。7. 子どもが前向きに治療できる工夫

嫌がらない矯正の始め方とは
小児矯正で最も大切なのは「お子さま本人が前向きに取り組めるかどうか」です。 どんなに効果的な治療法でも、子どもが矯正を嫌がってしまえば継続が難しくなり、治療効果も薄れてしまいます。 そのため、当院では「いきなり始める」のではなく、まずは「矯正ってどんなものか」を親子で理解していただくところからスタートします。 歯や口の模型を使って説明したり、装置に実際に触れてもらったりしながら、恐怖心や不安をやわらげる工夫をしています。親子で楽しむ通院のポイント
小さなお子さまにとって、「歯医者さん=怖いところ」というイメージを持ってしまうと、それだけで通院がストレスになります。 そこで当院では、院内の雰囲気づくりにも力を入れています。 明るい待合室、リラックスできる診療室、お子さま向けのキッズスペースなど、「また来たい」と思えるような空間づくりを心がけています。 また、通院のたびにスタンプカードやシールを用意するなど、ちょっとした“楽しみ”を取り入れることで、ポジティブな印象を与えられるようにしています。「頑張ったね」が自己肯定感につながる
治療後には必ず「よく頑張ったね」「今日はかっこよかったね」といった前向きな声かけを行います。 こうした言葉は、お子さまにとって達成感や自信につながり、次回の通院への意欲も高まります。 保護者の方にも、「できたことを褒める」「治療後にちょっとしたご褒美を用意する」といったサポートをお願いしています。 “痛い”や“怖い”という感情を“頑張った自分はえらい”という気持ちに変換できるよう、一緒に応援する姿勢がとても大切です。 また、お子さまが治療に前向きになれるためには「無理をさせない」ことも重要です。 たとえば装置の装着時間も、いきなり長時間ではなく、少しずつ慣れてもらうステップを設けています。 途中で嫌になってしまっても、「失敗ではなく、次につながる経験」として受け止め、柔軟に対応することが成功への近道です。 小児矯正は、単に歯を動かすだけの治療ではありません。 お子さまの心の成長や自己肯定感にも関わる、大切な“人生の第一歩”です。 私たちは、保護者の方と一緒に、お子さまが安心して、そして楽しみながら治療に取り組める環境を整えることを目指しています。 「矯正ってイヤじゃないかも」「やってよかった」と感じてもらえるよう、これからも心を込めてサポートしてまいります。8. 小児矯正だけで終わらないことも

永久歯が生えそろってからのⅡ期治療とは
小児矯正(Ⅰ期治療)は、主に6〜10歳頃までの乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」に行われます。 この時期は、顎の成長を促したり、悪習癖を改善したりすることで、永久歯が正しい位置に生えるための「土台づくり」を目的としています。 しかし、Ⅰ期治療だけですべての歯並びが整うとは限りません。 永久歯がすべて生えそろう12歳以降、改めて歯列全体のバランスを整える「Ⅱ期治療(本格矯正)」が必要になる場合があります。中学生以降に再調整が必要になるケース
Ⅱ期治療が必要になるケースには、以下のようなパターンがあります。- ・永久歯の生える位置や方向がずれてしまった
- ・顎の成長により噛み合わせが変化した
- ・Ⅰ期治療後の保定装置(リテーナー)の装着が不十分だった
将来を見越した段階的治療計画の重要性
Ⅰ期・Ⅱ期と段階を分けて矯正を行うことには、大きなメリットがあります。 たとえば、Ⅰ期治療で顎の大きさや位置を調整しておけば、Ⅱ期治療では抜歯を避けられる可能性が高くなります。 また、全体的な治療期間も短縮され、装置によるストレスを軽減できることもあります。 一方で、「Ⅰ期で終わると思っていたのに、また治療が必要なの?」と不安に感じる保護者の方もいらっしゃいます。 そのような誤解を防ぐためにも、最初のカウンセリング時に「段階的に治療を行う可能性があること」をしっかりとお伝えしています。 当院では、お子さま一人ひとりの成長のペースや歯の発育状況に合わせて、柔軟な治療プランをご提案しています。 将来にわたって整った歯並びと健康な噛み合わせを維持するためには、短期的な結果だけでなく、長期的な視点が欠かせません。 だからこそ、「今だけを見るのではなく、未来を見据えた矯正」を親子で一緒に考えていくことが重要です。 Ⅱ期治療が必要かどうかは、お子さまの成長や歯の生え方によって異なります。 「小児矯正で終わる場合」と「本格矯正が必要な場合」の両方を想定しながら、常に最適な道を一緒に模索していきましょう。 ご家庭と歯科医院が連携し、長いスパンで見守ることで、お子さまにとって最も負担の少ない矯正治療が実現できます。9. 開咬治療中の生活習慣と家庭でのケア

舌の正しい位置を教える方法
開咬(オープンバイト)の治療では、装置による矯正だけでなく、日常生活の中での“舌の位置”が大きな影響を与えます。 舌が常に下がった位置や前方にあると、前歯を内側から押す力がかかり、せっかく整えた歯並びが元に戻ってしまう可能性もあります。 正しい舌の位置は、上あごの「スポット」と呼ばれる場所(上の前歯の裏側、少し奥の膨らみ)に舌の先端がついている状態です。 「お口を閉じたとき、舌の先はどこにある?」とお子さまに声をかけ、日々の中で意識を高めていくことが大切です。鼻呼吸を習慣づけるための工夫
開咬の子どもに多く見られるのが「口呼吸」の習慣です。口で呼吸する癖があると、舌が常に下がったままになり、顎や歯並びの発育に悪影響を及ぼします。 口呼吸から鼻呼吸へと切り替えるには、まずお子さま自身が“鼻で呼吸することの意識”を持つ必要があります。 日中は「お口は閉じてね」とやさしく伝え、寝ている間の口の開きが気になる場合は、口テープや鼻呼吸サポートグッズを活用してみるのもひとつの方法です。 また、アレルギー性鼻炎などで鼻が詰まりやすい場合は、耳鼻科での治療と連携しながら改善を図ることも重要です。親が気をつける日常の声かけと環境づくり
矯正治療中は、お子さまのモチベーションや習慣の定着に“ご家庭でのサポート”が欠かせません。 例えば「指しゃぶりはやめようね」「お口を閉じてみよう」「舌は上に置いてごらん」といった、やさしい声かけを繰り返すことで、少しずつ意識が変わっていきます。 また、鏡を使って舌の位置を確認したり、絵本や動画で鼻呼吸の大切さを学んだりすることも効果的です。 大切なのは、“できていないことを責める”のではなく、“できたことをほめる”姿勢です。 「今日はちゃんとお口を閉じてたね」「鼻で呼吸できてたね」と、小さな成功体験を積み重ねていくことで、自然と正しい習慣が身につきます。 さらに、食事の際の姿勢や咀嚼の仕方も開咬治療に関係してきます。 背筋を伸ばして座り、よく噛んで食べることは、口周りの筋肉の発達を促し、正しい歯並びの維持につながります。 テレビを見ながらの“ながら食べ”を避け、家族で食卓を囲む時間を大切にすることも、健やかな口腔育成の一助となるでしょう。 矯正治療は装置だけで完結するものではありません。 毎日の生活の中での積み重ねが、最終的な成果に大きく影響します。 「家庭でできることなんてあるのかな」と不安に思う保護者の方もいらっしゃいますが、実はお子さまの“習慣づくり”こそが、治療を成功に導くカギとなるのです。 当院では、治療の進行に合わせてご家庭でできるケア方法や声かけのアドバイスも行っています。 お子さまの笑顔と健康な口元のために、一緒に取り組んでいきましょう。10.「いつ相談すればいい?」と思った今がチャンス

初診相談でわかることとは?
「うちの子の歯並び、もしかして開咬かも?」 そう気づいたときが、まさに相談のベストタイミングです。 初診相談では、歯の状態を確認するだけでなく、お子さまの顎の成長の度合いや、癖による影響、生活習慣なども詳しくヒアリングします。 その上で、現時点で治療が必要かどうか、今は経過観察でよいのか、それとも日常的なケアや習慣の見直しが有効なのかなどを総合的に判断いたします。 まだ歯並びが整っていなくても、早い段階で情報を得ておくことが、のちの選択肢を広げることにつながります。治療が必要かどうかの見極めができる
実は、「すぐに治療が必要」と判断されるケースばかりではありません。 開咬は、習癖や呼吸方法の改善だけで済む軽度な場合から、装置を使った矯正が必要な骨格性のケースまで、原因と程度に応じてさまざまです。 ご相談いただいた際には、お子さまの年齢・成長段階・歯の生え変わりのタイミングを踏まえたうえで、「今すぐできること」「今だからこそできること」「将来のために備えるべきこと」について、丁寧にご案内いたします。 また、矯正の必要がないと判断された場合も、数ヶ月〜半年ごとの経過観察を通じて、お口の状態を継続的に見守ることができます。成長に合った最適なタイミングを逃さないために
開咬治療の多くは、「顎の成長を利用して整える」ことが鍵になります。 特に5〜8歳頃の混合歯列期は、顎の骨が柔軟でコントロールしやすいため、この時期を逃さないことがとても重要です。 とはいえ、保護者の方が「今がその時期かどうか」を見極めるのは簡単ではありません。 だからこそ、まずは歯科医院に相談していただくことで、将来の治療計画を明確にし、安心感を得ることができるのです。 当院では、初診相談やカウンセリングを通じて、保護者の方が感じている不安や疑問にしっかりと寄り添い、無理な治療の提案は一切行いません。 「このまま様子を見ていいのか」「将来、矯正が必要になるのか」「今やっておくべきことはあるのか」——そうした思いを、ぜひ率直にお聞かせください。 開咬は、放置すれば成長とともに悪化することもありますが、早期にアプローチすれば自然に整いやすいケースも多くあります。 「様子を見ていたら、いつの間にか時期を逃してしまった」 そんな後悔をしないためにも、「少しでも気になったとき」がベストな相談タイミングです。 未来のために、お子さまの笑顔と健康を守る第一歩を、今ここから一緒に踏み出していきましょう。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより