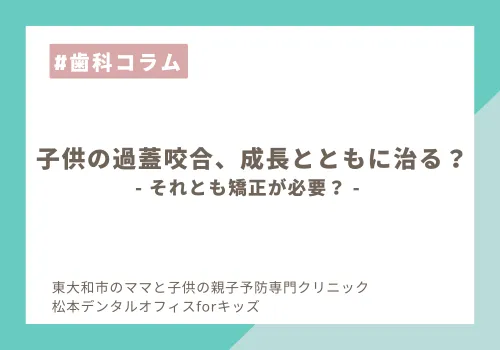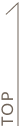こんにちは。松本デンタルオフィスforキッズです。
お子さんの噛み合わせについて気になったことはありませんか?過蓋咬合(かがいこうごう)は 上の前歯が下の前歯を覆いすぎてしまう 噛み合わせの異常で、見た目だけでなく 顎の成長や発音、歯の健康にも影響を及ぼす ことがあります。
特に子供のうちは、成長とともに自然に改善するケースもありますが、そのままにしておくと 顎関節症のリスク や 歯や歯ぐきへの負担 が増えることも。 「いつ治療を始めるべき?」 「家庭でできる予防法はある?」 といった疑問を持つ親御さんも多いはずです。
今回は、 子供の過蓋咬合の原因・治療法・家庭でできる対策 について解説していきます。お子さんの将来の健康な歯並びのために、今できることから始めましょう!
1.こんなお悩みありませんか?

✅ 子供の噛み合わせが深すぎる気がする
✅ 下の前歯がほとんど見えず、話しにくそうにしている
✅ 将来的に歯並びや顔の成長に影響が出ないか心配
お子様の歯並びを見て、「上の前歯が下の前歯を覆い隠している気がする…」「食べるときに噛みにくそう…」と感じたことはありませんか? 「過蓋咬合(かがいこうごう)」 という噛み合わせの状態かもしれません。
過蓋咬合は、見た目だけでなく、食事や発音、顎の成長にも影響を与えることがあります。子供の噛み合わせは、成長とともに変化していきますが、早めに適切なケアをすることで、将来的なリスクを減らすことができます。
2.過蓋咬合とは? その定義と特徴

過蓋咬合とは、噛んだときに上の前歯が下の前歯を大きく覆い隠してしまう噛み合わせ のことをいいます。
過蓋咬合の特徴
✅ 噛んだときに下の前歯がほとんど見えない
✅ 上の前歯が下の前歯や歯茎に強く当たることがある
✅ 前歯で噛む力が強くなり、歯がすり減りやすい
✅ 歯茎が下がりやすくなる
✅ 顎に負担がかかり、顎関節症のリスクがある
軽度の場合は大きな問題がないこともありますが、重度の過蓋咬合になると、歯や顎への負担が大きくなり、治療が必要になることがあります。
他の不正咬合との違い
不正咬合(ふせいこうごう)にはさまざまな種類があります。過蓋咬合と他の不正咬合との違いを比較してみましょう。
| 不正咬合の種類 | 特徴 | 影響 |
| 過蓋咬合(かがいこうごう) | 上の前歯が下の前歯を大きく覆い隠す | 前歯や歯茎への負担が大きい、顎関節症のリスク |
| 上顎前突(出っ歯) | 上の前歯が前に突き出している | 口が閉じにくい、前歯が折れやすい |
| 下顎前突(受け口) | 下の前歯が上の前歯より前に出る | 噛みにくい、発音が悪くなりやすい |
| 開咬(かいこう) | 前歯が噛み合わず、すき間ができる | うまく食べ物を噛めない、発音がしにくい |
| 交叉咬合(こうさこうごう) | 上下の歯が横にずれて噛み合っている | 顎が歪みやすい、顔の非対称が進むことがある |
過蓋咬合の特徴は、噛み合わせの深さに問題があること です。他の不正咬合と違い、歯だけでなく 顎や歯茎にも負担がかかりやすい という点がポイントです。
子供の成長と噛み合わせの関係
お子様の噛み合わせは、成長とともに変化します。特に 乳歯から永久歯に生え変わる時期(6〜12歳頃) は、噛み合わせが大きく変わるタイミングです。
過蓋咬合になりやすい原因
✅ 遺伝的な影響
→ 親御様のどちらかが過蓋咬合の場合、お子様もなりやすい
✅ 舌の癖や口の動き
→ 唇を噛む癖や、舌を前に押し出すクセがあると、噛み合わせに影響を与えることがあります
✅ 口呼吸の習慣
→ 口で呼吸することが多いと、顎の成長バランスが崩れることがある
✅ 柔らかい食べ物ばかり食べている
→ 硬い食べ物を噛む機会が少ないと、顎の成長が不十分になり、噛み合わせが深くなることがある
お子様の歯並びは、将来のお口の健康に大きく影響します。「もしかして過蓋咬合かも?」と気になったら、お気軽にご相談くださいね!
3.過蓋咬合の原因とは?

過蓋咬合とは、上の前歯が下の前歯を大きく覆い隠してしまう噛み合わせ のことです。
過蓋咬合になってしまう原因には、主に次の3つがあります。
遺伝的な要因と家族の歯並びの影響
お子様の歯並びや噛み合わせは、遺伝による影響を大きく受けます。
✅ 遺伝が関係するポイント
- 顎の形や大きさ → 親御様が小さい顎を持っていると、お子様も同じように小さい顎になることが多い
- 歯のサイズや生え方 → 歯のサイズが大きいと、噛み合わせが深くなりやすい
- 噛み合わせのクセ → 噛み癖や顎の動きのパターンも遺伝の影響を受けやすい
✅ 家族に過蓋咬合の人がいる場合は要チェック!
「私も小さい頃から噛み合わせが深かった」「親も歯並びが似ている」 という場合、お子様も過蓋咬合になりやすい可能性があります。
ただし、遺伝だからといって 必ず過蓋咬合になるわけではありません!
生活習慣や早めの対策で、噛み合わせを改善できることもあります。
指しゃぶり・頬杖・口呼吸などの生活習慣の影響
お子様の噛み合わせは 普段の生活習慣 によっても大きく影響を受けます。
✅ 指しゃぶり
- 3歳くらいまでの指しゃぶりは自然な行動ですが、5歳を過ぎても続くと歯並びに影響 することがあります。
- 上の前歯が前に押し出され、過蓋咬合を悪化させる原因になることも。
✅ 頬杖(ほおづえ)
- 片側だけに負担をかけると 顎の成長がアンバランスになり、噛み合わせがずれる ことがあります。
- 特に 長時間の頬杖 は要注意!
✅ 口呼吸(くちこきゅう)
- 口をポカンと開けている習慣があると、舌の位置が下がってしまい、正しい顎の発達が妨げられる ことがあります。
- 口呼吸が続くと 歯並びや噛み合わせだけでなく、風邪をひきやすくなる ことも。
✅ 舌の癖(くせ)
- 舌で前歯を押すクセがあると、歯が前に押し出されて過蓋咬合の原因になる ことがあります。
- 正しい舌の位置は「上あごに軽くついている状態」です。
【お子様のチェックポイント!】
☑ 指しゃぶりのクセが残っている
☑ 長時間の頬杖をすることが多い
☑ 口をポカンと開けることが多い
☑ 舌を前に出すクセがある
これらのクセに気づいたら、少しずつ改善していくことが大切です!
乳歯の早期喪失や奥歯の成長不足
乳歯が早く抜けたり、奥歯の成長が十分でないと、噛み合わせに影響を与えることがあります。
✅ 乳歯の早期喪失(早く抜けること)
- 虫歯やケガ で乳歯が早く抜けると、隣の歯がずれてしまい、噛み合わせが深くなってしまうことがある
- 乳歯は自然に抜けるタイミングがあるので、むやみに抜かないことが大切
✅ 奥歯の成長不足
- 奥歯がしっかり成長しないと、前歯の噛み合わせが深くなりやすい
- 硬いものを噛む習慣 をつけることが大切(噛みごたえのある食事が効果的!)
【お子様のチェックポイント!】
☑ 乳歯が早く抜けたことがある
☑ やわらかい食べ物ばかり食べている
☑ 食事中によく噛まないで飲み込む
お口の成長には「よく噛む」ことがとても重要!
お子様の噛み合わせを守るために、しっかり噛んで食べる習慣をつけること を意識しましょう。
お子様の過蓋咬合は 「遺伝」と「生活習慣」 の両方が関係していることがわかっています。親御様やご家族に過蓋咬合の方がいる場合、お子様も同じような噛み合わせになる可能性があります。しかし、日常のちょっとした習慣にも気をつけることで、噛み合わせの悪化を防いだり、改善につなげたりすることができます。
4.過蓋咬合が引き起こす問題とは?

過蓋咬合は 見た目の問題だけでなく、歯や顎、全身の健康にも影響を及ぼすことがある噛み合わせ です。
歯や歯ぐきへの負担と炎症のリスク
過蓋咬合の一番の問題は、歯や歯ぐきにかかる負担が大きくなること です。
✅ 強すぎる噛む力が歯にダメージを与える
過蓋咬合では、前歯にかかる力が通常よりも強くなりがちです。そのため、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 前歯のすり減りが早くなる → かみ合わせが深いほど、前歯が削れて短くなりやすい
- 歯が欠けたり、ひびが入ることがある → 特に硬いものを噛んだときに負担がかかりやすい
- 奥歯にも負担がかかる → 前歯のバランスが悪いため、奥歯に余計な力がかかることがある
✅ 歯ぐきへの負担が炎症を引き起こす
過蓋咬合の程度が強いと、下の前歯が上の歯ぐきに当たってしまう ことがあります。これが原因で、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 歯ぐきが傷つき、腫れたり出血しやすくなる
- 歯ぐきが下がり、歯の根が露出しやすくなる
- 歯周病になりやすくなる(特に大人になってからのリスクが高まる)
過蓋咬合は見た目の問題だけではなく、歯や歯ぐきの健康にも大きく影響する ことを覚えておきましょう。
顎関節症や頭痛・肩こりとの関係
過蓋咬合は、歯だけでなく 顎(あご)や全身のバランス にも影響を及ぼします。
✅ 顎関節症(がくかんせつしょう)のリスク
- 噛み合わせが深いと、顎の動きが制限される ことがあります。
- その結果、顎関節に負担がかかり、痛みや違和感が出る ことがあります。
👀 顎関節症のサインは?
☑ 口を開けると「カクッ」と音がする
☑ 顎の周りが痛むことがある
☑ 口を大きく開けにくい
このような症状がある場合は、噛み合わせが関係している可能性があります。
✅ 頭痛や肩こりが起こることも
噛み合わせが悪いと、噛む筋肉に余計な負担がかかる ため、首や肩の筋肉まで緊張しやすくなります。その結果、次のような症状につながることがあります。
- 頭痛が起こりやすくなる(こめかみのあたりがズキズキすることが多い)
- 肩こりや首こりが続く(特に長時間の勉強やスマホ使用で悪化しやすい)
一見、噛み合わせとは関係なさそうな症状ですが、実は過蓋咬合が原因になっていることも多い のです。
見た目や発音への影響
過蓋咬合は、お口の機能や見た目 にも影響を与えます。
✅ 口元の印象が変わる
- 噛み合わせが深いため、口を閉じたときに下あごが小さく見える ことがあります。
- また、笑ったときに歯ぐきが目立ちやすく(ガミースマイルになりやすい) なることもあります。
見た目が気になることで、自信を持って笑えなくなったり、コンプレックスを感じるお子様もいらっしゃいます。
✅ 発音に影響が出ることも
過蓋咬合があると、舌の動きが制限されるため、発音に影響を与えることがあります。 特に、次のような音が発音しにくくなることがあります。
- 「さ行」→ 例:「さかな」「しんぶん」
- 「た行」→ 例:「たまご」「ちず」
お子様が話すときに 発音が不明瞭だったり、聞き取りにくい場合は、噛み合わせが関係している可能性も あります。
過蓋咬合は、見た目の問題だけではなく 歯や顎、全身の健康に影響を及ぼす可能性がある ことがわかっています。
5.何歳から治療を始めるべき?

過蓋咬合の治療を始める適切なタイミングは お子様の成長段階によって異なります。それぞれの年齢でできることを知って、お子様にとってベストなタイミングを見極めましょう。
過蓋咬合の治療に適した年齢
過蓋咬合の治療を始めるのに適した時期は 6歳〜12歳ごろの学童期 です。この時期は 顎の成長が活発で、永久歯への生え変わりが進むタイミング なので、治療による効果が得やすいからです。
しかし、お子様によって成長のスピードは異なるため、 「何歳になったら必ず治療を始める」という決まりはありません。
重要なのは、
✅ お子様の噛み合わせの状態
✅ 成長のスピード
✅ 過蓋咬合の程度(軽度〜重度)
を総合的に判断しながら、最適なタイミングを見極めることです。
では、幼児期・学童期・思春期のそれぞれの時期にできることを詳しく見ていきましょう。
幼児期・学童期・思春期でできること
お子様の成長に合わせて、過蓋咬合の対応方法は異なります。
① 幼児期(3〜6歳)
この時期は まだ乳歯が生えそろっている段階 なので、基本的には経過観察をしながら生活習慣の改善を意識していきます。
🔹 この時期にできること
- 指しゃぶりや舌で歯を押すクセをやめる
- 口をポカンと開けないよう、鼻呼吸を意識する
- 頬杖や歯ぎしりのクセをチェックする
- 硬いものを噛む習慣をつける
🔹 歯科医院でのチェックポイント
- 顎の成長に問題がないか
- 歯並びに異常がないか
- 生活習慣の指導が必要かどうか
この時期は 「治療」よりも「予防」 を意識しながら、成長を見守ることが大切です。
② 学童期(6〜12歳)
この時期が 過蓋咬合の治療に最も適したタイミング です。
🔹 この時期にできること
- 顎の成長をコントロールするための矯正治療(プレートやマウスピース)
- 歯並びを整えるためのブラケット矯正(ワイヤー矯正)
🔹 治療の目的
- 上下の噛み合わせを適切に調整する
- 顎の成長をコントロールし、過蓋咬合の悪化を防ぐ
- 歯や顎にかかる負担を軽減する
過蓋咬合は成長期に治療を始めると、治療効果が得られやすい ため、できるだけこの時期にチェックを受けておくことをおすすめします。
③ 思春期(12〜18歳)
この時期は 永久歯が生えそろい、顎の成長もほぼ完了する時期 です。
🔹 この時期にできること
- 矯正治療(ワイヤー矯正・マウスピース矯正)
- 必要に応じて歯を削る処置やかぶせ物による治療
思春期は 成長期ほど顎の成長を利用した治療ができない ため、できるだけ学童期に治療を始めるのが理想です。しかし、この時期からでも 適切な矯正治療で改善することは可能 なので、気になる場合は歯科医院に相談してみましょう。
早期治療のメリットと放置するリスク
過蓋咬合は 放置すると噛み合わせがさらに深くなり、さまざまなトラブルにつながる可能性があります。
✅ 早期治療のメリット
・顎の成長を利用して、自然に噛み合わせを改善できる
・歯や顎への負担を軽減できる(すり減り・顎関節症のリスクを下げる)
・矯正治療の負担を減らし、短期間で治療できる可能性が高い
・発音や食事の問題を早めに改善できる
早めに治療を始めることで、負担が少なく、効率よく治療を進めることができます。
✅ 放置するリスク
・噛み合わせがどんどん深くなり、治療が難しくなる
・歯がすり減ったり、欠けたりしやすくなる
・顎関節症のリスクが高まる
・発音や食事に影響が出ることがある
過蓋咬合は 軽度のうちに治療するのがベスト ですが、すでに症状が進行している場合でも 適切な治療を行えば改善できます。
お子様の過蓋咬合は、 6〜12歳ごろの学童期が治療のベストタイミング です。早期治療を行うことで 顎の成長をコントロールしながら、負担を少なく過蓋咬合を改善できる 可能性があります。一方で、放置すると 治療が難しくなり、将来的なリスクが増える ことも。
6.子供の過蓋咬合の治療法とは?

過蓋咬合の治療は お子様の成長段階や歯並びの状態に合わせて 選択されます。ここでは、主な治療法として 「取り外し可能なマウスピース矯正」、「拡大床(あごを広げる装置)」、「ワイヤー矯正」 の3つを詳しくご紹介します。
取り外し可能なマウスピース矯正
まず、過蓋咬合の治療に取り外し可能なマウスピース矯正を使う方法 があります。
✅ マウスピース矯正とは?
透明なマウスピース型の装置を装着し、歯を少しずつ動かして噛み合わせを改善する矯正方法 です。お子様が 食事や歯みがきの際に取り外しができる のが特徴です。
✅ マウスピース矯正が向いているケース
✔ 軽度〜中等度の過蓋咬合
✔ お子様が装置をしっかり装着できる場合
✔ ワイヤー矯正に抵抗がある場合
✅ マウスピース矯正のメリット
・透明で目立ちにくい → 見た目が気にならない
・取り外し可能 → 食事や歯みがきがしやすい
・違和感が少ない → ワイヤー矯正より痛みが少ないことが多い
✅ マウスピース矯正のデメリット
・1日20時間以上の装着が必要 → 装着時間を守らないと効果が出にくい
・重度の過蓋咬合には不向き → ワイヤー矯正が必要になることも
マウスピース矯正は 適応できる範囲が限られる ため、まずは歯科医院でしっかり診断を受けることが大切です。
拡大床(あごを広げる装置)の活用
お子様の成長期(6歳〜12歳ごろ)で、顎の発育がまだ進行中の段階 では、「拡大床(かくだいしょう)」 という装置を使って、顎の幅を広げる方法があります。
✅ 拡大床とは?
拡大床は、ネジで少しずつ顎の骨を広げながら、歯がきれいに並ぶスペースを作る装置 です。
✅ 拡大床が向いているケース
✔ 顎の成長がまだ終わっていないお子様(6〜12歳)
✔ 歯が並ぶスペースが不足している場合
✔ 軽度〜中等度の過蓋咬合の場合
✅ 拡大床のメリット
・顎の成長を利用できる → 自然な形で噛み合わせを改善しやすい
・永久歯の抜歯を避けられる → スペースを作ることで歯並びが整いやすい
・取り外し可能 → 食事や歯みがきのときに外せる
✅ 拡大床のデメリット
・毎日装着する必要がある → 装着時間を守らないと効果が出にくい
・成長期を過ぎると効果が出にくい → 12歳以降はワイヤー矯正が必要になることが多い
拡大床は 顎の成長を利用できる学童期に最も効果的 です。「うちの子、顎が小さいかも?」と思ったら、早めにご相談ください。
ワイヤー矯正が必要になるケース
過蓋咬合の程度が強い場合や、マウスピース矯正・拡大床では改善が難しい場合には、ワイヤー矯正(ブラケット矯正) を行うことになります。
✅ ワイヤー矯正とは?
歯にブラケット(小さな金属や透明の装置)をつけ、ワイヤーを通して歯を動かす矯正方法です。
✅ ワイヤー矯正が必要なケース
✔ 重度の過蓋咬合(噛み合わせが深すぎる)
✔ 顎の成長がほぼ完了している思春期以降(12歳〜)
✔ 他の矯正方法では十分な改善が見込めない場合
✅ ワイヤー矯正のメリット
・あらゆる症例に対応できる → 軽度〜重度の過蓋咬合にも対応可能
・確実に歯を動かせる → 治療の自由度が高い
✅ ワイヤー矯正のデメリット
・取り外しができない → 食事や歯みがきのときに注意が必要
・違和感や痛みを感じることがある → 装置が口の中に当たることがある
ワイヤー矯正は 治療の自由度が高い反面、お子様の負担も大きくなりやすい ため、しっかりとサポートしながら進めていくことが大切です。
お子様の過蓋咬合の治療方法には、成長段階や症状の程度によっていくつかの選択肢があります。過蓋咬合は 早めに治療を始めることで、より負担の少ない方法で改善できる ことが多いです。
7.家庭でできる過蓋咬合の予防法

過蓋咬合は 生活習慣によって予防できる部分もある ため、日常のちょっとした工夫がとても大切です。
今回は、家庭でできる 「正しい姿勢と食事の仕方」「噛む力を鍛えるトレーニング」「口周りの筋肉を強化する習慣づくり」 について、すぐに実践できる方法を紹介します。
正しい姿勢と食事の仕方
お子様の姿勢や食事の仕方が、実は噛み合わせの成長に大きく影響します。
✅ 正しい姿勢を意識する
- 背筋を伸ばし、足をしっかり床につけて座る(足がつかない場合は、足台を活用)
- 食事中にテレビやスマホを見ながら食べない(姿勢が崩れる原因に)
- 片側だけで噛まないように、両方の奥歯でしっかり噛む
姿勢が悪いと、顎の発育がバランスを崩し、過蓋咬合を悪化させることがあります。お子様の食事中の姿勢を意識するだけでも、噛み合わせの発達をサポートできます。
✅ よく噛んで食べることが大切
噛む回数が少ないと、顎の成長が十分に進まず、過蓋咬合になりやすくなります。
🔹 こんな食べ方になっていませんか?
☑ 柔らかいものばかり食べる
☑ 口に入れてすぐ飲み込む
☑ 片側だけで噛むクセがある
噛む回数を増やし、しっかりと顎を使うことで、噛み合わせのバランスを整えることができます。
✅ 噛む力を育てるおすすめの食材
硬すぎるものは歯を傷めることもあるので、適度な噛みごたえのある食材 を選びましょう。
✔ 根菜類(にんじん、大根、ごぼうなど) → 歯ごたえがあり、自然と噛む回数が増える
✔ するめ・昆布 → よく噛まないと食べられないので、噛む力を鍛えるのに最適
✔ 玄米や雑穀米 → 白米よりも噛む回数が増える
✔ ナッツ類(アレルギーがない場合) → 小さく砕いたものを食べると噛むトレーニングに
「よく噛んで食べる」ことが、歯並びの健康を守る第一歩です!
噛む力を鍛えるトレーニング方法
噛む力が弱いと、顎の発達が不十分になり、過蓋咬合の原因になることがあります。家庭で簡単にできる 噛む力を鍛えるトレーニング をご紹介します!
✅ 風船ガムトレーニング
- ガムを20〜30回以上噛んでから 飲み込まずに捨てる
- できれば片側だけでなく、左右均等に噛む
- 大きな風船を作ると、口周りの筋肉が鍛えられる
🎈 ガムを噛むメリット 🎈
✅ 噛む回数が自然と増える
✅ 口周りの筋肉が鍛えられる
✅ 顎の発達をサポートする
※キシリトール入りのシュガーレスガムを選ぶと、虫歯予防にもなります。
✅ タオルを使った噛むトレーニング
- 清潔なタオルを用意する
- タオルを奥歯で軽く噛む
- ゆっくり噛みしめて、力を入れて5秒キープ
- これを1日5回程度 繰り返す
このトレーニングをすると、顎の筋肉が鍛えられ、しっかりと噛めるようになります。
口周りの筋肉を強化する習慣づくり
口周りの筋肉が弱いと、過蓋咬合だけでなく 口呼吸のクセがついたり、歯並びが乱れやすくなる ことがあります。
✅ 口をしっかり閉じる習慣をつける
口をポカンと開けるクセがあると、舌の位置が下がり、正しい噛み合わせを妨げることがあります。
👄 口を閉じるトレーニング方法 👄
- お口ポカン防止シールを貼る(寝ている間に口が開くのを防ぐ)
- 唇を閉じたまま、鼻呼吸を意識する
- 鏡の前で「いー」と口を横に伸ばす練習をする
これを毎日少しずつ続けると、自然と口を閉じる習慣がつきます。
✅ あいうべ体操で口周りの筋肉を鍛える
「あいうべ体操」は、口周りの筋肉をしっかり鍛え、正しい噛み合わせを促すトレーニングです。
やり方
- 「あー」口を大きく開く
- 「いー」口を横に大きく広げる
- 「うー」唇を前に突き出す
- 「べー」舌を思い切り前に出す
✨ 1日30回程度行うと、口周りの筋肉が鍛えられます!
過蓋咬合の予防には、普段の食事や生活習慣がとても大切 です。「過蓋咬合が心配だけど、まだ小さいから様子を見ている」という親御様も多いと思いますが、早めに生活習慣を見直すことで、噛み合わせの発育をサポートできます!
8.矯正治療は痛い?費用は?

矯正治療には 痛みやコスト、治療期間 など、気になるポイントがいくつかあります。そこで、矯正治療の痛みの対処法、治療期間の目安、費用の相場と保険適用について解説していきます!
子供の矯正治療に伴う痛みとその対処法
✅ 矯正治療の痛みはどんな感じ?
子供の矯正治療では、装置をつけることによって 歯や顎に力がかかるため、一時的に痛みを感じることがあります。
🔹 痛みを感じやすいタイミング
- 装置をつけた直後(初日〜3日目)
- ワイヤーやマウスピースを交換した直後
矯正中の痛みの感じ方には個人差がありますが、「歯が浮いたような違和感」や「押されるような軽い痛み」 を感じるお子様が多いです。
✅ 痛みの対処法
「痛みが心配…」という親御様へ。痛みを和らげる方法もあるので、ご安心ください!
🟢 痛みを和らげる方法
- 柔らかい食べ物を食べる(お粥、スープ、ヨーグルトなど)
- 痛みが強いときは冷やす(頬の外側を冷たいタオルで軽く冷やす)
- 市販の鎮痛剤を使用する(どうしても痛みが強い場合は、医師に相談の上で痛み止めを使用)
- しばらくすると慣れることを伝える(「2〜3日で落ち着くよ」と声をかけるだけでも安心感に)
矯正治療の痛みは 一時的なもの です。数日経てば慣れて、普段通りの生活ができるようになります!
治療期間の目安とスケジュール
「矯正治療はどれくらいの期間かかるの?」という質問もよくいただきます。
過蓋咬合の治療期間は 年齢や症状の程度、使用する装置によって異なります が、目安としては 1年半〜3年程度 です。
✅ 矯正治療の流れと期間の目安
| 治療ステップ | 期間 | 内容 |
| ① 初診・相談 | 1日 | 口腔内検査・レントゲン撮影・相談 |
| ② 精密検査・診断 | 1〜2週間 | CT・歯型採取・治療計画の説明 |
| ③ 治療開始(装置装着) | 1回 | 矯正装置を装着 |
| ④ 定期調整(1ヶ月に1回) | 1年半〜3年 | 歯を少しずつ動かす |
| ⑤ 保定期間 | 1〜2年 | リテーナー(後戻り防止装置)を使用 |
治療が完了した後も、後戻りを防ぐためにリテーナー(保定装置)を使う期間が必要 になります。
特に 顎の成長が終わるまでは、歯が動きやすい ため、しっかりと管理していくことが大切です!
費用の相場と保険適用について
「矯正治療は高額」とよく言われますが、具体的にどのくらいの費用がかかるのか、詳しく解説します。
✅ 矯正治療の費用相場
過蓋咬合の矯正費用は、使用する装置によって異なります。
| 矯正方法 | 費用の目安 | 特徴 |
| 拡大床(顎を広げる装置) | 10万〜30万円 | 取り外し可能、成長期の子供向け |
| マウスピース矯正 | 50万〜100万円 | 目立たない、取り外し可能 |
| ワイヤー矯正 | 60万〜120万円 | 効果が高いが固定式 |
| 部分矯正(前歯のみ) | 20万〜40万円 | 軽度のケース向け |
矯正治療は 基本的に自由診療(保険適用外) になるため、費用が高額になりやすいです。
✅ 矯正治療に保険は使える?
通常、子供の矯正治療は 「審美目的」とみなされるため保険適用外 です。
しかし、次のようなケースでは 保険適用になることもあります。
🟢 保険適用になるケース
- 顎の成長異常(骨格性の過蓋咬合) → 外科手術を伴う矯正が必要な場合
- 厚生労働省指定の「先天性疾患」がある場合(唇顎口蓋裂など)
保険適用になるかどうかは、歯科医院での診断が必要 ですので、気になる場合はご相談ください。
矯正治療は 長い時間をかけて歯並びを改善していく治療 ですが、その分 お子様の将来の歯の健康や噛み合わせの安定 に大きく貢献します。
9.子供の矯正治療を成功させるためのポイント

矯正治療は 数年単位の長い治療 になります。そのため、途中でモチベーションが下がってしまうお子様も少なくありません。でも、親御様のサポート次第で、スムーズに治療を続けられることもあります。
矯正治療中のモチベーション維持の方法
矯正治療は 長期間かかるため、お子様のモチベーションを維持することが大切 です。途中で「もうやめたい…」と言われてしまうこともありますよね。
そこで、子供が前向きに矯正治療を続けられるコツ をご紹介します!
✅ 成功イメージを持たせる
「矯正が終わったら、どんなキレイな歯並びになるか」を 具体的に伝えることが大切 です。
🟢 やる気を引き出す声かけ
- 「今がんばると、将来キレイな歯並びになるよ!」
- 「矯正が終わったら、自信を持って笑えるよ!」
- 「もうちょっと頑張れば、もっと食べやすくなるよ!」
治療前の写真と途中経過の写真を比べて見せるのも、モチベーションアップにつながります。
✅ ご褒美を取り入れる
「痛みがあっても頑張った」「きちんと装置をつけていた」など、小さな努力をほめてあげる ことが大切です。
🎁 おすすめのご褒美例
✔ 「装置を毎日きちんとつけたら、好きなシールを1枚プレゼント!」
✔ 「1ヶ月しっかり矯正を頑張ったら、好きな本やおもちゃを買おう!」
ただし、甘いお菓子のご褒美は 虫歯のリスクがあるため控えめに!
✅ 矯正の痛みや違和感を軽減する
矯正装置による痛みや違和感が原因で、お子様が治療を嫌がることもあります。
🟢 痛みを和らげるコツ
- 矯正装置を調整した日には 柔らかい食べ物(おかゆ、スープ、ヨーグルトなど) を準備する
- 痛みが強い場合は、頬を冷やす・鎮痛剤を使う(医師に相談)
お子様が「ちょっと痛いけど頑張れそう!」と思える環境を作ることが大切です。
親御様のサポートが重要な理由
矯正治療は お子様ひとりで頑張るものではありません! 親御様の協力が成功のカギを握っています。
✅ 矯正装置の管理をサポート
特に マウスピース矯正や拡大床(取り外しできる装置) を使っている場合、お子様がきちんと装置を装着しているか 親御様が確認してあげることが大切 です。
🟢 親御様のチェックポイント
☑ 矯正装置をしっかり装着しているか?
☑ 1日20時間以上つけているか?
☑ きちんとお手入れできているか?
特に小学生の間は 「つけ忘れ」「適当に管理してしまう」 ことがあるので、優しくサポートしてあげましょう!
✅ 食事の工夫でサポート
矯正中は 硬いものや装置に引っかかる食べ物を避ける 必要があります。
🍽 おすすめの食事メニュー
✔ 柔らかめの煮物やスープ
✔ おかゆや雑炊
✔ ヨーグルトやプリン
逆に、硬い食べ物(せんべい・ナッツ類・ガム)は 装置が壊れる原因 になるため、注意しましょう!
✅ 矯正治療を前向きにサポート
お子様が「矯正いやだな…」と思うこともあるかもしれません。そんなときは、励ましの言葉がとても大切 です。小さな変化を一緒に喜びながら、ポジティブな気持ちで矯正治療を進めていきましょう!
歯科医と定期的に相談しながら進める
矯正治療は 定期的な調整が必要な治療 です。
✅ 定期検診の大切さ
矯正治療中は 1ヶ月〜2ヶ月に1回のペースで通院 します。
🟢 定期検診で行うこと
✔ 矯正装置の調整
✔ 歯並びの変化の確認
✔ 磨き残しや虫歯チェック
定期的に歯科医と相談しながら治療を進めることで、治療がスムーズに進み、トラブルを防ぐことができます!
矯正治療は お子様ひとりで頑張るものではなく、親御様や歯科医と一緒に取り組むもの です。
10.よくある質問
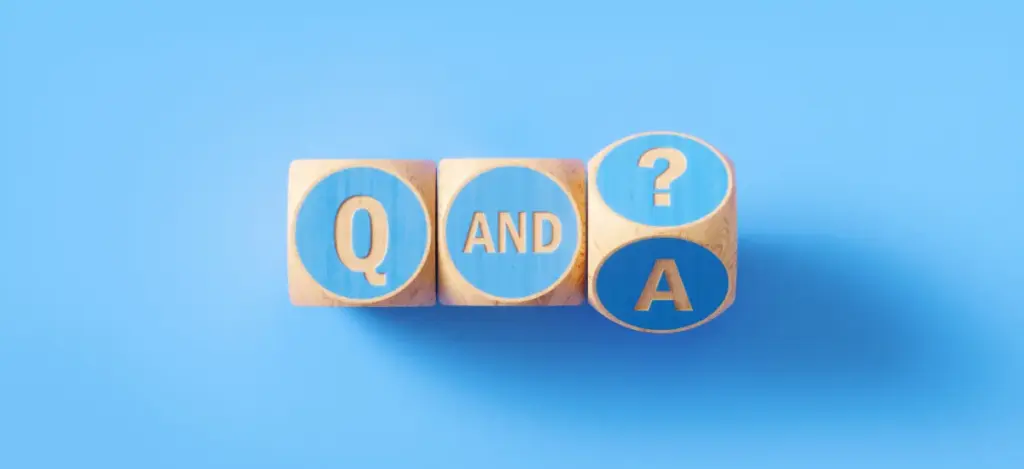
「子供の過蓋咬合に関するよくある質問」について、親御様から特に多くいただく3つの疑問にお答えします。
Q1.過蓋咬合は自然に治ることがある?
A1.軽度の過蓋咬合なら自然に改善することも
子供の過蓋咬合は、成長とともに改善する場合もあります。特に 乳歯から永久歯に生え変わるタイミング(6〜12歳頃) では、噛み合わせが変わることが多いため、軽度の過蓋咬合であれば自然に良くなる可能性もあります。
✅ ただし、改善しないケースも多い
一方で、顎の成長バランスが悪い場合や、噛み合わせの深さが強い場合は自然に治らないことがほとんど です。
🟢 自然に治る可能性があるケース
✔ 軽度の過蓋咬合(前歯が少し重なっている程度)
✔ 乳歯の時期で、永久歯への生え変わりが順調な場合
✔ 舌の癖や口呼吸などの影響がなく、自然な顎の成長が期待できる場合
🔴 自然に治りにくいケース
❌ 上の歯が大きく下の歯を覆い隠している
❌ 顎の骨格的な問題(下顎が小さいなど)がある
❌ 指しゃぶりや口呼吸、頬杖などの生活習慣の影響がある
過蓋咬合が気になる場合は 「様子を見るべきか、治療を始めるべきか」 を判断するために、一度歯科医院でチェックすることをおすすめします!
Q2.乳歯のうちは様子を見ても大丈夫?
A2.乳歯の時期は経過観察が基本
3〜6歳くらいの乳歯の時期は、まだ顎の成長も途中段階です。この時期に 少し過蓋咬合がある場合は、すぐに矯正を始める必要がないこともあります。
そのため、乳歯の時期は 基本的に経過観察しながら、成長を見守るのが一般的 です。
✅ ただし、気をつけるべきポイントも
乳歯の時期でも、以下のような症状がある場合は早めに相談したほうがよいでしょう。
🔴 乳歯の時期でも注意が必要なケース
❌ 下の前歯がほとんど見えないほど噛み合わせが深い
❌ 下の前歯が上の歯ぐきに当たって傷ついている
❌ 食べにくそうにしている(しっかり噛めない)
❌ 発音に影響が出ている(さ行・た行の発音が不明瞭)
✅ 乳歯の時期にできること
乳歯の時期でも、以下のようなことを意識するだけで、過蓋咬合の悪化を防ぐことができます。
🟢 姿勢を正す(猫背や頬杖を避ける)
🟢 よく噛んで食べる習慣をつける
🟢 口呼吸をやめて鼻呼吸を意識する
乳歯のうちは すぐに治療を始めるケースは少ないですが、正しい生活習慣を身につけることが大切 です!
Q3.治療しないと大人になってどうなる?
A3.「子供のうちは特に困っていないし、このまま放っておいても大丈夫?」と悩まれる親御様もいらっしゃいます。
しかし、過蓋咬合を放置すると、大人になってからさまざまなトラブルが起こる可能性がある ため、注意が必要です。
✅ 放置すると起こる可能性のある問題
❌ ① 歯や歯ぐきへのダメージ
過蓋咬合が強いと、下の前歯が上の歯ぐきに当たり続ける ことがあります。その結果、歯ぐきが傷ついたり、歯がすり減ってしまう こともあります。
❌ ② 顎関節症(あごの痛み)につながることも
噛み合わせが深すぎると、顎の関節に負担がかかり、顎関節症(がくかんせつしょう) の原因になることがあります。
「口を開けるとカクッと音がする」「顎が痛い」などの症状が出ることも。
❌ ③ 発音や噛む機能に影響が出る
過蓋咬合が強いと、舌の動きが制限されるため、「さ行」「た行」の発音がしづらくなる ことがあります。また、しっかり噛めないことで消化に負担がかかる ことも。
❌ ④ 矯正治療が大人になってから難しくなる
子供の頃に治療をしておけば、顎の成長を利用できるため、比較的スムーズに治療できる ことが多いです。しかし、大人になってからだと 外科手術が必要になるケースもある ため、早めの治療が理想的です。
過蓋咬合は 見た目の問題だけでなく、歯や顎への負担、発音や食事のしづらさなど、将来的に大きな影響を及ぼす可能性があります。早めに気づいて適切な対策をとることで、よりスムーズに改善できる可能性が高くなります。
「うちの子の噛み合わせ、大丈夫かな?」と少しでも気になったら、まずは 専門の歯科医に相談することが大切 です。お子様の成長段階に合わせた治療法や予防策を考え、一緒にサポートしていきましょう!
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより