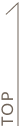1.「うちの子、矯正が必要かも?」と気づいたら

まず知っておきたい「矯正が必要なサイン」
お子さまの歯並びや噛み合わせを見て、「なんとなく歯並びがガタガタしている気がする」「前歯が出ているように見える」と感じたことはありませんか?
実はこうした“直感的な違和感”こそが、矯正治療が必要かもしれないサインです。
具体的には、次のような症状がある場合、早めのチェックが推奨されます。
- ・上下の前歯が噛み合わない
- ・前歯が極端に出ている(出っ歯)または内側に倒れている(受け口)
- ・永久歯の生え方にズレや重なりがある
- ・歯の隙間が広い、またはギュウギュウに並んでいる
これらの特徴は、将来的なかみ合わせのトラブルや口腔機能の低下につながる恐れがあります。
また、見た目の問題だけでなく、「しっかり噛めない」「発音がしにくい」といった機能的な問題も出てくるため、単なる“見た目の問題”と侮らず、気づいたときに一度専門医に相談することが大切です。
放置せず、早めの相談がなぜ大切なのか
「子どもの矯正って、永久歯が生えそろってからでいいのでは?」とお考えの方も多いかもしれません。
確かに、大人の矯正はすべて永久歯で行うため、そのようなイメージを持たれがちです。
しかし、子どもの場合は“成長”という大きな武器があります。この時期にしかできない骨格や顎の誘導が可能になるのです。
特に5歳~10歳頃の「混合歯列期」(乳歯と永久歯が混ざっている時期)は、矯正治療の第一ステップであるⅠ期治療を始める絶好のタイミング。
この段階で不正咬合の芽を摘んでおけば、将来の本格矯正(Ⅱ期治療)が必要なくなる、あるいは期間を短縮できる可能性もあります。
一方、放置してしまうと骨格の歪みが固定されてしまい、後々外科的な介入が必要になるケースも少なくありません。
「何か気になる」「自分では判断がつかない」という段階でも、専門の矯正歯科に相談することで安心材料を得られるはずです。
“矯正期間”はいつからスタートするの?
矯正治療のスタート時期は、お子さまの口腔状態や成長のタイミングによって異なります。
例えば、受け口(反対咬合)のような骨格的な問題がある場合は、早ければ4~5歳から治療が始まることも。
逆に、軽度の歯列不正であれば、様子を見てから対応することもあります。
ただし、「いつから始めるのが正解か?」という問いに明確な答えはありません。
重要なのは、医師の診断のもと「成長をどう活かすか」「どの装置が合っているか」「お子さま本人の準備ができているか」を見極めたうえで、治療を始めることです。
なお、一般的には矯正相談→診査→治療計画立案→治療スタートという流れを踏み、早くても初診から装置装着までに1〜2ヶ月かかることもあります。
そのため、「気になったらすぐ相談」が、結果として治療の質を高め、負担を軽減することにもつながります。
お子さまの健やかな成長と美しい歯並びを守るためには、親御さんの“気づき”が最初の鍵となります。
「もしかして矯正が必要かも?」——その気持ちをきっかけに、ぜひ一度専門医にご相談ください。
2. 矯正治療の全体像と期間の考え方

Ⅰ期治療とⅡ期治療、それぞれの役割
子どもの矯正治療は、大きく分けて「Ⅰ期治療」と「Ⅱ期治療」の2段階に分けて考えられます。
Ⅰ期治療とは、主に5〜10歳頃の混合歯列期に行うもので、顎の骨の成長を正しく導くことを目的としています。この時期に顎のバランスを整えておくことで、永久歯が自然にきれいに並ぶスペースを確保できる可能性があり、結果的にⅡ期治療が不要になったり、軽度で済んだりすることもあります。
一方、Ⅱ期治療は12歳以降、永久歯がほぼ生えそろってから行う本格的な歯列矯正です。ブラケットやマウスピースを使って、歯そのものの位置を整える治療が中心になります。
Ⅰ期治療は「予防的」「成長を活かす」アプローチ、Ⅱ期治療は「仕上げ」「見た目や機能の完成」の段階という位置づけです。どちらか一方のみで済むお子さまもいれば、両方を段階的に行うケースもあります。
“成長”という時間を味方にする戦略
子どもの矯正における最大のアドバンテージは、「成長発育を利用できること」です。
特にⅠ期治療では、骨格の形成途中にある顎の成長を適切に誘導できるため、歯を抜かずに整える可能性を広げることができます。これは大人の矯正にはない、大きなメリットです。
例えば、受け口や出っ歯といった骨格性の不正咬合は、骨が固まってからの矯正では難易度が高くなりがちです。しかし、成長段階で適切な装置を用いることで、顎の前後バランスを整えやすくなります。
また、子どもにとって矯正治療が「生活の一部」として自然に馴染む点も、治療の継続性や成功率において重要な要素です。成長期を味方にした矯正は、身体への負担を抑えながら効果的に進めることができる、まさに“今しかできないアプローチ”といえるでしょう。
平均的な治療期間はどれくらい?
気になる治療期間ですが、Ⅰ期・Ⅱ期を合わせた全体の目安としては、平均3〜5年ほどとされています。
Ⅰ期治療は比較的短く、1年〜1年半程度で終了するケースが多く見られます。一方、Ⅱ期治療に入ると、歯の移動速度や装置の種類にもよりますが、2〜3年程度の通院が必要になる場合があります。
ただし、これはあくまで「一般的な平均」であり、治療期間には個人差が大きく出る点も理解しておくことが重要です。
たとえば、顎の成長がスムーズで装置の装着状況も良好なお子さまの場合、予定より早く治療が完了することもあります。逆に、悪習癖の改善に時間がかかったり、途中で治療を中断したりすると、計画より長引いてしまうケースもあります。
したがって、最初の相談時点で「治療の見通しをしっかり立ててもらうこと」が非常に大切です。
矯正専門の歯科医であれば、お子さまの顎の成長スピードや歯列の状態を丁寧に確認したうえで、個別に合った治療計画を提案してくれるはずです。
また、治療期間中は3〜6週間に一度程度の通院が必要となりますが、その間に状態の変化や本人の生活状況に応じた微調整を行うことで、よりスムーズな進行が可能になります。
子どもの矯正治療は、単に「歯を動かす」だけではなく、成長とともに「未来をデザインする」医療とも言えるでしょう。だからこそ、治療期間は「長い・短い」だけで判断するのではなく、「どう過ごすか」「どんな成果を得るか」を見据えて考えることが大切です。
3. Ⅰ期治療:5〜10歳頃に始める“成長誘導”

歯列や顎のバランスを整える時期
Ⅰ期治療とは、永久歯が生えそろう前の「混合歯列期(5〜10歳頃)」に行われる小児矯正のことを指します。この時期の最大の特徴は、顎の骨がまだ柔らかく、成長が続いているという点です。
そのため、成長のタイミングを活かして顎のバランスを整えたり、歯が正しく生えるためのスペースを作ったりすることが可能になります。
単に歯を動かすのではなく、「正しい方向に成長を導く」ことがⅠ期治療の目的です。
たとえば、上顎が狭いお子さまには、拡大床やプレオルソといった装置を使って上顎の幅を広げることで、将来の歯並びや噛み合わせの改善が期待できます。また、受け口傾向のあるお子さまには、下顎の前方成長を抑制し、上顎の成長を促す装置を使用することがあります。
このように、Ⅰ期治療は「将来の本格矯正を軽減する」ことを目的とした“準備の矯正”でありながら、実際には多くのケースで大きな成果を上げています。
使用する装置と通院頻度の目安
Ⅰ期治療では、お子さまの状態に応じてさまざまな装置が用いられます。たとえば、以下のような装置が代表的です。
- ・プレオルソ(マウスピース型矯正装置)
- ・ムーシールド(受け口用機能的装置)
- ・拡大床(顎の幅を広げる装置)
- ・上顎前方牽引装置(上顎の成長を促す)
多くの装置は取り外しが可能で、就寝時や自宅での時間を中心に装着します。お子さまに過度な負担をかけず、学校生活や遊びの時間を妨げない設計となっているため、安心して取り組むことができます。
また、定期的な通院は4〜6週間に一度程度が一般的です。装置の調整やお口の中の変化を確認しながら、段階的に治療を進めていきます。
治療の途中で癖(指しゃぶり・舌突出癖・口呼吸)などが見つかった場合には、それらを改善するトレーニングを併用することもあります。機能的な側面からもアプローチすることで、より根本的な矯正効果が期待できます。
平均1〜2年、様子を見ながらのステップ
Ⅰ期治療の期間は、お子さまの成長や歯列の状態によって異なりますが、一般的には1〜2年ほどが目安です。
ただし、成長スピードには個人差があり、途中で経過観察を挟みながら段階的に治療を進めることもあります。
たとえば、1年間で一定の成果が出た場合、その後は永久歯の萌出を待つ「休止期間」に入り、再評価のうえでⅡ期治療の必要性を判断するという流れになります。
Ⅰ期治療だけで十分に整った歯並びを得られるお子さまもいれば、Ⅱ期治療が必要になるケースもありますが、いずれの場合も「成長を利用している」ことが共通の大きなメリットです。
とくに将来的に抜歯をせずに済む可能性が高まる点は、保護者にとっても大きな安心材料となります。
また、Ⅰ期治療を経験することで、お子さまが「歯を大切にする気持ち」を持ちやすくなるという心理的効果も期待できます。矯正装置の使い方や通院の習慣が自然と身につき、Ⅱ期治療に移行した際にもスムーズに治療を続けられるという利点があります。
このように、Ⅰ期治療はただ歯を整えるだけでなく、子どもの成長と将来の健康を見据えた“未来の投資”とも言える大切なステップです。お子さまの歯並びに不安を感じたら、まずは矯正専門の歯科医院でご相談されることをおすすめします。
4. Ⅱ期治療:永久歯がそろったあとに行う本格矯正

中学生以降が対象、歯並びと噛み合わせを整える最終ステージ
お子さまの歯の矯正治療は、永久歯がすべて生えそろった後に行う「Ⅱ期治療」が、本格的な仕上げのステージとなります。
Ⅰ期治療では顎の成長をコントロールしながら土台を整えることが目的でしたが、Ⅱ期治療では歯列そのものをきれいに整え、理想的な噛み合わせへ導くことが主な目的となります。
対象となるのは、だいたい12歳前後〜中学生以降が目安です。全ての永久歯が生えそろってからが治療の開始タイミングとなるため、時期には個人差がありますが、本人の成長の様子や顎の状態、Ⅰ期治療の有無によっても判断されます。
ブラケット矯正・マウスピース矯正、それぞれの特徴と治療期間
Ⅱ期治療では、一般的に「ワイヤー(ブラケット)矯正」または「マウスピース矯正」が用いられます。
ブラケット矯正は、歯の表面にブラケットを接着し、ワイヤーで徐々に歯を動かしていく伝統的な方法です。細かいコントロールに優れており、幅広い症例に対応できます。治療期間の目安は、平均で2〜3年ほどですが、歯の動きや本人の協力度によって前後します。
一方、透明で目立ちにくいマウスピース矯正は、見た目を気にする年頃のお子さまにも人気です。1日に20時間以上の装着が必要で、自己管理がしっかりできる年齢になってからが適しています。
症状の重さや骨格の状態によってはマウスピース単独では難しいケースもあり、その場合は併用治療やワイヤー矯正が選択されることもあります。
大人と同じ内容の矯正だからこそ、今始めるメリットがある
Ⅱ期治療は、基本的に大人の矯正と同じ内容になります。つまり、今後大人になってから治療を始めるのと同じ工程・装置が必要になりますが、今この時期に始めることで、以下のようなメリットがあります。
- ・骨の成長がまだ完全には止まっていないため、歯の移動がスムーズ
- ・早期にコンプレックスを解消でき、自信を持った学校生活を送れる
- ・将来的な虫歯や歯周病のリスク軽減につながる
また、すでにⅠ期治療を受けているお子さまの場合、顎のバランスが整っているため、Ⅱ期治療の負担が軽減されるケースもあります。
逆に、Ⅰ期治療を行っていない方でも、Ⅱ期からの矯正でしっかりと噛み合わせを整えることは可能です。歯並びや噛み合わせを放置すると、大人になってから頭痛や顎関節症の原因になることもあるため、この時期にしっかり整えておくことはとても重要です。
矯正治療は、単に見た目を整えるだけでなく、心身の健康や生活の質を向上させるものでもあります。Ⅱ期治療はその仕上げ段階であり、ゴールに向かって確実に進んでいくための大切なプロセスです。
「もうすぐ永久歯がそろいそう」「Ⅰ期は終わったけれど今後どうする?」といったタイミングでは、ぜひ一度、矯正歯科の専門医にご相談ください。お子さま一人ひとりに最適な治療計画をご提案いたします。
5. 期間が長引く?短くなる?要因を知ることがカギ

治療期間が変わる3つの要因とは?
お子さまの矯正治療を検討する際、多くの保護者の方が気にされるのが「治療はどれくらいの期間かかるのか」という点です。
「周りの子は1年で終わったのに、うちはまだ続いている」「予定より長引いている気がする」――そんな声も少なくありません。しかし、矯正治療は一人ひとりの状態に応じて設計されるもので、期間にも大きな個人差があります。
治療期間に影響を与える主な要因としては、以下の3点が挙げられます。
- ・歯や顎の状態(歯並びの複雑さや骨格の問題)
- ・使用する装置の種類と適切な装着状況
- ・本人と保護者の治療への協力度合い
この3つのバランスが整うことで、治療はよりスムーズに進み、結果的に短期間での完了につながることもあります。逆に、どれか一つでも難がある場合は、治療が長引く要因となることがあります。
“装着時間”と“生活習慣”が与える決定的な影響
特に重要なのが、「装置の装着時間」と「生活習慣」の2点です。
取り外し式のマウスピース矯正装置(プレオルソやインビザラインなど)は、決められた時間(一般的に1日20時間以上)の装着が治療効果に直結します。装着時間が足りないと、歯の移動が計画通りに進まず、治療が長引く原因に。
また、指しゃぶりや舌の癖、頬杖、口呼吸といった「悪習癖」が残っていると、せっかく動かした歯が元の位置に戻ろうとする力が働き、矯正効果が打ち消されるリスクもあるのです。
こうした生活習慣の改善には、ご家族のサポートが不可欠です。矯正医からの指導だけでなく、日常の中での声かけや見守りがとても大切になります。装置の装着状況を一緒に確認したり、悪習癖が見られたときに優しく注意したりするだけでも、治療の進行スピードに大きく影響します。
「本人のやる気」がカギを握る!協力体制の大切さ
矯正治療が順調に進むかどうかは、お子さま本人の“やる気”や“モチベーション”にかかっている部分も大きいのです。
特に小学生〜中学生の時期は、治療に対して不安や面倒くささを感じることも多く、「今日はつけなかった」「外している時間が長かった」ということが繰り返されると、治療計画がずれてしまいます。
そのため、治療期間を短く、効果的に進めるためには、以下のようなポイントが重要になります。
- ・治療の「目的」をお子さまと共有する(きれいな歯並び、将来の健康)
- ・痛みや違和感をすぐに相談できる環境をつくる
- ・頑張ったことを褒めてあげる習慣を持つ
また、通院先の歯科医院が「治療を押し付けない」「子どもが安心して通える雰囲気」であることも大切です。当院では、歯科医師・歯科衛生士・スタッフが一丸となって、お子さまとご家族をサポートする体制を整えています。
「どれくらいで終わりますか?」という質問に、明確な答えを出すことは難しいかもしれませんが、お子さまにとって最適なスピードで、できるだけスムーズに、そして前向きに治療が進められるよう、環境を整えていくことがなによりの近道です。
治療の期間を“ただの時間”ではなく、“未来への投資”ととらえて、一緒に向き合っていきましょう。
6. 装置によって異なる治療スピード

取り外し式と固定式、それぞれの特徴と違い
矯正治療の期間に大きく影響する要素のひとつが、「どの装置を使うか」です。
矯正装置には大きく分けて「取り外し式」と「固定式」があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、治療スピードや負担の大きさも異なります。
取り外し式の代表格は、マウスピース型矯正装置(インビザライン、プレオルソなど)です。透明で目立ちにくく、取り外して食事や歯みがきができるため、日常生活に支障が少ないのが特徴です。
ただし、1日20時間以上の装着が前提となるため、本人の協力度合いが治療結果に直結します。装着時間が足りないと治療が長引くことがある点に注意が必要です。
一方、固定式装置(いわゆるワイヤーブラケット矯正)は、歯に直接装置を装着し、24時間力をかけ続けるため、計画どおりに歯が動きやすく、確実性の高い治療が可能です。
ただし、見た目が気になりやすく、歯みがきがしづらくなることから虫歯リスクが高まるなど、生活上の負担も伴います。
マウスピース矯正は短期間で終わるのか?
「マウスピース矯正=早く終わる」という印象を持たれることもありますが、実際にはケースバイケースです。
軽度の歯列不正(例えば前歯が少し重なっているだけ、など)の場合は、短期間での改善が期待できることがあります。しかし、顎の骨格から整える必要がある中度〜重度の症例では、取り外し式だけでは十分なコントロールが難しいケースもあります。
また、お子さまの場合、装着時間の管理が難しくなることも少なくありません。保護者の協力や日々の声かけが欠かせない治療スタイルとなるため、「つけたり外したり」が多いお子さまには、固定式の方が向いていることもあります。
マウスピース矯正のメリットは、何よりも「生活に合わせやすい」こと。習い事や学校行事とのバランスを取りながら治療が進められる点は、保護者からも好評です。
装置選びが治療期間とストレスに与える影響
装置の種類によって、治療のスピードだけでなく、本人やご家族が感じる「ストレス」の程度も変わってきます。
たとえば、見た目を気にして矯正に抵抗感があるお子さまには、目立ちにくいマウスピース装置が有効です。一方で、確実な動きを求めるなら固定式が選ばれることが多くなります。
装置による違いは、次のような点に現れます。
- ・装着時間の自己管理ができるかどうか
- ・見た目や違和感へのストレス
- ・通院回数やチェックの頻度
- ・装置の破損リスクや交換頻度
当院では、お子さまの性格や生活スタイル、ご家族のサポート体制などを総合的に判断し、最適な装置をご提案しています。
治療期間は装置選びによって数か月〜年単位で変わることもあるため、「早く終わるためにどれを選ぶか」ではなく、「続けやすく効果が出やすい装置はどれか」という視点で考えることが大切です。
どの装置にも一長一短があります。大切なのは、お子さまが無理なく治療を続けられ、最終的に満足のいく結果が得られること。
装置の選択は、医師との相談を通じて、納得のいく形で進めていきましょう。
7. 矯正治療中に“やるべきこと・気をつけること”

毎日の歯みがきと食生活の見直しが基本
矯正治療中は、装置があることで歯に汚れがたまりやすくなります。ブラケットやワイヤー、マウスピースの周囲には食べかすが残りやすく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
そのため、治療中は今まで以上に「歯みがき」が重要となります。特に固定式の装置を使用している場合、歯ブラシだけでなく、タフトブラシや歯間ブラシなどを使った補助的なケアが必要です。
また、食生活の見直しも治療の成功に直結します。硬いものや粘着性の強い食べ物(キャラメルやガムなど)は、装置を壊す原因になるため注意が必要です。
装置の破損は治療期間の延長にもつながるため、避けたほうが安心です。食後の口ゆすぎや、水分補給も忘れずに行いましょう。
さらに、おやつの時間を決める、食後すぐに歯を磨くなど、習慣そのものを整えることが、虫歯予防にもつながります。お子さま一人では難しいことも多いため、保護者の方の声かけやサポートが不可欠です。
定期通院の大切さとその間隔
矯正治療中は、1〜2か月に一度の通院が基本です。通院の目的は、装置の調整だけでなく、歯の動きや噛み合わせの確認、虫歯のチェック、清掃状態の確認など多岐にわたります。
この「定期チェック」を怠ってしまうと、予定していた歯の動きが得られなかったり、装置に不具合が起きたまま時間が過ぎてしまったりと、治療の進行に大きな影響が出てしまいます。
特に成長期の子どもは、あごの大きさや歯の生え方がどんどん変化するため、その変化に応じた治療の調整が重要です。
もし装置が取れてしまった、装着に違和感がある、歯ぐきに痛みが出たといったトラブルがあれば、定期通院を待たず、早めに連絡するようにしましょう。
当院では、毎回の診察で「今の状態」と「次の目標」をわかりやすく伝えるよう心がけています。お子さま本人にも内容を理解してもらい、治療へのモチベーションを保つ工夫を大切にしています。
生活の中で続けるための工夫とサポート
矯正治療は、数か月から数年に及ぶ“長期戦”です。続けるためには、「無理のない習慣」と「治療に前向きになれる環境づくり」が欠かせません。
お子さまが装置の装着を忘れてしまったり、痛みで嫌がってしまったりといった場面も、決して珍しくありません。
そうしたときに、保護者の方が「がんばってるね」「もう少しで調整だよ」と励ましてあげることが、お子さまの気持ちを支える大きな力になります。
また、治療の進捗が見えるように、カレンダーや表に装着時間や通院日を記録する方法もおすすめです。視覚的に「頑張っていること」が実感できると、モチベーションにもつながります。
歯科医院側でも、治療を「つらいもの」「面倒なこと」にしない工夫が重要です。痛みに配慮した診療、優しい声かけ、子どもが安心できる雰囲気づくりなど、心理的なハードルを下げる配慮を行っています。
矯正治療は、歯だけでなく「家族全体で取り組むもの」です。お子さまの成長に寄り添いながら、一歩ずつ進めていくことで、治療の成功と明るい未来がつながっていきます。
今しかできないことを大切に、矯正の時間を“前向きな体験”として積み重ねていきましょう。
8. 治療終了=ゴールではない?保定期間の存在

矯正後の歯並びは“動きやすい”状態にある
矯正治療が終わり、装置が外れた瞬間は、患者さまにとって大きな達成感と安心感があります。しかし、実はこのタイミングこそ注意が必要です。
歯は「動かされた直後」が最も不安定で、元の位置に戻ろうとする“後戻り”が起こりやすい時期です。これを防ぐために重要なのが「保定(ほてい)期間」です。
保定期間とは、矯正治療後に歯が新しい位置に安定するまでの期間を指し、この間、専用の「保定装置(リテーナー)」を使用して歯列を固定します。
せっかく整えた歯並びも、保定装置を怠ってしまうと数か月でズレが生じるケースがあり、再治療が必要になることもあるため、このステップは決して軽視できません。
お子さまの場合、成長によって顎や顔貌が変化するため、保定期間中も歯科医による定期チェックが推奨されます。
見た目が整っているからといって、保定を自己判断でやめてしまうのは非常にリスクが高い行為です。
保定装置の種類と使い方、注意点とは
保定装置にはいくつか種類がありますが、主に「取り外し式のプレート型」と「歯の裏側に固定するワイヤー型」が用いられます。
お子さまには取り外し式が使用されることが多く、学校や食事中など生活に合わせて使いやすい反面、「使い忘れ」や「紛失」のリスクがあります。
取り外し式の保定装置は、就寝中の装着が基本となり、最初の数か月は毎日、それ以降は徐々に使用頻度を減らしていきます。
ただし、個々の歯の動き方や骨の状態によって異なるため、歯科医の指示通りに使うことが大前提です。
装置が変形したり、壊れたりした場合も、すぐに連絡することが重要です。放置してしまうと、歯が少しずつ動き始め、再び矯正装置を装着しなければならなくなることもあります。
また、保定装置の使用中も虫歯予防のためのケアは欠かせません。特に装置の隙間や留め具部分に食べかすが溜まりやすいため、丁寧な歯みがきを習慣にしましょう。
保定期間は1〜2年が目安、でも油断は禁物
保定期間の長さは個人差がありますが、多くの場合1〜2年が目安とされています。中には成長が落ち着くまで数年間にわたってリテーナーを使うケースもあります。
特にお子さまは骨の成長が続くため、定期的な経過観察を行いながら、必要に応じて装置の変更や装着時間の見直しが行われます。
保定期間中は、矯正治療の“仕上げ”という重要なステージです。ここでの努力と継続が、将来にわたって美しい歯並びと良好な噛み合わせを維持するカギとなります。
「装置が外れたから終わり」と思わず、「ここからが新しいスタート」と捉えて、お子さまの口腔の健康を見守っていくことが大切です。
また、保護者の方が一緒にリテーナーの管理を行い、通院をサポートすることも、保定期間の成功には欠かせません。
装着忘れを防ぐためのアラームやカレンダー管理、定期的な声かけなど、ご家庭でできる小さな工夫が積み重なることで、後戻りを防ぎ、治療の成果を長く保つことができるのです。
9.「長く感じる」治療期間との向き合い方

矯正は“ゴールが遠く感じる”からこそ、工夫が必要
小児矯正は、数か月では終わらず、Ⅰ期・Ⅱ期あわせて数年にわたることも少なくありません。そのため、親御さんにとっても、お子さまにとっても「終わりが見えない」「思っていたより長い」と感じてしまうのは自然なことです。
特に、途中で装置の使用がつらくなったり、見た目が気になったりする年齢に差し掛かると、モチベーションが下がる場面も出てきます。
しかし、矯正治療は「今のがんばりが将来につながる」という長期的な視点が必要な医療です。
だからこそ、治療中に気持ちが折れないような工夫を取り入れることが、成功への鍵となります。小さな成功体験を積み重ねながら、本人の中に「治したい」という意志が育つようなサポートが求められます。
子どもの“やる気”を引き出すサポート術
お子さまのモチベーションを保つために大切なのは、「矯正=我慢」と感じさせない工夫です。たとえば、装置の装着時間を守れたらカレンダーにシールを貼る、診察後にご褒美を用意するなど、日常の中で“達成感”を感じられる工夫が効果的です。
また、治療の経過を見える化するのも一つの方法です。写真で治療前後の違いを見せてあげると、「こんなに変わったんだ!」と実感し、自信につながることがあります。
歯科医師やスタッフが子どもにわかる言葉で説明し、少しでも「自分ごと」として捉えられるようにすると、治療への理解も深まります。
保護者の関わりも非常に重要です。「頑張ってるね」「ちゃんと続けられてすごいよ」といった声かけは、子どもの自己肯定感を高め、継続へのモチベーションになります。
逆に「ちゃんとやらないとダメ」「また忘れたの?」といったネガティブな言葉は避け、共に乗り越えるスタンスで寄り添いましょう。
“未来の笑顔”を思い描けるかどうかが分かれ道
矯正治療は、今すぐの結果を求めるものではなく、「数年後に整った歯並びで自信を持って笑える未来」を目指すプロセスです。
この“未来の自分”をお子さまが想像できるようになると、治療期間がポジティブに感じられるようになります。
たとえば、「歯がきれいになったら何がしたい?」といった質問からイメージを広げると、目標が明確になりやすくなります。七五三や入学式、卒業アルバムの写真など、節目のイベントをモチベーションにするのも良い方法です。
治療中にスランプが訪れても、「やめたらどうなるか」「今までの努力がどう活きるか」を一緒に確認することで、原点に立ち返ることができます。
そのためには、定期的に「振り返る」時間を作り、どれだけ変化したのかを本人と共有することがとても大切です。
最後に、矯正治療の道のりは長くても、決して孤独なものではありません。歯科医師・歯科衛生士・保護者、そしてお子さま自身がチームになって歩むからこそ、乗り越えられるものです。
「時間がかかること」は必ずしも悪いことではありません。それだけじっくり、丁寧に整えている証です。
一緒に未来を見据えながら、前向きに進んでいける環境づくりが、お子さまにとっての何よりの支えになるはずです。
10. まずは相談から。“今できること”を知る勇気

「矯正が必要かも…」と思ったときこそ、動き出すタイミング
お子さまの歯並びを見て、「このままで大丈夫かな?」「矯正が必要なのか分からないけど気になる」と感じたことはありませんか?
実際、多くの保護者の方がそうした“気づき”をきっかけに矯正歯科の門を叩いています。
矯正治療は、「歯並びが悪くなってから始める」のではなく、「気になった時点で相談する」ことで、より良い結果が得られる治療です。
特に小児矯正は、顎の成長が活発な時期を活かせる“タイミングの医療”です。
成長期を逃さずに始めることで、骨格からバランスを整えることが可能になり、将来的な抜歯のリスクや矯正期間の短縮にもつながります。
「今すぐ治療を始めなければならない」というわけではありませんが、「今の状態を知る」ことで、“最適なタイミング”を逃さずに済むのです。
相談=治療のスタートではありません
矯正歯科への相談というと、「治療を始めることが前提」と感じてしまい、なかなか一歩が踏み出せない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、初診相談の段階で治療をスタートするケースばかりではありません。
むしろ、「今は様子を見ましょう」という判断になることも多く、歯の生え変わりや成長を見ながら、最適な時期を待つことも大切な選択です。
初診相談では、お子さまの歯並びや顎の状態、口腔習癖などを丁寧にチェックし、「今どんな状態なのか」「これからどう変化していくのか」を詳しく説明します。
そのうえで、すぐに治療を始めるべきか、あるいは経過観察をしながらタイミングを待つかを一緒に考えていきます。
ご家族の不安や疑問に寄り添いながら、治療の必要性や方法、費用や期間についても丁寧にご案内いたします。
治療を迷っている段階でも、まずは相談して現状を知ることが、最も確実で安心できる一歩になります。「相談=決断」ではないということを、ぜひ知っておいてください。
未来を変える“今”の選択。親としてできること
歯並びの問題は、見た目だけでなく、発音・咀嚼・顎の成長、さらには姿勢や呼吸にも影響を及ぼすことがあります。
それらを予防し、より健康で快適な未来につなげていくためには、「今、何ができるのか」を把握しておくことがとても重要です。
保護者の方が少しでも「気になる」と感じたときこそ、受診のベストタイミングです。
忙しい日々のなかで、「まだ小さいし」「歯が全部生え揃ってからでいいかな」と思いがちですが、矯正歯科の視点では“今”だからこそ可能な治療法があることも少なくありません。
後になって「もっと早く相談していれば…」と後悔しないためにも、まずは気軽にご相談ください。
矯正治療は、お子さまが自信を持って笑える未来のための、大切な準備です。
その第一歩は、「今の状態を正しく知る」ことから始まります。
私たちは、ご家族と一緒に、お子さまにとって最適な治療の時期や方法を見つけていくパートナーでありたいと考えています。
少しの勇気が、大きな安心につながるはずです。まずはお気軽にご相談ください。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより