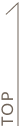1. 「歯並び、大丈夫かな?」と感じたら今がチャンス

・3歳頃から見える“歯並びの兆候”とは
お子さまの成長のなかで、「なんとなく歯の並びが気になる…」と感じる瞬間があるかもしれません。実は、歯並びの乱れは3歳頃から兆候として見えてくることがあります。
代表的なサインとしては、前歯が交差している「反対咬合(受け口)」、前歯の間に大きなすき間がある「すきっ歯」、また歯がねじれて生えているような「乱ぐい歯(叢生)」などがあります。
これらのサインは、永久歯への生え変わりを待たずとも、乳歯列期の段階で見極めが可能です。「どうせ生え変わるし…」と見過ごされがちですが、実は乳歯の状態から矯正治療の必要性が分かるケースも多くあります。
・「様子を見よう」はリスク?早期発見のメリット
「様子を見ましょう」と言われたから…と経過を見守る保護者の方も多くいらっしゃいます。しかし、歯並びの問題の多くは、放置するほどに骨格や咬み合わせに影響を及ぼす可能性があります。
例えば、顎の成長が偏ってしまったり、上下の噛み合わせのズレが固定化したりすると、将来的な本格矯正において治療期間や費用が大きくなることもあります。
早期の段階で問題点に気づくことができれば、「成長誘導」と呼ばれる骨格や歯列の発育を正しい方向に導くアプローチが可能です。このような治療は、お子さまにとっても負担が少なく、結果的により自然で整った歯並びへとつながります。
・お口の機能チェックも大切なポイント
見た目の歯並びだけでなく、お口の機能も非常に重要な判断材料です。
たとえば、口呼吸が多い、発音がはっきりしない、食べ物を噛みにくそうにしている、いつもお口が開いている——これらの様子が見られたら、実は歯並びや顎の発育に影響している可能性があります。
また、指しゃぶりや頬杖、舌を前に出す癖(舌突出癖)なども歯並びを乱す原因になります。こうした“癖”や“機能面の異常”は、見た目以上に深刻なトラブルを引き起こすこともあるため、単なる審美の問題と捉えず、総合的な診断が必要です。
当院では、単に「歯がきれいに並んでいるか」だけでなく、「噛む」「飲み込む」「話す」といったお口全体の機能面も含めて評価し、お子さまの将来を見据えたアドバイスを行っています。
お子さまの歯並びに少しでも気になるサインが見られたら、それは“今”がチャンスかもしれません。早めに気づき、適切なケアや観察を始めることで、より自然で健康的な成長を促すことができます。
「まだ小さいから大丈夫」と思わず、気になる点があればお気軽にご相談ください。小児矯正の第一歩は、“気づいたときに動き出す”ことから始まります。
2. 子どもの歯並びは“育てていく”ものです

・成長過程で変化する顎と歯のバランス
子どもの歯並びは、ただ「きれいに生えそろうのを待つもの」ではありません。実は、顎の発育や乳歯と永久歯の生え変わりなど、成長の段階によって常に変化しています。
たとえば、乳歯列の頃にスペースがぎっしり詰まっていると、「歯並びが良さそう」と思うかもしれません。しかし、これは永久歯が生えるスペースが足りないサインかもしれないのです。永久歯は乳歯より大きいため、その分の“隙間”が必要です。
また、顎の骨の成長スピードや方向も、歯の並びに大きな影響を与えます。上下の顎がアンバランスに育てば、受け口や出っ歯の原因になります。つまり、子どもの歯並びは「育っていく」ものであり、「育て方次第で変わる」ものなのです。
・歯並びの土台となる「噛み合わせ」の重要性
きれいな歯並びは、見た目だけの問題ではありません。「正しい噛み合わせ」があることで、食べ物をしっかり噛める、言葉を明瞭に発音できる、顔や身体のバランスが整う——こうした多くの機能が正常に働きます。
逆に、噛み合わせにズレがあると、食べこぼしや発音のしづらさだけでなく、偏った顎の使い方が習慣化されてしまい、将来的に顎関節症や肩こり、姿勢不良につながることもあります。
また、噛む力が偏ることで歯にかかる負担が不均等になり、虫歯や歯周病のリスクも高まります。噛み合わせを正しく導くことは、健やかな成長と将来の健康への“投資”ともいえるのです。
・姿勢や呼吸が歯並びに影響する理由
歯並びを“育てる”という視点で見ると、意外かもしれませんが、姿勢や呼吸の習慣も大きなカギになります。
たとえば、いつも猫背で頭を前に出した姿勢をとっていると、舌の位置が下がり、正しく上顎に舌が収まらなくなります。舌は上顎の内側を支える重要な筋肉でもあるため、これがうまく働かないと顎の幅が狭くなり、結果として歯が並ぶスペースが不足してしまいます。
さらに、口呼吸の習慣があると、唇を閉じる力が弱くなり、前歯が外に押し出されやすくなります。これは出っ歯や開咬(前歯が閉じない状態)の原因にもつながります。
このように、正しい歯並びを「作る・保つ」ためには、歯や顎だけでなく、お子さまの全身の姿勢や呼吸法といった“生活習慣”にも目を向けることが重要です。
子どもの歯並びは、自然に整うこともありますが、多くの場合は正しい育て方を知っているかどうかが将来の結果を大きく左右します。
当院では、歯の状態だけでなく、姿勢や呼吸、噛み方のクセまで含めた包括的な視点でお子さまの成長をサポートしています。将来のお子さまの健康的な笑顔のために、今できることを一緒に考えていきましょう。
3.「矯正は小学生から」と思っていませんか?

・乳歯列期からできる“成長誘導”という考え方
「矯正は永久歯が生えそろってから」とお考えの保護者の方も多いかもしれません。しかし実際には、すべての永久歯が生えそろう前の“乳歯列期”から始められる矯正もあります。
この段階の矯正は「成長誘導」とも呼ばれ、顎の発育をコントロールしたり、悪習癖(指しゃぶり・口呼吸など)を改善したりすることで、歯並びが悪くなる原因そのものにアプローチします。
つまり、見えている歯の位置を整えるだけでなく、「これから歯並びが悪くなるのを防ぐ」という、いわば“予防矯正”のような側面もあるのです。
・5〜8歳で治せる癖と骨格のゆがみ
子どもの歯並びに影響するのは、歯そのものの問題だけではありません。実は、舌の位置や呼吸の仕方、姿勢、指しゃぶりなどの日常的な“癖”も、顎の成長や歯の並びに深く関係しています。
こうした癖や骨格的な問題は、5〜8歳頃の比較的早い段階であれば、柔軟に対応しやすく、大きな矯正装置を使わずに改善できる可能性もあります。
この時期にマウスピース型の装置(例:プレオルソ)やトレーナー装置などを使い、筋機能の改善や顎の成長を促すことで、後の本格矯正が必要なくなるケースも少なくありません。
・本格矯正が必要なくなることもある
早期からの成長誘導矯正は、すべてのケースで本格的な矯正を回避できるわけではありませんが、「永久歯が並ぶスペースをしっかり確保できた」「出っ歯や受け口の傾向が改善された」といった成果が出れば、その後のⅡ期治療(本格矯正)の必要性が軽減されることがあります。
特に、顎の骨格的なバランスの乱れや口呼吸などが長期化すると、永久歯が正しい位置に生えること自体が難しくなり、矯正期間が長期化したり、抜歯の必要性が出てくることもあります。
「矯正は小学生から」と思い込まず、お子さまの成長を活かせる“今この時期”を見逃さないことが、将来の歯並びだけでなく、お子さまの健康的な成長全体にもつながるのです。
「早すぎる矯正は良くないのでは?」と不安に思う保護者の方もいらっしゃいますが、実際には、乳歯列期の矯正は“治療”というよりも“育成”に近いアプローチです。
お子さまの歯や顎の成長は日々変化しており、「矯正を始めるかどうか」よりも、「どんな状態かを知る」ことがまず大切です。
当院では、年齢に応じた段階的な診断と、無理のない治療計画をご提案しております。矯正の必要があるかないか、気になり始めたら、それが最初の一歩になるタイミングかもしれません。
4. 矯正治療の対象となる“見た目と機能”のサイン

・受け口・出っ歯・デコボコの歯並び
見た目で分かる歯並びの問題には、「前歯が出ている(出っ歯)」「下の歯が上の歯より前にある(受け口)」「歯が重なり合っている(叢生/デコボコ)」などがあります。
これらは永久歯に生え変わる過程でも自然に改善することは少なく、むしろ成長とともに目立つことも多いため、早期のチェックが大切です。
また、歯の位置が悪いと、かみ合わせがずれて顎関節に負担がかかったり、虫歯や歯周病のリスクが高まったりする可能性もあります。お子さまの歯並びが「ちょっと気になるな」と感じたら、それは矯正相談のきっかけになります。
・口呼吸・舌の癖・発音の不明瞭さ
お口の機能に関わるトラブルも、矯正治療の重要な対象です。たとえば「常に口が開いている」「鼻ではなく口で呼吸している」などの口呼吸は、歯並びや顎の成長に大きな影響を及ぼします。
また、舌を前に突き出す癖(舌突出癖)や、正しく舌を動かせないことで、発音が不明瞭になるケースもあります。
これらは「MFT(口腔筋機能療法)」と呼ばれるトレーニングや、マウスピース型装置を併用して改善が可能です。単なる“発音の問題”ではなく、根本にある歯並び・舌・口腔周囲筋のバランスの崩れに目を向けることが重要です。
・指しゃぶりや頬杖などの悪習癖も要注意
乳幼児期の癖はかわいらしく見えることもありますが、長期的に続くと歯並びや顎の成長に悪影響を与える原因になります。
代表的なのは、指しゃぶりや頬杖、爪を噛む、舌を吸うといった癖です。特に指しゃぶりが長期間続くと、出っ歯や開咬(前歯がかみ合わない状態)になるリスクが高くなります。
これらの癖は、早期にやめることで自然に改善することもありますが、場合によっては矯正治療によって歯列の成長を適切に導く必要が出てきます。
「癖ぐらいで矯正?」と思われるかもしれませんが、こうした日常習慣の積み重ねこそが、歯並びに大きな影響を与えるのです。癖の段階で気づければ、それだけで将来の治療負担が減る可能性もあるのです。
このように、矯正治療が必要かどうかは「見た目の歯並び」だけでは判断できません。
お子さまの呼吸、舌の使い方、発音、そして日々の癖など、見えにくい“機能面”のサインも、しっかりと観察していくことが大切です。
「まだ小さいから」「永久歯が生えそろってから」と待っているうちに、改善しにくい状態へ進んでしまうこともあります。
少しでも気になる点があれば、専門の矯正歯科で相談してみることをおすすめします。小さな気づきが、大きな治療の第一歩につながります。
5. 矯正が必要かどうかはプロの目で判断を

・かかりつけの小児歯科では気づかれないことも
日頃から定期的に通っているかかりつけの小児歯科がある場合、「歯並びも見てもらっているから安心」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、矯正治療は非常に専門的な分野であり、通常の小児歯科では“矯正の必要性を判断するだけの検査・分析”までは行わないケースもあります。
例えば、見た目には歯がきれいに並んでいるように見えても、「上下のかみ合わせがズレている」「成長にともなって将来的に悪化する可能性がある」など、矯正専門医でなければ見抜けない問題もあるのです。
かかりつけ医と併用して、矯正歯科の相談を受けることは、お子さまの将来の健康な口腔環境を守るうえでとても有効です。
・専門的な分析による「経過観察」という選択肢
矯正相談に行くと、「すぐに治療が始まるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、「今はまだ治療の必要はないが、将来的に矯正が必要になるかもしれない」と判断された場合、“経過観察”という選択肢が取られることも多くあります。
この経過観察では、お子さまの顎や歯の成長バランス、永久歯への生え変わりの進行状況を、数ヶ月〜半年おきに記録しながら最適なタイミングを見計らうという大切なプロセスが行われます。
むやみに早く始めるのではなく、医学的根拠にもとづいた「開始のタイミング」を見極めることが、無駄なく効率的な矯正治療へとつながるのです。
・治療が不要と分かるだけでも安心材料に
矯正相談の結果、「現時点では治療の必要はありません」と言われることもあります。
それでも、親御さんにとっては「このまま様子を見ても大丈夫なんだ」という確かな判断が得られることで、大きな安心につながります。
また、お子さま自身も「歯並びが気になっていたけど、今は大丈夫なんだ」と自信を持つことができ、日々の生活や歯みがきにも前向きに取り組めるようになることがあります。
矯正治療は“やるか・やらないか”の二択ではなく、“今必要か・将来的に必要になるか・不要か”という多様な可能性がある診断です。
一度、プロの目でしっかり診てもらうこと自体が、将来への備えとなります。
矯正のタイミングは「様子を見よう」としている間に逃してしまうこともあります。
成長が関係するからこそ、“今”の状態を専門的に分析し、必要なら適切な時期に始める。それが結果的にお子さまにとって最良の選択になるのです。
迷ったら、まずは矯正専門の歯科医に相談してみましょう。
治療が必要かどうかを知るだけでも、確かな安心と判断の指針を得ることができます。
6. 3歳〜小学生低学年のうちにできるやさしい矯正

・プレオルソなどのマウスピース矯正とは?
「矯正治療=歯に金属の装置をつける」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、近年は3歳〜小学生低学年のうちから、負担の少ない“やさしい矯正”が可能になっています。
その代表が「プレオルソ」などのマウスピース型矯正装置です。
プレオルソは、取り外し可能なやわらかい素材の装置で、主に日中1時間と夜間の就寝中に装着することで、歯並びだけでなく舌や唇の筋肉バランス、正しい呼吸・飲み込みの習慣も整えていく治療です。
「矯正治療は怖い、痛そう」と感じるお子さまでも、比較的スムーズに受け入れやすいのが特徴です。
・痛みが少なく、取り外しもできる装置の特徴
従来のワイヤー矯正と比べて、マウスピース矯正は非常に快適で安全性も高いとされています。
柔らかいシリコン製やウレタン素材でできているため、お口の中に装着しても違和感や痛みが少なく、お子さまのストレスを最小限に抑えられます。
また、取り外しが可能なので、食事や歯みがきのときには外して清潔に保つことができます。
この「自分で取り外せる」という要素は、お子さま自身の主体性を育てることにもつながります。
ただし、保護者の方がしっかり管理し、指示された装着時間を守ることが治療の効果を左右する重要なポイントです。
・お子さまが嫌がらない工夫も大切
小さなお子さまの矯正治療において最も大切なのは「継続できること」。
いくら優れた装置でも、毎日使わなければ効果は得られません。
そのためには、装置を“嫌がらずに使ってくれる”ことが必要です。
当院のような小児矯正に力を入れている歯科医院では、初めての装着時にお子さまが怖がらないよう、スタッフが丁寧に声かけしながら練習したり、装置に色をつけたり、シールを貼るなどの楽しい工夫を取り入れています。
また、治療のたびに「がんばったね」と褒めてもらえることが、お子さまのモチベーションにもつながります。
おうちでも「一緒に頑張ろうね」と励ましながら、楽しく続けられる環境を整えてあげることが、成功への近道です。
このように、3歳〜低学年のうちに始められるやさしい矯正は、単に歯を動かすだけでなく、お子さまの“お口の機能を育てる”という視点を大切にしています。
成長の初期段階で正しい機能を身につけることで、将来的に大掛かりな矯正治療が不要になるケースも少なくありません。
「今は早すぎるのでは?」と思わずに、一度専門的な相談を受けてみることをおすすめします。
その一歩が、お子さまの未来の健康と笑顔につながります。
7. 治療開始のタイミングは「生え変わり」がカギ

・前歯と奥歯が生え変わる時期を見逃さない
子供の歯並びにおいて、実はとても大きな意味を持つのが「歯の生え変わりのタイミング」です。
特に注意したいのは、6歳頃から始まる前歯と奥歯の交換時期です。この時期は、乳歯が抜けて永久歯が生えてくる“過渡期”にあたります。
この時期に、永久歯が正しい位置に生えてこられるように環境を整えることで、将来的な矯正治療の必要性や負担を軽減できる可能性があります。
例えば、前歯の永久歯が重なって生えてくる、奥歯の生える位置が内側にズレている、といったサインを早くキャッチできれば、成長に合わせた“軽度で済む矯正”が可能になります。
・6歳臼歯の位置が将来の歯並びを左右する
矯正の専門家が必ず確認するのが「6歳臼歯」と呼ばれる第一大臼歯の生え方です。
6歳臼歯は、乳歯の一番奥のさらに奥から生えてくる初めての永久歯で、上下の噛み合わせや顎の成長を左右する“鍵”とも言える重要な歯です。
この歯が正しく生えないと、全体の噛み合わせや歯列アーチが乱れる原因になります。
しかし、6歳臼歯は見えにくい場所にあるため、保護者が気づかないうちに傾いて生えてしまうこともあります。
定期的に歯科医院でチェックを受けることで、このようなリスクを早期に発見・対処することができます。
・“今できること”を逃さないための定期チェック
「まだ小さいから矯正は先でいい」と思われがちですが、矯正治療は“始めるタイミング”がとても重要です。
特に乳歯から永久歯への移行期は、歯や顎の成長に働きかけやすく、「今しかできない治療」があるのです。
実際、骨格のズレや癖を早めに治すことで、本格的な矯正治療が不要になったり、期間や費用が抑えられるケースも多く見られます。
そのためには、3〜6ヶ月に1回程度の定期チェックを受けて、成長のステージごとのリスクを見逃さないことが大切です。
当院では、歯の生え変わりだけでなく、噛み合わせ・顎の発育・口呼吸や舌癖の有無なども総合的に確認し、お子さま一人ひとりに合ったケアを行っています。
矯正治療は、「いつから始めるか」で結果が大きく変わります。
永久歯が生えそろってからではなく、“乳歯と永久歯が混在する時期”こそが、最も適切な矯正のタイミングになることも多いのです。
生え変わりの兆候が見られたら、まずは専門的なチェックを受けてみましょう。
お子さまにとって最良のタイミングで、無理のない矯正をスタートできるかもしれません。
8. 矯正治療の流れと期間の目安を知っておこう

・Ⅰ期(成長誘導)とⅡ期(本格矯正)の違い
子供の矯正治療は、「Ⅰ期治療」と「Ⅱ期治療」の2段階に分かれています。
Ⅰ期治療は乳歯がまだ残っている「混合歯列期(5〜10歳頃)」に行う矯正で、顎の成長をコントロールしたり、歯並びが悪化しないように導く“予防的”な治療です。
対してⅡ期治療は、永久歯がほぼすべて生えそろった「12歳前後〜」に行う本格的な矯正で、ブラケット矯正やマウスピース矯正などを使って歯を1本ずつ動かしながら理想的な歯並び・噛み合わせをつくっていきます。
Ⅰ期で土台を整えておくことで、Ⅱ期での治療期間が短くなったり、場合によってはⅡ期自体が不要になることもあります。
・平均的な通院頻度と治療期間
Ⅰ期治療の平均的な治療期間は1〜2年程度、月に1回〜2ヶ月に1回のペースで通院するのが一般的です。
この段階では、取り外し可能なマウスピース型の装置(例:プレオルソなど)を使用し、お子さまにとって負担の少ない治療が行われます。
Ⅱ期治療に進んだ場合は、2〜3年ほどかけて歯を正しい位置に動かしていきます。
使用する装置や治療の複雑さによっても期間は変わりますが、こちらも通院頻度は月に1回が目安です。
矯正治療は長期間にわたる通院が必要となるため、ライフスタイルや学校のスケジュールと調整しやすいかどうかも重要なポイントです。
・ご家族の協力がスムーズな治療の鍵
特にⅠ期治療では、お子さまが装置を正しく装着するかどうか、毎日決まった時間使えているか、という点が治療成果に大きく影響します。
そのため、ご家庭でのサポートが非常に重要です。
「今日の分、ちゃんとつけたかな?」「痛みや違和感はないかな?」といった声かけや励ましが、治療継続のモチベーションにもつながります。
また、歯並びが改善してくると、ご本人の自信や笑顔が増えてくるため、ポジティブな変化を一緒に喜ぶ姿勢も大切です。
歯科医院とご家族がチームとなってお子さまを支えることで、よりスムーズに、より前向きに治療が進みます。
子供の矯正治療は「長くかかるのでは…」と不安に思われる方も多いかもしれません。
しかし、適切なタイミングで開始し、段階的に治療を進めていくことで、子どもの成長と調和した“やさしい矯正”が可能になります。
まずは現在の歯並びの状態を確認し、「今、必要なのはⅠ期治療か?それとも経過観察で十分か?」を判断するところから始めましょう。
矯正治療の流れや目安を知っておくことは、保護者の不安を減らし、納得して治療を進めるための大きな助けとなります。
9. 矯正治療で得られる“未来の笑顔”

・見た目だけでなく、健康的な成長のサポート
矯正治療というと、「見た目の改善」だけが注目されがちですが、実は子どもの成長全体を支える治療でもあります。
歯並びや噛み合わせが整うことで、正しく噛めるようになり、あごや顔面の筋肉がバランスよく成長します。
また、発音や呼吸の質にも影響を与えるため、口呼吸の改善や滑舌の向上といった副次的な効果も期待できます。
見た目が整うことでお子さまの印象もぐっと明るくなり、内面の自信や積極性にもつながっていくのです。
・歯磨きしやすくなることで虫歯予防にも
歯並びがガタガタしている状態では、ブラシが届きにくく磨き残しが多くなりがちです。
とくに奥歯が重なっていたり、前歯が極端に出ていたりする場合は、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
矯正治療によって歯が正しい位置に整うと、歯磨きがしやすくなり、セルフケアの質が大きく向上します。
これは、矯正後の歯を長く健康に保つ上でも大きなメリットとなります。
小さい頃から歯並びを整えることで、将来的な虫歯・歯周病のリスク軽減にもつながるのです。
・自信を持って笑えるお子さまの姿へ
歯並びを気にして、口をあけて笑えなかったり、人前で話すのが苦手になってしまうお子さまも少なくありません。
しかし、矯正治療を通じて自分の歯並びがきれいになっていく過程は、自己肯定感を高める貴重な経験にもなります。
「前より話しやすくなった!」「友達に褒められた!」といった声をきっかけに、表情が明るくなり、性格も積極的になるお子さまも多くいらっしゃいます。
また、大人になってからも歯並びのコンプレックスに悩まずに済むことは、将来の健康や人間関係にも良い影響を与えてくれます。
矯正治療を通じて得られるのは、見た目の美しさだけではなく、心と体の健やかな成長、そして未来への自信です。
そのためにも、保護者の方が早い段階で「歯並びのチェック」や「相談」という一歩を踏み出してあげることが、何より大切だといえるでしょう。
10. まずは一度、相談だけでも大丈夫です

・初回カウンセリングで分かること
お子さまの歯並びが気になってきたとき、「矯正が本当に必要なのか分からない」「まだ早いのでは?」と悩む保護者の方は少なくありません。
そんなときこそ、まずは初回の矯正相談をおすすめします。
初回カウンセリングでは、現在のお口の中の状態を丁寧に確認し、成長や発育の状況も踏まえたうえで、矯正が必要かどうかを専門的に判断します。
また、矯正を始める適切なタイミングや、将来的な治療の必要性、考えられる選択肢についても詳しく説明を受けることができます。
「今すぐ治療が必要か」だけでなく、「今後どういう流れで様子を見ていくか」まで見通せることで、保護者の不安が大きく和らぐのです。
・“矯正はまだ早い?”という不安も解消
3歳や4歳といった乳歯列期のお子さまであっても、早期に癖を見つけることは将来的な歯並びに大きな意味を持ちます。
例えば、指しゃぶり、頬づえ、舌の癖、口呼吸といった「悪習癖」は、顎の成長を阻害したり、歯列を乱したりする原因になり得ます。
こうした癖は早く気づくほど改善がしやすく、矯正の介入が必要なくなるケースもあるのです。
「まだ様子を見よう」と考えている間に、骨格や歯列のゆがみが固定化してしまう可能性もあるため、不安がある時点で一度ご相談いただくことが非常に大切です。
・お子さまに合わせたタイミングと方法をご提案
矯正治療は「何歳から始めるべき」と一概に決まっているわけではありません。
お子さまの成長スピードや骨格の状態、生活習慣、性格の傾向まで考慮したうえで、最も無理のない時期や治療法をご提案します。
「今は経過観察だけでOK」「あと半年後がベスト」など、段階的なアプローチも可能です。
また、マウスピース型の装置やプレオルソのような取り外し式の装置を活用することで、お子さまの負担を最小限にしながら治療が行えることもあります。
カウンセリングの場では、ご家族の希望やライフスタイルについても丁寧に伺いながら、納得いただける形での治療計画を一緒に考えていきます。
「相談してよかった」「モヤモヤが晴れた」と多くの方がおっしゃいます。
まずは一度、気軽な気持ちでのご相談から、始めてみてはいかがでしょうか。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより