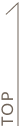「うちの子、受け口かも…」と気づいたら

お子さまの受け口に気づいたら、まず確認してほしいこと
お子さまの歯の噛み合わせを見たとき、「下の歯が前に出ている気がする」「上の前歯よりも下の前歯が目立つ」——そんなふうに感じたことはありませんか?それは、医学的に「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれる状態で、いわゆる“受け口”の可能性があります。
受け口は単なる見た目の問題だけでなく、お子さまの健やかな発育に関わる機能面・健康面に大きな影響を与える咬合異常のひとつです。特に小さなお子さまの受け口は、早期に適切なタイミングで治療を行うことで、骨格の成長方向そのものを整えることが可能です。
親が気づきやすい“受け口のサイン”とは?
日常生活の中で、次のようなサインが見られる場合には注意が必要です。
・正面から見て、上下の前歯が逆に噛み合っている(下の歯が前に出ている)
・横顔を見たときに、下あごが前に突き出ているように見える
・食事のとき、噛みにくそうにしている
・発音がこもる、舌足らずな話し方になっている
・口元の印象に違和感を感じる
これらは、受け口の初期サインである可能性があります。
放置するとどうなるのか?
「そのうち自然に治るかもしれない」「永久歯に生え変わったら考えよう」——そう考える保護者の方も少なくありません。
しかし受け口は、放置することで骨格の成長方向が定着してしまい、大人になってからでは外科的処置が必要になる可能性もあります。
また、下顎前突は咀嚼や発音、さらには姿勢や全身のバランスにも影響を与えることがわかっています。特に、噛み合わせが悪いことで消化不良になったり、発音が不明瞭でコミュニケーションに支障が出たりするケースもあります。こうした機能的な問題は、成長とともにさらに複雑化していくため、できるだけ早期の対応が望ましいのです。
受け口治療の“ベストタイミング”とは
お子さまの成長に合わせて、受け口の治療には「Ⅰ期治療(成長誘導)」と「Ⅱ期治療(歯列矯正)」という2つの段階があります。
特にⅠ期治療は、5〜8歳の混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)が重要なタイミングとされており、顎の成長方向をコントロールできる数少ない時期です。
この時期に、受け口の原因となっている悪習癖(舌癖、口呼吸、逆咬合のクセ)や骨格の不調和に対してアプローチすることで、将来的な歯列矯正の負担を軽減したり、抜歯のリスクを回避することにもつながります。
少しでも不安があるなら、まずは矯正専門医へ
受け口は、早期に発見し、正しい時期にアプローチすることで大きな改善が見込める疾患です。見た目に違和感を感じるだけでなく、「何かおかしいかも」と思ったその直感こそが、正しい治療への第一歩となります。
私たちは、お子さまの成長と将来を見据え、歯を削らずに整える「マウスピース矯正」をはじめとしたさまざまな治療法をご用意しています。
受け口かもしれない——そう思った時点で、まずは一度、矯正の専門医にご相談ください。治療するかどうかを決めるのは、診断を受けてからでも遅くはありません。
子どもの成長と“あごのバランス”

子どものあごが出てきたと感じたら
「子どものあごが出てきた気がする」「横顔のバランスが気になる」——このようなお悩みをお持ちの保護者の方は少なくありません。成長過程にあるお子さまの下顎前突(受け口)は、単なる歯並びの問題にとどまらず、“骨格の成長バランス”が大きく関係していることをご存じでしょうか?
下顎前突は、下あごが過剰に成長している、または上あごの成長が不十分であることが原因で起こる場合が多くあります。これらの成長の偏りは、乳歯期や混合歯列期の早い段階から現れることがあり、早期に適切な対処をすることで、骨格全体のバランスを整えやすくなります。
骨格的な問題か?それとも生活習慣が原因か?
下顎前突には大きく分けて2つの原因があります。一つは、骨格そのものに起因する「骨格性の受け口」。もう一つは、舌や唇の使い方、口呼吸、頬杖などの生活習慣に起因する「機能性の受け口」です。
特に、舌で前歯を押すクセや指しゃぶり、うつ伏せ寝などの“無意識の習慣”が長く続くと、上顎の発達が妨げられ、結果として下顎が前に出てしまうというケースも少なくありません。逆に言えば、これらの生活習慣を早めに見直すだけでも、症状の悪化を防げる可能性があります。
成長期は骨のバランスを整える“最大のチャンス”
子どもの骨はまだ柔らかく、成長に伴って日々変化しています。特に、6〜10歳頃は顎の骨の成長をコントロールしやすい時期です。このタイミングを逃すと、骨格の偏りが固定されてしまい、思春期以降の治療が難しくなることも。
当院では、この成長のチャンスを逃さず、あごの成長方向をコントロールする矯正装置や、悪習癖を改善する機能的矯正装置などを組み合わせた「Ⅰ期治療」をご提案しています。こうした治療は、ただ歯を動かすのではなく、“正しい成長を促す”ことを目的としているのが大きな特長です。
親子で気づける“小さなサイン”が治療の入り口
「うちの子、下あごが出てるかな?」と感じたときは、以下のようなサインをチェックしてみてください。
・正面から見て、下の前歯が上の歯より前にある
・食事中に前歯でうまくかみ切れない
・横顔を見たときに、顎が前に突き出ている
・サ行・タ行などの発音が不明瞭
・唇が閉じにくそう、口がぽかんと開いている
これらの兆候は、受け口や顎のバランス異常の“入り口”かもしれません。早めの相談によって、適切な成長誘導や生活習慣の見直しだけで症状が改善するケースもあります。
削らず、抜かずに整えるために——
松本デンタルオフィス for キッズの「削らない審美歯科」では、お子さまの成長を最大限に活かしたマウスピース型の機能矯正装置やプレオルソ・ムーシールドなどの取り外し式装置を使いながら、自然な成長を妨げず、将来の本格矯正が不要になるよう導くことを目指しています。
「まだ治療が必要か分からない」「いつから始めたらいいのか迷っている」——そんなときこそ、まずは一度、矯正専門医にご相談ください。成長のステージに合わせた“今、できる最善”をご提案いたします。
受け口は早期発見がカギ

早期発見・早期対応が未来を変える
受け口(下顎前突)は、見た目の印象を大きく左右するだけでなく、お子さまの成長や健康、将来的な噛み合わせの安定にも関わる重要な課題です。しかし、多くの保護者の方が「乳歯だから」「様子を見よう」と判断を先延ばしにしてしまうことが少なくありません。
実は、受け口こそ“早期発見・早期対応”が治療の成否を分けるカギ。特にあごの骨が柔らかく、成長が著しい時期にこそ、正しいアプローチをすることが、将来の治療負担や抜歯リスクの軽減に直結します。
第一のチャンスは5歳〜8歳
受け口の治療には、「Ⅰ期治療(成長誘導)」と「Ⅱ期治療(本格矯正)」があります。Ⅰ期治療は、乳歯と永久歯が混在する“混合歯列期”に行う治療で、主に5〜8歳頃が対象です。この時期は、顎の成長が活発なだけでなく、生活習慣や口腔機能がまだ定着していないため、癖の改善や骨格へのアプローチがしやすいというメリットがあります。
このタイミングを逃すと、骨格が固定化しやすくなり、後の治療で外科的手術が必要になるリスクが高まることも。言い換えれば、“治しやすい時期”を逃さないことが、最も大切なポイントなのです。
見た目だけじゃない、受け口による影響
受け口の問題は、見た目の印象や顔立ちのアンバランスにとどまりません。実は、以下のような全身の機能にも関わる深刻な影響が出ることがあります。
・咀嚼機能の低下:前歯でうまく噛めず、奥歯ばかり使って食べるため消化に負担がかかる
・発音障害:舌の動きに制限が出て、サ行・タ行などが不明瞭に
・姿勢の崩れ:顎のズレが体のバランスに影響し、猫背や肩こりの原因になることも
・口呼吸の悪化:口が閉じづらくなることで、風邪やアレルギー性疾患のリスクが高まる
このように、受け口は「ただの歯並びの問題」ではなく、お子さまの心身の成長全体に関わる問題であるという認識が必要です。
自然に治る?その判断には専門的視点が必要です
保護者の中には、「成長とともに自然に治るかも」と様子を見る方もいらっしゃいます。しかし、自己判断で放置してしまうと、最適なタイミングを逃してしまう危険性があります。
確かに、一部の受け口は自然に改善することがありますが、それはごく一部のケース。多くの場合は、骨格的なアンバランスや口腔機能の問題が背景にあり、専門的な検査と診断がなければ正確な見極めは難しいのが実情です。
当院では、お子さまの咬合状態・顎の成長・生活習慣を多角的に診査し、治療が必要かどうかを総合的に判断します。「治すべきなのか、様子を見るべきなのか」——その答えは、歯科医師との相談でしか導き出せません。
「様子を見る」は慎重に——早めの相談が未来を変えます
「まだ早いかな?」「小学生になってからでも大丈夫?」——そう迷ったときこそ、ぜひ一度、矯正専門医にご相談ください。お子さまの成長段階は一人ひとり異なります。今がベストタイミングである可能性もあれば、経過観察で十分な場合もあるでしょう。
私たちは、削らず・抜かず・痛みに配慮した「マウスピース型矯正装置」など、お子さまの負担を最小限に抑えた治療をご提案しています。親御さまの「気づき」が、お子さまの未来の笑顔を守る第一歩です。
当院が行う「下顎前突」早期治療のポイント

受け口治療は“見た目”のためだけではありません
子どもの「受け口(下顎前突)」治療は、単に見た目を整えることが目的ではありません。大切なのは、お子さまが将来にわたって健やかに成長し、正しい咬み合わせと機能を維持できること。そのためには、“早期に適切なアプローチをする”ことが極めて重要です。
当院では、松本デンタルオフィス for キッズが掲げる理念「削らない審美歯科」に基づき、子どもの成長を最大限に活かした、身体に優しい受け口治療を提供しています。ここでは、当院が実践する受け口の早期治療の特徴と考え方をご紹介します。
顎の成長にアプローチする「Ⅰ期治療」の重要性
「Ⅰ期治療」とは、乳歯と永久歯が混ざっている混合歯列期(おおよそ5〜10歳)に行う治療で、顎の骨のバランスや成長方向をコントロールすることを目的としています。
この時期の治療は、歯列を無理に動かすのではなく、“顎の発育を正しく導く”ことが最大のポイント。例えば、上顎の発育が不十分な場合には上顎を前方に促進するような装置を、下顎の成長が過剰な場合にはそれを抑制する装置を使用し、バランスの取れた顔立ちと噛み合わせを目指します。
このように、Ⅰ期治療は将来的な「Ⅱ期治療(本格矯正)」を必要としない、あるいはより軽度な治療で済むようにするための“土台作り”でもあるのです。
「削らない」「抜かない」ためのマウスピース型機能矯正
当院では、受け口のⅠ期治療において、マウスピース型の機能的矯正装置(プレオルソやムーシールドなど)を導入しています。これらは取り外しができ、日常生活への負担が少なく、お子さまが自然に慣れて使える装置です。
装着することで、舌の位置や呼吸、咀嚼筋のバランスが改善され、受け口の原因となる“悪習癖”を取り除きながら顎の成長をコントロールすることができます。また、必要に応じて固定式の急速拡大装置やリンガルアーチなどを併用し、より正確な顎の位置づけと歯列の誘導を行います。
これにより、「歯を抜かずに並べるスペースを確保できる」可能性が高まり、将来的な治療リスクを抑えることにもつながります。
子ども一人ひとりに合わせたカスタムプラン
すべてのお子さまに同じ治療をするわけではありません。顎の大きさ・歯の生え方・生活習慣・装置への適応力は一人ひとり異なります。
当院では、矯正専門の歯科医師が時間をかけて精密な診査を行い、成長発育に応じた「その子だけの治療プラン」をご提案しています。ご家族とも密に連携し、お子さまが前向きに取り組めるよう、説明・サポート体制を整えています。
治療の目的は“笑顔で成長できること”
受け口の早期治療は、将来の口元や顔貌、健康に大きな影響を与えます。しかし、最も大切なのは、お子さまが自信をもって笑えるようになることです。
「矯正って痛い?」「長くかかるのかな?」そんな不安を持つお子さまとご家族に対しても、当院では“痛みの少ない・精神的な負担の少ない矯正”を目指し、やさしい治療をご提供しています。
もしも「もしかして受け口かも?」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。専門医の目で正しく判断することで、お子さまにとってベストなタイミングを見極めることができます。
受け口治療が必要になる“サイン”とは?

見逃さないでほしい“はじまりのサイン”
お子さまの歯並びを見ていて、「これって受け口?」「成長とともに治るのかな?」と迷った経験はありませんか?受け口(下顎前突)は、成長過程に現れることが多く、早い段階で適切に見極めることが、将来の治療負担を大きく左右します。
ただし、受け口の初期兆候は分かりづらく、見た目に現れにくいことも。そのため、親御さんが気づける“サイン”を知っておくことがとても重要です。ここでは、治療の判断材料となる受け口の兆候について、わかりやすくご紹介します。
サイン① 上下の前歯の噛み合わせが「逆」になっている
鏡でお子さまの歯を正面から見たときに、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態が確認できる場合、それは典型的な受け口のサインです。このような噛み合わせは「反対咬合」とも呼ばれ、咀嚼・発音・顎の成長に影響を及ぼすリスクがあります。
「乳歯だからそのうち治る」と放置されがちですが、成長とともにさらに下顎が前に伸びてしまうケースもあるため、注意が必要です。
サイン② 横顔に違和感がある、下あごがしゃくれて見える
お子さまの横顔を見て、下あごが突出していたり、顔全体のバランスに違和感を感じる場合は、骨格的な問題が隠れている可能性があります。骨格性の下顎前突は、遺伝的要因が関係することもありますが、生活習慣や悪癖によっても形成されることがあるため、できるだけ早めの診断が推奨されます。
また、受け口のあるお子さまは、上下の唇を閉じにくく、常に口が開いている“お口ポカン”の状態になっていることもあります。
サイン③ 発音が不明瞭、「サ行」や「タ行」がこもる
受け口によって舌の動きが制限されると、サ行・タ行・ナ行などが滑舌悪く聞こえることがあります。特に「し」「ち」「つ」などの発音がこもって聞こえる場合、前歯の位置が発音に影響している可能性が高いといえます。
「言葉の問題かな?」と思っていたら、実は歯並びや噛み合わせが原因だったというケースも少なくありません。
サイン④ よく噛めない・食事に時間がかかる
受け口のお子さまは、前歯で物をかみ切るのが難しく、奥歯ばかりで噛んでいることがあります。これにより食事に時間がかかったり、しっかり噛めていなかったりすることも。特に硬い食べ物を嫌がる・食べこぼしが多い場合は、噛み合わせに原因があるかもしれません。
咀嚼のアンバランスは消化器への負担や、偏った筋肉の発達につながることもあるため、注意が必要です。
気になるサインがあれば、まずは専門医の診断を
これらのサインはすべて、「今すぐ治療が必要」かどうかを示すものではありません。しかし、適切なタイミングで専門医に診てもらうことで、治療の選択肢を広げることができます。
私たちは、お子さまの成長段階・生活習慣・噛み合わせを総合的に診査し、削らない・痛みの少ないマウスピース型矯正など、成長に合わせた最適な治療プランをご提案しています。
「気になるけれど、様子を見ていた方がいいのかも」——その迷いがある今こそ、相談のベストタイミングです。何もなければそれで安心、必要があれば最小限のアプローチから。まずは一歩、正しい診断からはじめてみませんか?
子どもに伝える矯正の大切さ

子どもの“治す力”を引き出すには
子どもの受け口(下顎前突)の治療を始めようと思ったとき、多くの保護者の方が直面するのが「うちの子、ちゃんと続けられるだろうか?」という不安です。矯正治療は、医師や保護者の判断だけでは完結しません。実際に装置を装着して治療に取り組むのは“お子さま自身”だからです。
治療の成果をしっかり出すためには、お子さまが「なぜ治療が必要なのか」を納得し、前向きに取り組む姿勢を育むことがとても大切です。
「痛いの?」「学校でからかわれる?」子どもの不安を理解する
初めて矯正装置をつけるお子さまは、少なからず不安を抱えています。「痛くないの?」「見た目が恥ずかしい」「友達に何か言われたら嫌だ」——こうした気持ちはとても自然なことです。
大人が「そのうち慣れるから」「綺麗になるためだよ」と簡単に言ってしまうと、子どもは置き去りにされたような気持ちになります。大切なのは、子どもの気持ちに丁寧に寄り添い、共感しながら話すことです。
たとえば、「一緒に頑張ろうね」「もし痛くなったら、すぐに教えてね」など、お子さまの不安を受け止めながら安心感を与えてあげましょう。
親と子の“二人三脚”で進める矯正治療
矯正治療は、装置をつけたからといって勝手に歯が動くわけではありません。治療効果は、装置の使用時間やケアの習慣によって大きく左右されます。
特に取り外し式のマウスピース型矯正装置の場合、お子さま自身が決められた時間きちんと装着できているかどうかが治療の成果に直結します。
そのため、保護者の方の関わり方が非常に重要です。「今日はどれくらい使えた?」「寝る前に一緒に確認しようね」といった声かけや、小さな達成を一緒に喜ぶことで、お子さまの“がんばる気持ち”は自然と育っていきます。
子どもが矯正をポジティブに捉える工夫を
当院では、矯正に対する前向きな気持ちを育むための環境づくりにも力を入れています。お子さま自身が治療内容を理解できるよう、イラストや模型を使って丁寧に説明を行い、「何のために装置をつけるのか」「どうしてこの時期が大切なのか」を自分の言葉で感じてもらえるようサポートします。
また、お子さまの年齢や性格に応じて、「達成シール」や「がんばりカード」などの工夫もご提案。
“矯正=我慢”ではなく、“矯正=自分のためのチャレンジ”という意識に変えていくことが、成功への第一歩です。
矯正を通して、自己肯定感も育てる
矯正治療は、単に歯を動かすだけではありません。「自分で頑張って治した」「前よりもかっこよく・可愛くなった」と感じられる体験は、お子さまの自己肯定感を大きく育てます。
歯並びにコンプレックスを持っていたお子さまが、矯正を経て笑顔に自信を持てるようになったというケースは少なくありません。これは、成長期にある子どもにとって、とても大きな財産になります。
お子さまの“やる気”を育てるのは、周囲の大人の関わり方
私たちは、お子さま一人ひとりの性格やライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる矯正プランをご提案しています。お子さまが治療に前向きに取り組めるよう、保護者の方への声かけ方法のアドバイスや、装置の使い方のサポートもしっかり行っています。
お子さまの受け口治療は、決して本人任せにして良いものではありません。保護者と医療者が手を取り合い、お子さまの気持ちに寄り添いながら治療を進めていくことが、最も大切な要素です。
「うちの子、治療についてどう思ってるかな?」と感じたときは、まずは一緒に話してみてください。そして、迷ったらお気軽に当院へご相談ください。私たちが全力で、お子さまの笑顔と未来をサポートいたします。
治療後の“きれいな歯並び”がもたらす未来

見た目の改善は“心と体の健康”にもつながる
子どもの下顎前突(受け口)治療を考えるとき、多くの親御さまが気にされるのは「見た目が整うかどうか」かもしれません。しかし、矯正治療で得られるのは見た目の変化だけではありません。“きれいな歯並び”は、心と身体の健康、そしてお子さまの将来にまで影響を与える大きな力を持っています。
ここでは、治療後に期待されるさまざまなメリットについてご紹介します。
自分に自信が持てる——笑顔に隠れた「こころ」の成長
受け口のあるお子さまの中には、歯並びやしゃくれた口元が気になり、人前で笑うことをためらったり、写真に写るのを嫌がったりするケースもあります。これは見た目の問題にとどまらず、自己肯定感の低下やコミュニケーションへの消極性にもつながりかねません。
矯正治療によって歯並びや顎のバランスが整うと、見た目の印象が大きく変わります。それと同時に、「自分の口元に自信が持てる」ことで、笑顔が自然と増え、気持ちが明るくなる子どももたくさんいます。
見た目の改善が心の変化を生み出し、学校生活や人間関係にもプラスの影響を与えてくれる——それが、小児矯正の大きな価値のひとつです。
噛み合わせの改善は、身体全体の健康にもつながる
受け口は、見た目の問題だけでなく、咀嚼・発音・姿勢・消化機能などにも悪影響を及ぼします。前歯でうまくかみ切れないことで奥歯に過剰な負担がかかり、歯の摩耗や顎関節のトラブルの原因になることも。
また、噛み合わせがずれていることで、首や肩の筋肉のバランスが崩れ、猫背や偏った姿勢を招くケースも見られます。これは見落とされがちですが、実は全身の骨格発育にも影響を及ぼす重要なポイントです。
正しい噛み合わせを得ることで、これらの問題が解消され、成長期における健全な身体づくりをサポートする効果が期待できます。
歯磨きしやすい環境=虫歯・歯周病リスクの軽減
歯並びが乱れていると、どうしても歯ブラシが届きにくい箇所が生まれ、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。特に受け口のケースでは、下の前歯に強い負担がかかり、歯ぐきが下がる(歯肉退縮)症状を起こすことも。
矯正治療によって清掃性の良い歯列が形成されることで、将来的なトラブルの予防にもつながります。これは、歯の寿命を延ばし、生涯にわたって自分の歯で食べるための基盤づくりでもあるのです。
「成人矯正が不要になる」可能性も広がる
受け口を成長期にしっかり治しておくことで、将来的に本格的な歯列矯正が不要になる、または抜歯を避けて短期間で済む可能性が高まります。
特に当院のように、削らず・痛みに配慮したマウスピース型の機能矯正を採用している場合、骨格の成長誘導によって大人の矯正負担を大幅に軽減できるケースもあります。
つまり、小児期の矯正は、「今のため」だけでなく「将来の自分を守る選択」でもあるのです。
歯並びが整うことで、表情や雰囲気まで変わる
きれいな歯並びとバランスの整った口元は、お子さまの表情に明るさと知性を与え、顔全体の印象をより魅力的に見せる効果があります。
笑顔が増えると、周囲とのコミュニケーションも円滑になり、結果的にお子さまの“人生の選択肢”が広がることにもつながります。
矯正治療を通じて得られるのは、整った歯並びだけではありません。“心・身体・将来”のすべてにプラスの影響をもたらすのが、私たちがご提供する「削らない審美矯正」の大きな特長です。
迷ったときこそ、ぜひご相談ください。お子さま一人ひとりの未来を見据えたご提案を、専門医が丁寧にお話しさせていただきます。
もし“Ⅱ期治療”が必要になったら

Ⅰ期治療だけで終わらないケースもある
子どもの下顎前突(受け口)に対して早期からⅠ期治療を行っていても、すべてのケースがその段階で完了するとは限りません。お子さまの成長や骨格の状態によっては、中高生以降に行う「Ⅱ期治療(本格矯正)」が必要になる場合があります。
「Ⅱ期治療って何をするの?」「抜歯は必要なの?」「痛みはある?」——このような不安を感じる保護者の方のために、ここではⅡ期治療についての基礎知識と、当院がどのような方針で対応しているかをわかりやすく解説します。
Ⅰ期とⅡ期の違いとは?
Ⅰ期治療が「成長を活かして顎のバランスや悪習癖を整える治療」なのに対し、Ⅱ期治療は「永久歯がすべて生えそろったあと、歯を理想的な位置に移動させる治療」です。
つまり、Ⅱ期治療は歯並びの最終調整を行うステージであり、あくまで「仕上げ」の段階。Ⅰ期治療で骨格のコントロールがうまくいっている場合には、Ⅱ期の矯正が短期間・軽度で済むことも多くあります。
しかし、骨格の成長が強く残っていたり、歯の大きさと顎の幅のバランスにズレがある場合には、Ⅱ期でもしっかりとした治療が必要になるケースもあるため、適切な診断が欠かせません。
ブラケット矯正・マウスピース矯正——どんな選択肢があるの?
Ⅱ期治療には大きく分けて2つの方法があります。
-
- ワイヤー(ブラケット)矯正
歯に小さな装置を取りつけ、ワイヤーで力を加えて少しずつ歯を動かす方法。精密なコントロールが可能で、複雑な症例にも対応できます。
- ワイヤー(ブラケット)矯正
- マウスピース型矯正(インビザラインなど)
透明なマウスピースを使用する方法で、目立たず取り外しも可能。軽度~中等度の症例に適しており、近年は子どもや思春期の患者さまにも選ばれることが増えています。
当院では、成長期のお子さまでも使用可能な「ティーン用マウスピース矯正」をご提案しており、本人のライフスタイルやモチベーションに応じて、無理なく続けられる選択肢を一緒に検討します。
抜歯が必要になるのはどんなとき?
矯正治療では、「非抜歯」で進められるかどうかも大きな関心ごとの一つです。歯を抜かずに矯正できるかどうかは、顎の大きさ・歯の大きさ・歯列のスペースなどによって決まります。
Ⅰ期治療を適切に行っていた場合、歯が並ぶスペースを事前に確保できているケースが多く、Ⅱ期でも非抜歯で治療を完了できる可能性が高まります。
ただし、どうしてもスペースが足りない場合や、歯のねじれが大きいケースでは、専門医が総合的に判断し、抜歯の要否を丁寧にご説明いたします。もちろん、いきなり抜歯を提案するようなことは決してありませんので、ご安心ください。
Ⅱ期治療をスムーズに進めるために
Ⅱ期治療は、中学生〜高校生と多忙な時期に差しかかるため、本人の理解とモチベーションの維持がとても重要です。治療の必要性をしっかり説明し、本人が納得したうえでスタートすることが、治療の成功につながります。
当院では、お子さまとのコミュニケーションを大切にし、「なぜ今、治療をするのか」「どうすれば早く終わるか」といった治療の目的をしっかり共有することを心がけています。
“治療のゴール”は美しさと健康を両立すること
Ⅱ期治療の目的は、単に歯をまっすぐ並べることではありません。しっかり噛める、話せる、笑えるという機能と美しさの両立がゴールです。
また、歯並びや噛み合わせが整うことで、将来の虫歯・歯周病・顎関節症の予防にもつながり、長い人生を健康な口元で過ごすための土台を作ることができます。
もし「Ⅱ期治療が必要になるかもしれない」と言われたら、それはネガティブな話ではなく、お子さまの将来をより良くするための大切なステップです。
松本デンタルオフィス for キッズでは、削らない・痛みに配慮した矯正治療で、お子さまの未来をしっかりサポートいたします。次のステップに進むかどうか、一緒にじっくり考えてみませんか?
親として知っておきたい、虫歯・歯みがきのポイント

矯正中は「むし歯予防」も同じくらい重要
矯正治療中の子どもにとって、歯並びを整えることと同じくらい重要なのが「むし歯予防」や「正しい歯みがき」です。
どれほど良い矯正をしても、治療の途中で虫歯になってしまえば中断が必要になったり、装置の交換や処置が必要になったりと、お子さまにとっても大きな負担になってしまいます。
ここでは、親御さんが知っておきたい“矯正中に注意したいお口のケア”についてわかりやすく解説いたします。
矯正中は虫歯ができやすい?その理由とは
矯正治療では、歯に装置を装着したり、マウスピースを長時間つけることが多いため、どうしても汚れがたまりやすくなる傾向があります。
特にワイヤー矯正の場合、歯ブラシが届きにくい部分にプラーク(歯垢)が残りやすく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
マウスピース矯正でも、装着したままおやつを食べてしまう、毎回しっかり磨かずに装着するといった使い方をしてしまうと、むし歯リスクは急上昇します。
つまり、矯正中こそ“予防ケアを強化すべき時期”なのです。
フッ素塗布・シーラント処置の活用を
当院では、矯正中のお子さまに対し、定期的なフッ素塗布や、奥歯の溝を埋めるシーラント処置など、むし歯予防に有効な対策を積極的にご提案しています。
フッ素は歯の再石灰化を促し、むし歯菌の活動を抑える効果があるため、矯正によって清掃性が落ちがちな時期にとって強い味方になります。
シーラントは特に乳歯や生えたての永久歯の奥歯に適応される処置で、むし歯になりやすい溝をあらかじめ保護する役割を担います。
矯正治療と並行して、こうした予防処置を取り入れることで、むし歯リスクを大幅に低下させることができます。
毎日の歯みがきを“仕組み化”する
矯正治療中は、普段以上に「丁寧な歯みがき習慣」を身につけることが必要です。
- マウスピースを外したら必ず歯みがきをしてから再装着
- 夜の仕上げ磨きは必ず保護者がチェック
- 歯ブラシだけでなく、デンタルフロスやタフトブラシを活用
このように、家庭でも「決まった流れ」を作ることで、習慣化しやすくなります。特に小学校低学年くらいまでは、自分でしっかり磨くことが難しいため、親御さんの手助けがとても大切です。
「毎日続けることが苦手」「忘れやすい」というお子さまには、カレンダーにシールを貼る、がんばり表を使うといった“見える工夫”も効果的です。
定期メンテナンスでプロのチェックを
当院では、矯正治療中も定期的なメンテナンス・クリーニングをおすすめしています。歯科衛生士によるプロフェッショナルケアは、見逃しがちな磨き残しをチェックできるだけでなく、お子さまがモチベーションを保つためにも有効です。
「ここがよく磨けていたね」「ここの部分はもう少し意識しようか」など、褒めて伸ばすアドバイスを心がけています。
また、歯ぐきの炎症や初期むし歯など、自覚症状のないトラブルを早期に発見できることも、プロのメンテナンスの大きなメリットです。
矯正中だからこそ、口腔内の健康意識を高める好機に
矯正治療は、単に歯並びを整えるだけではなく、正しいケア習慣や予防の意識を育てる絶好のチャンスでもあります。
この時期にしっかりとした歯みがき習慣を身につけておくことで、大人になってからも口腔内の健康を保ちやすくなります。
「歯並びがきれいになること」と「むし歯にならないこと」は、どちらも大切なお口の健康の柱です。
私たち松本デンタルオフィス for キッズは、矯正治療と並行して、予防歯科の視点からもお子さまをサポートいたします。
迷ったら、まずは相談から

「うちの子、受け口かも?」そう思ったときの第一歩
「うちの子、受け口かもしれない」「いつ治療を始めたらいいんだろう?」——そんな風に感じたとき、すぐに治療を始めなければいけないわけではありません。
大切なのは、“今の状態を正しく知る”こと、そして“いつ・どのように治療すべきか”を専門家と一緒に考えることです。
治療を前提としない「相談だけ」のご来院も歓迎
私たち松本デンタルオフィス for キッズでは、治療を前提にしない相談だけのご来院も大歓迎です。
受け口はタイミングによっては自然に改善する場合もあり、すぐに治療が必要とは限りません。
「治療するかどうかは、診てもらってから決められる」安心感
矯正相談というと、「無理に治療を勧められるのでは?」と不安に思われる方も少なくありません。
しかし、当院ではご本人・保護者のご希望を第一に尊重し、十分な説明と同意(インフォームド・コンセント)のもとで診療を進めています。
実際に初診相談の場では、
- 現在の歯並びや噛み合わせの状態
- 顎の成長バランス
- 癖(舌の位置、口呼吸、姿勢)などの影響
- 治療が必要な場合と、経過観察で問題ない場合の違い
といった点を、丁寧な診査・写真撮影・模型分析などを通じて把握し、わかりやすくご説明いたします。
そのうえで、「今すぐ治療しましょう」とお伝えすることはほとんどなく、「〇歳頃から始めた方がよさそうですね」「半年ごとに様子を見ましょう」といったご提案になるケースも多いのが実情です。
初診カウンセリングの流れと所要時間
当院では、初めての方でもリラックスしてご相談いただけるよう、矯正専用のカウンセリングシステムを整えています。
- 受付・問診票の記入(お悩みやご希望を伺います)
- 簡単なお口のチェックとお写真撮影
- 専門医による診断と、治療の必要性の有無を説明
- 質疑応答、今後のスケジュールのご案内
所要時間は30~45分程度。完全予約制で、じっくりお話しできる時間を確保しています。
お子さまにも理解できるよう、専門用語を使わず、模型や画像を使って楽しく説明することを心がけていますので、ご安心ください。
「まだ早い?」「もう遅い?」と迷ったら——それが相談のタイミング
矯正治療には“今しかできないこと”がある一方、“今はまだやらなくていいこと”もあります。
だからこそ、自己判断せず、専門的な視点で診てもらうことが重要です。
実際、「もっと早く来ればよかった」「こんなに丁寧に説明してくれるとは思わなかった」といったお声も多くいただいています。
私たちは、ただ歯を並べるのではなく、お子さまが自信を持って笑える未来を一緒につくることを目指しています。
矯正治療を迷っている今こそ、その第一歩を踏み出すチャンスです。
「削らずに整える」マウスピース矯正で、お子さまの未来を守る治療を
では、歯を削らず、できるだけ抜歯も避け、成長に寄り添った“やさしい矯正”を行っています。
マウスピース型装置を用いた治療は、お子さまにも負担が少なく、見た目にも配慮された現代的な矯正方法として注目されています。
受け口は、気づいた今がチャンスです。迷ったままにせず、まずはお気軽に初回相談へお越しください。
私たちが、あなたとお子さまの未来をサポートいたします。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより