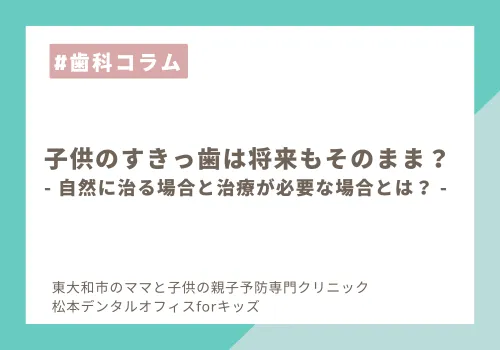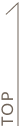こんにちは。松本デンタルオフィスforキッズです。
お子さんの前歯に隙間があるのを見て、「このまま大人になってもすきっ歯のままなのかな?」「歯並びに影響しないの?」と気になったことはありませんか?
乳歯の時期はすきっ歯が自然な状態のこともありますが、成長過程で注意が必要なケースもあります。すきっ歯の原因は 顎の成長と歯の大きさのバランス や 指しゃぶり・口呼吸などの生活習慣 によるものなどさまざま。放置すると、将来的に 噛み合わせの悪化や発音の問題 につながることもあります。
今回は、「子どものすきっ歯とは原因とは?」「治療が必要なケースは?」 といった疑問にお答えしながら、お子さんの歯並びを健康に保つためのポイントを解説していきます。
1.こんなお悩みありませんか?

お子様の歯並びを見て、「前歯に隙間があるけれど、このままで大丈夫?」「成長してもこの隙間は残ってしまうの?」と不安に感じたことはありませんか?実は、お子様の歯のすき間(空隙歯列)には、自然に解消するケースと矯正が必要なケースがあります。まずは、お子様のすきっ歯の原因や今後の影響を知ることが大切です。
✅ 前歯の隙間が気になるけれど、このまま放っておいていいのかわからない
✅ 乳歯のときは問題なかったのに、最近すきっ歯が目立つようになってきた
✅ すきっ歯がこのまま残ると、将来の歯並びや噛み合わせに影響しないか心配
お子様の歯並びは成長とともに変化しますが、どのタイミングで経過を見守るべきか、または治療を検討すべきかを正しく判断することが大切です。
2.子供のすきっ歯(空隙歯列)とは?

お子様の歯と歯の間に隙間があると、「このまま大人になっても歯並びが悪くならないか?」と不安に思われる親御様もいらっしゃるかと思います。しかし、子供のすきっ歯は成長の過程で自然に見られるものであり、すぐに矯正治療が必要なわけではありません。
空隙歯列とは?
歯と歯の間に隙間がある状態を空隙歯列(くうげきしれつ)と呼びます。特に子供の場合、乳歯は永久歯よりも小さいため、歯と歯の間に余裕が生じやすくなります。これは、将来的に永久歯が正しく生えてくるためのスペースを確保する自然な現象であり、多くの場合、特別な処置をしなくても自然に隙間が埋まります。
乳歯と永久歯の生え変わりと隙間の変化
子供の歯は、乳歯から永久歯へと徐々に入れ替わる過程で大きな変化を迎えます。その際、すきっ歯がどのように変わっていくのかを知ることが大切です。
乳歯期のすきっ歯(発育空隙)
✅ 乳歯列の時期に見られる隙間は自然な成長過程の一部
✅ 将来、永久歯が適切な位置に生えるために隙間がある方が良いこともある
✅ 発育空隙(はついくくうげき): 永久歯がスムーズに生えてくるために必要なスペース
✅ 霊長空隙(れいちょうくうげき): 上の犬歯の前、下の犬歯の後ろにできる隙間で、成長とともに消失することが多い
永久歯期のすきっ歯
✅ 永久歯が生えそろう過程で隙間が徐々に埋まることが多い
✅ 顎の成長具合と歯の大きさのバランスによって、隙間が残ることもある
✅ 指しゃぶりや舌の癖があると、前歯に隙間ができやすくなる
子供に見られる代表的なすきっ歯のタイプ
お子様のすきっ歯は、成長の段階や生活習慣によって異なる特徴を持ちます。以下は、よく見られるすきっ歯の種類です。
① 乳歯の生え変わり期に見られる隙間
➡ 乳歯の間にできる隙間は永久歯のための準備段階
➡ ほとんどの場合、自然に埋まるため、特別な治療は不要
➡ 永久歯が生えることで、歯並びが整うことが多い
② 前歯の隙間(上唇小帯の影響)
➡ 上唇と歯ぐきをつなぐ「上唇小帯(じょうしんしょうたい)」が太いと、前歯の間に隙間ができることがある
➡ 自然に治るケースもあるが、改善しない場合は処置が必要
③ 顎の成長と歯のサイズの違いによるすきっ歯
➡ 顎の発育が良く、歯が小さいと、永久歯が生えそろっても隙間が残ることがある
➡ この場合は自然に治らず、矯正治療が検討されることも
④ 指しゃぶりや舌の癖によるすきっ歯
➡ 指しゃぶりや舌で歯を押す癖が続くと、前歯が外側に押し出されて隙間が広がる
➡ 長期間続くと、噛み合わせ全体に影響を与える可能性がある
➡ まずは習慣を改善することが大切
子供のすきっ歯は成長の一部として自然に見られるもので、多くの場合は永久歯が生えてくることで改善されます。しかし、顎の大きさや歯のサイズのバランスが悪い場合や、指しゃぶり・舌のクセが影響している場合は、自然に治らないこともあります。「この隙間は放っておいて大丈夫なのか?」「治療が必要か判断がつかない」といったお悩みがある場合は、まずは歯科医師に相談することが大切です。 定期的なチェックを行うことで、お子様にとって最適な対応を見極めることができます。
3.乳歯のすきっ歯は問題ない?成長空隙について

お子様の歯に隙間があると、「このまま大人になっても隙間が残るのでは?」と心配される親御様も多いかもしれません。しかし、乳歯の時期のすきっ歯は成長の一環としてよく見られる現象であり、すぐに問題になるわけではありません。
発育空隙とは?正常なすきっ歯の仕組み
乳歯の時期に見られるすきっ歯は「発育空隙(成長空隙)」とも呼ばれ、永久歯が正しく生えてくるために必要なスペースです。
✅ どうしてすきっ歯になるの?
➡ 乳歯は永久歯よりも小さいため、永久歯が生えるためのスペースを確保するために自然と隙間ができることがあります。
✅ どの時期に見られやすいの?
➡ 4歳~6歳頃に、特に前歯(上の前歯・下の前歯)の隙間が目立つことが多いです。
✅ いつ頃隙間が埋まるの?
➡ 永久歯が生え揃うにつれて、自然と隙間がなくなっていくことがほとんどです。
➡ 6歳~7歳頃に前歯の永久歯が生え始めると、徐々に歯と歯の間の隙間が狭まります。
乳歯のすきっ歯と永久歯の生え変わりの関係
乳歯に隙間があること自体は心配する必要はありません。むしろ、永久歯が適切に並ぶためには、ある程度の隙間が必要です。
🔹 乳歯の時期に隙間がないとどうなるの?
➡ 乳歯の歯並びがピッタリと詰まっている場合、永久歯が生えてくるスペースが足りず、歯並びが乱れる原因になることがあります。
🔹 成長とともに自然に隙間が埋まる?
➡ ほとんどの場合、永久歯が生えてくると隙間が閉じていきます。
➡ ただし、顎の大きさや歯のサイズのバランスによっては、永久歯になっても隙間が残るケースもあります。
経過観察で問題ないケースと注意が必要なケース
経過観察で問題ないケース
✔ 乳歯の時期に隙間が見られるが、特に異常がない場合
✔ 顎の成長が順調で、永久歯が正しく生えるスペースが確保されている場合
✔ 6歳以降、前歯の永久歯が生え始めるにつれて隙間が徐々に狭くなってきた場合
注意が必要なケース
⚠ 前歯の隙間が大きすぎる(2~3mm以上)
⚠ 7~8歳になっても隙間が埋まらない
⚠ 舌で前歯を押す癖や口呼吸が原因で歯並びに影響が出ている
⚠ 永久歯が生えそろっても隙間が目立つ(空隙歯列の傾向)
このような場合は、自然に改善しないことがあるため、歯科医院で相談するのが安心です。
乳歯のすきっ歯は永久歯が生えてくるために必要なスペースとしてよく見られる現象です。多くの場合、成長とともに改善するため心配はいりませんが、隙間が大きすぎる場合や、永久歯が生えそろっても改善しない場合は、矯正治療が必要になることもあります。
4.治療が必要なすきっ歯とは?

お子様のすきっ歯(空隙歯列)は、多くの場合、成長とともに自然に改善されることがほとんどですが、すべてのケースがそうとは限りません。特に、特定の原因によってすきっ歯が生じている場合は、放置すると歯並びや噛み合わせに影響を及ぼす可能性があります。
正中離開(前歯の真ん中に隙間がある状態)
正中離開(せいちゅうりかい)とは、上の前歯の中央に大きな隙間ができている状態を指します。
✔ よくあるケース
- 小さい頃は自然に見られることが多いが、永久歯が生えそろっても隙間が埋まらない場合がある
- 隙間が大きく、発音に影響を与えることもある
- 見た目が気になることで、お子様が口元を隠してしまうことがある
✔ 治療が必要になるケース
- 永久歯が生えそろっても隙間が目立つ場合
- 発音に影響が出る場合(特に「サ行」が発音しにくい)
- 噛み合わせに問題が出てくる場合
✔ 治療方法
- 軽度の場合は経過観察を続け、自然に埋まるか確認
- 隙間が大きい場合や発音に影響が出る場合は、矯正治療を検討
上唇小帯の異常によるすきっ歯
上唇小帯(じょうしんしょうたい)とは、上唇と歯ぐきをつないでいる筋(すじ)のことです。通常、この筋は成長とともに薄くなりますが、異常があると前歯の隙間が閉じにくくなることがあります。
✔ 上唇小帯異常が原因の特徴
- 上唇をめくると、前歯の間まで小帯が入り込んでいる
- 永久歯が生えても前歯の隙間が埋まらない
- 笑ったときに歯ぐきが強く引っ張られて違和感がある
✔ 治療が必要になるケース
- 前歯の隙間が埋まらず、見た目や機能に影響がある場合
- 上唇の動きに違和感がある場合
✔ 治療方法
- 成長によって自然に改善する場合もあるため、まずは経過観察
- 隙間が大きく閉じない場合は、矯正治療とあわせて小帯の切除手術を検討(簡単な処置で、痛みも少ない)
過剰歯や欠損歯が原因のケース
過剰歯(かじょうし)とは、通常よりも多く歯が生えてしまう状態を指します。逆に欠損歯(けっそんし)とは、生まれつき歯の本数が少ない状態です。どちらのケースも、前歯のすきっ歯を引き起こすことがあります。
① 過剰歯によるすきっ歯
✔ 過剰歯があるとどうなる?
- 前歯の間に余分な歯があることで、永久歯が正しい位置に生えにくくなる
- 正中離開(前歯の隙間)が埋まりにくくなる
- 噛み合わせに影響が出ることがある
✔ 治療方法
- 過剰歯が前歯のすきっ歯の原因になっている場合は抜歯を検討
- 永久歯の位置を正しく整えるために矯正治療を行うこともある
② 先天性欠損歯(生まれつき歯が足りない)によるすきっ歯
✔ 先天性欠損歯があるとどうなる?
- 永久歯が生えてこないため、その部分に隙間ができる
- 周りの歯が動いてしまい、歯並びが乱れる
- 噛み合わせのバランスが崩れる
✔ 治療方法
- 軽度の場合 → 矯正治療で周囲の歯を移動させ、自然な歯並びに調整
- 歯の欠損が大きい場合 → 矯正治療後に義歯やインプラントなどで補う
お子様のすきっ歯は、多くの場合、成長とともに自然に改善されます。しかし、正中離開や上唇小帯の異常、過剰歯や欠損歯などが原因の場合は、適切な治療が必要になることもあります。
5.すきっ歯を放置するとどうなる?

お子様のすきっ歯は成長とともに改善することが多いですが、原因によっては放置することで歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす場合があります。見た目の問題だけでなく、発音や食事のしやすさ、将来的な歯並びにも影響を与える可能性があるため、気になる場合は早めに歯科医院で相談することをおすすめします。
見た目の問題(コンプレックスになる可能性)
すきっ歯が目立つと、お子様が気にしてしまうことがあります。
✔ こんな影響が出ることも
- 笑うときに口元を隠すようになる
- 周囲の目を気にして積極的に話せなくなる
- 友達に指摘されて自信をなくしてしまう
特に小学生や中学生になると、歯並びを気にするお子様が増えてきます。コンプレックスを感じてしまう前に、適切なアドバイスや治療を受けることが大切です。
発音障害や食べ物の噛みにくさ
歯と歯の間に大きな隙間があると、発音や食事に影響が出ることがあります。
✔ 発音への影響
- 「サ行」や「タ行」が発音しづらくなる
- 息が抜けてうまく話せないことがある
- うまく発音できないことで会話に自信をなくしてしまう
✔ 食事のしづらさ
- すきっ歯があると、前歯で食べ物を噛み切りにくい
- 食べ物が歯の間に詰まりやすくなる
- しっかり噛めないことで、消化に負担がかかる
発音や食事に影響が出ると、学校生活にも影響を及ぼす可能性があるため、改善が必要かどうかを確認することが重要です。
将来的な歯並びや噛み合わせへの影響
すきっ歯を放置すると、永久歯の生え方や噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。
✔ 放置すると起こり得るリスク
- 隣の歯が傾いてしまい、歯並びが乱れる
- 隙間があることで奥歯の噛み合わせに影響が出る
- 永久歯が正しい位置に生えてこない可能性がある
歯並びが乱れると、将来的に矯正治療が必要になるケースもあります。 すきっ歯が自然に治るのか、それとも治療が必要なのかをしっかり見極めることが大切です。
すきっ歯は、成長とともに自然に改善するケースもありますが、原因によっては放置すると歯並びや噛み合わせ、発音、食事に影響を与えることがあります。
6.すきっ歯の矯正治療のタイミング

お子様のすきっ歯が気になったとき、「今すぐ治療したほうがいいのか、それとも様子を見たほうがいいのか」と悩まれる親御様も多いのではないでしょうか? すきっ歯の治療は、歯の生え変わりや顎の成長を考慮して適切なタイミングで行うことが大切です。
乳歯の段階での対応が必要な場合
乳歯の時期のすきっ歯は、多くの場合、永久歯への生え変わりとともに自然に改善します。しかし、以下のようなケースでは、早めに歯科医院で診てもらうことをおすすめします。
✔ 早期の対応が必要なケース
- 上唇小帯の異常(前歯の間にある筋が太く、隙間が閉じない)
- 過剰歯の存在(余分な歯が生えて、歯の位置を邪魔している)
- 指しゃぶりや舌の癖による影響(歯が外側に押し出され、隙間が広がる)
これらの原因がある場合は、適切なタイミングで治療を開始することで、将来の歯並びへの影響を防ぐことができます。
永久歯が生え揃うまで経過観察するケース
乳歯のすきっ歯が気になる場合でも、永久歯が生え揃うまで経過観察することが適しているケースもあります。
✔ 経過観察が適しているケース
- 発育空隙(乳歯の時期に見られる自然なすきっ歯)
- まだ永久歯が生え揃っていない状態
- 顎の成長が不十分で、今後の変化が見込まれる
特に、前歯のすきっ歯は、犬歯(糸切り歯)が生えてくることで自然に閉じることが多いため、慌てて矯正を始める必要がないこともあります。歯の生え変わりのスピードや顎の成長を考慮し、適切なタイミングを見極めることが重要です。
6歳〜10歳ごろの治療の選択肢
小学校低学年〜中学年(6歳〜10歳頃)は、矯正治療を始めるのに適した時期です。
✔ この時期に治療を検討すべきケース
- すきっ歯の程度が大きく、自然に閉じる見込みがない
- 噛み合わせに問題がある(開咬や過蓋咬合など)
- 顎の成長をコントロールしたほうがよいと判断された場合
この時期の矯正治療は「第1期治療」と呼ばれ、顎の成長をコントロールしながら、歯が正しく並ぶためのスペースを確保することを目的としています。
6歳〜10歳頃に選択できる治療方法
✅ プレート型の矯正装置(床矯正)
- 顎の成長を促し、歯が並ぶスペースを確保する
- 取り外しができるため、食事や歯磨きがしやすい
✅ マウスピース型矯正(インビザライン・ファースト)
- 目立ちにくく、子どもも抵抗なく装着できる
- 歯を動かしながらスペースを確保する治療が可能
✅ ワイヤー矯正
- すきっ歯が広範囲にわたる場合に適用
- 治療効果が安定しやすい
この時期に適切な矯正治療を行うことで、将来的な歯並びの乱れを最小限に抑えられます。 矯正が必要かどうかは、歯科医院での診断を受けることで判断できます。
すきっ歯の治療を始める前に大切なこと
矯正治療を検討する際には、「本当に治療が必要なのか?」を見極めることが大切です。
🔹 まずは歯科医院で相談する
- 「このすきっ歯は自然に治るのか?」
- 「矯正治療が必要なのか?」
- 「どの治療法が適しているのか?」
これらの疑問は、専門家の診断を受けることで解決できます。
🔹 生活習慣の見直しも大切
- 口呼吸をしていないか?
- 指しゃぶりや舌の癖がないか?
- しっかり噛む習慣がついているか?
日常の習慣を改善することで、すきっ歯の進行を防ぐことも可能です。
すきっ歯の治療タイミングは、お子様の成長や歯の生え変わりの状況によって異なります。
7.すきっ歯の治療方法

お子様のすきっ歯が気になる場合、どのような治療法があるのか気になる方も多いでしょう。すきっ歯の状態や原因によって、適した治療方法は異なります。
マウスピース矯正(インビザライン・ファーストなど)
最近、子供向けのマウスピース矯正が注目されています。その中でも「インビザライン・ファースト」は、小児矯正向けの透明なマウスピース矯正で、すきっ歯の改善にも効果が期待できます。
🔹 マウスピース矯正の特徴
- 透明で目立たない:矯正装置が目立つのが嫌なお子様でも安心
- 取り外しができる:食事や歯磨きの際に取り外せるので衛生的
- 痛みが少ない:ワイヤー矯正よりも歯への負担が少ない
🔹 適応するケース
- 軽度〜中程度のすきっ歯
- 顎の成長を利用しながらスペースを確保する必要がある場合
- 指しゃぶりや舌の癖による歯列の乱れを改善する場合
マウスピース矯正はお子様自身が装置をきちんと装着することが重要です。1日20時間以上の装着が推奨されているため、装着時間を守れるお子様に向いています。
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正は、歯並び全体を細かく調整できるため、すきっ歯の治療に効果的です。
🔹 ワイヤー矯正の特徴
- さまざまな歯並びの問題に対応可能:すきっ歯だけでなく、噛み合わせの問題も改善できる
- 歯を動かす力が強い:短期間で効果が出やすい
- 装着時間の管理が不要:取り外し式ではないため、装着忘れの心配がない
🔹 適応するケース
- すきっ歯の隙間が大きい場合
- 顎の成長による影響が少ない年齢(10歳前後〜)
- マウスピース矯正では対応が難しい歯並び
ワイヤー矯正は、装置が固定されているため、食べ物が挟まりやすく、歯磨きをしっかり行う必要があります。親御様のサポートが重要になります。
矯正前に必要な処置(過剰歯の抜歯、小帯の処置など)
すきっ歯の原因によっては、矯正治療を始める前に必要な処置があります。
✅ 過剰歯の抜歯
過剰歯とは、本来生えてこないはずの余分な歯のことです。過剰歯が原因ですきっ歯になっている場合、矯正治療の前に抜歯が必要になります。
🔹 過剰歯による影響
- 歯が正しい位置に並ばない
- 永久歯の生え方に影響を与える
- 正中離開(前歯の真ん中に大きな隙間ができる)
矯正治療と並行して、必要な抜歯を行うことで、歯並びの改善がスムーズになります。
✅ 上唇小帯の切除
上唇小帯(じょうしんしょうたい)とは、上唇の裏側にある筋(スジ)のことです。この部分が厚かったり、位置が低かったりすると、前歯の隙間(正中離開)が閉じにくくなります。
🔹 上唇小帯の影響
- 前歯の間に隙間ができる
- 矯正治療後に後戻りしやすくなる
- 上唇が動きにくく、発音に影響が出ることもある
矯正治療を始める前に、この小帯の切除を行うことで、すきっ歯が改善しやすくなるケースがあります。
お子様のすきっ歯は、成長とともに自然に閉じることもありますが、原因によっては早めの対応が必要になるケースもあります。
8.すきっ歯を予防するための習慣

お子様のすきっ歯を防ぐためには、歯の成長を正しくサポートする生活習慣が大切です。すきっ歯の原因には、遺伝だけでなく、舌の使い方や口の閉じ方、呼吸の仕方なども関係しています。日常のちょっとした習慣を見直すことで、将来の歯並びをより良く保つことができます。
正しい舌の使い方・口の閉じ方を意識する
舌の位置や口の閉じ方が適切でないと、歯並びに影響を与え、すきっ歯の原因になることがあります。お子様が普段どのように口を閉じ、舌を動かしているかをチェックしてみましょう。
✅ 正しい舌の位置
- 何もしていないとき、舌は上あご(口蓋)に軽く触れているのが正しい状態
- 口を開けたまま舌が下がっていると、歯が前に押し出されてすきっ歯になる可能性がある
✅ 正しい口の閉じ方
- 唇を軽く閉じ、無理に力を入れずに自然な状態にする
- 口を開けたままの状態が多い場合は、口周りの筋肉が弱くなり、歯並びが乱れる原因になる
👀 親御様がチェック!
「お子様がリラックスしているときに、口が開いていないか」「舌が下がっていないか」を観察してみてください。意識的に舌を正しい位置に持っていく習慣をつけることで、歯並びの安定につながります。
口呼吸を防ぐためのトレーニング
お口をポカンと開けたままの状態が続くと、口の周りの筋肉が衰え、歯並びに影響を与えることがあります。特に口呼吸が習慣化すると、舌の位置が下がり、すきっ歯や出っ歯の原因になりやすいです。
✅ 口呼吸のデメリット
- 口周りの筋肉が弱まり、歯を支える力が低下
- 舌が下がることで、前歯が押し出されすきっ歯になりやすい
- 口が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが上がる
✅ 口呼吸を改善するトレーニング
- あいうべ体操(舌や口の筋肉を鍛える)
① 「あー」と口を大きく開ける
② 「いー」と口を横に広げる
③ 「うー」と口を前に突き出す
④ 「べー」と舌を思い切り出す - 口を閉じる練習(唇の筋肉を鍛える)
- ガムを噛みながら唇をしっかり閉じる
- 飲み物を飲むときにストローを使わず、コップからしっかり吸うように飲む
お子様が無意識のうちに口呼吸になっていないか、日常生活の中で意識してみることが大切です。
親御様が気をつける生活習慣のポイント
お子様のすきっ歯を防ぐために、親御様が気をつけるべきポイントをまとめました。
✅ 食事の習慣を見直す
- 硬いものをよく噛んで食べる習慣をつける(例:根菜類、ナッツ、せんべいなど)
- 片側だけで噛まず、両側の歯をバランスよく使う
✅ 指しゃぶりや頬杖のクセをなくす
- 指しゃぶりが長引くと、歯並びに影響を与える可能性がある
- 頬杖をつくと、片側の歯や顎に圧力がかかり、歯の位置がずれることがある
✅ 寝るときの姿勢をチェック
- うつ伏せ寝や横向き寝を続けると、顎に負担がかかり、歯並びが乱れやすくなる
- 仰向けで寝る習慣をつけることで、顎のバランスを整える
✅ フッ素や歯磨き習慣を徹底
- すきっ歯があると、歯と歯の間に食べ物が詰まりやすく、虫歯リスクが高まる
- フッ素入りの歯磨き粉を使い、歯の間も丁寧に磨く
お子様のすきっ歯を防ぐためには、成長に合わせた適切なケアが必要です。
特に小さいうちは、親御様のサポートが大きなカギになります。「いつの間にかすきっ歯になっていた…」と後悔しないためにも、早めに生活習慣を見直し、歯の健康を守る習慣をつけていきましょう。
9.すきっ歯と全身の健康の関係

お子様のすきっ歯(空隙歯列)は見た目の問題だけではなく、全身の健康や発育にも影響を与えることがあります。 噛み合わせが悪いと、食べ物をうまく噛めなかったり、正しい呼吸ができなくなったりすることがあります。その結果、姿勢や発音、さらには脳の発達にも影響を及ぼすことがあるのです。
正しい噛み合わせが姿勢や発育に与える影響
噛み合わせが悪いと、全身のバランスが崩れ、姿勢にも影響を及ぼします。
✅ 噛み合わせと姿勢の関係
- 歯並びが悪いと顎のバランスが崩れ、猫背になりやすい
- 噛む力が左右で偏ると、首や肩のこりにつながる
- 噛み合わせが悪いと顎関節に負担がかかり、頭痛や顎の痛みを引き起こすことも
お子様の歯並びが整っていないと、食事中にしっかり噛むことが難しくなり、顎の成長や発育に影響を与えます。正しい噛み合わせを形成することは、健康な体作りの第一歩です。
歯並びと呼吸機能(口呼吸・いびき)の関係
歯並びが悪いと、口を閉じるのが難しくなり、口呼吸の習慣がついてしまうことがあります。
✅ 口呼吸がもたらす影響
- 口の中が乾燥し、虫歯や歯周病のリスクが上がる
- 喉の粘膜が乾燥し、風邪をひきやすくなる
- いびきや睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まる
本来、人間は鼻で呼吸をするのが理想的です。しかし、すきっ歯や顎の成長不足により、口が閉じにくいと自然と口呼吸の習慣がついてしまいます。 口呼吸が続くと、舌の位置が下がり、さらに歯並びが悪化するという悪循環に陥ることもあります。
このような問題を防ぐためには、歯並びだけでなく、お子様の呼吸習慣にも目を向けることが大切です。 すきっ歯が気になる場合は、噛み合わせだけでなく、お子様が口をしっかり閉じて鼻呼吸ができているかもチェックしてみましょう。
噛む習慣が脳の発達に与える影響
「よく噛んで食べること」は、お子様の脳の発達にも大きな影響を与えます。
✅ 噛むことで期待できる効果
- 脳への血流が増え、集中力や記憶力がアップ
- 顎の発達が促進され、歯並びが整いやすくなる
- 食べ物をしっかり噛むことで、消化がスムーズになり、栄養の吸収率がアップ
近年、「柔らかい食べ物」が増えたことで、しっかり噛む習慣が減っているお子様が増えています。 その結果、顎の発達が不十分になり、歯並びの乱れや噛み合わせの問題につながることがあります。
また、噛むことは脳への刺激となり、集中力や思考力の向上にもつながることが研究でも明らかになっています。お子様のすきっ歯を改善し、噛む力を鍛えることは、学習能力の向上にもつながる可能性があるのです。
すきっ歯は見た目の問題だけではなく、姿勢・呼吸・脳の発達にも影響を与える可能性があります。
10.子供のすきっ歯に関するよくある質問

お子様のすきっ歯について、多くの親御様から寄せられる質問にお答えします。お子様の歯並びは成長とともに変化するため、適切なタイミングでの対応が大切です。
Q1.すきっ歯は自然に治ることもある?
A1.お子様のすきっ歯は、成長の過程で自然に改善する場合もありますが、すべてのケースで放置して大丈夫というわけではありません。
🔹 自然に治るケース
- 乳歯期の「発育空隙」(生え変わりのためのスペース)は問題なし
- 永久歯が生えそろうと、自然に隙間が埋まることがある
🔹 注意が必要なケース
- 前歯の間が大きく開いている(正中離開)
- 上唇小帯が太く、歯の間に入り込んでいる
- 過剰歯や歯の先天的欠損による隙間
乳歯の段階では問題がなくても、永久歯の生え変わりの時期に確認が必要です。 すきっ歯が気になる場合は、一度歯科医に相談してみましょう。
Q2.何歳までに矯正を始めるべき?
A2.矯正治療の開始時期は、お子様の成長段階によって異なります。
📌 すきっ歯の矯正を始める目安
- 6〜8歳頃:前歯の隙間が目立つ場合、この時期にチェック
- 8〜10歳頃:歯並びや噛み合わせの異常が出やすい時期
- 10歳以降:本格的な矯正治療を考えるタイミング
🔹 乳歯の段階では、経過観察が基本
- 自然に改善する可能性が高いので、定期的なチェックが大切
🔹 永久歯が生え始めたら相談を
- 隙間が広く、自然に埋まりそうにない場合は、矯正を検討
矯正を始めるベストなタイミングは個人差があるため、気になったら早めに歯科でチェックしてもらいましょう。
Q3.すきっ歯の矯正は痛みがあるの?
A3.矯正治療の痛みは、装置の種類やお子様の歯の状態によって異なります。
🔹 マウスピース矯正(インビザライン・ファースト)
- 透明なマウスピースを使い、違和感が少ない
- 徐々に歯を動かすため、痛みは比較的少ない
🔹 ワイヤー矯正
- 初めて装着したときや、調整後に軽い痛みを感じることがある
- 1〜2日で慣れるケースが多い
💡 痛みを軽減する方法
- やわらかい食べ物を選ぶ(硬いものを無理に噛まない)
- 装置に慣れるまで少しずつ噛む練習をする
- 歯科医師の指示に従い、適切な調整を行う
矯正治療は、お子様の成長を利用して進めるため、大人よりもスムーズに歯が動きやすい特徴があります。痛みが心配な場合は、負担の少ない治療方法を選ぶことも可能ですので、気軽にご相談ください。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより