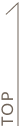1. 「うちの子、そろそろ歯医者さんデビュー?」と悩んだら

・「いつから行くべき?」と迷う保護者の声
「子供の定期検診って、何歳から通い始めればいいんですか?」というご相談は、小児歯科でよく聞かれる質問のひとつです。特に初めて育児を経験されている保護者の方にとって、子供をいつ小児歯科に連れて行けばよいのかは、判断が難しいテーマかもしれません。「歯が生えそろってからでいいのでは?」「虫歯ができてからで大丈夫?」と考えている方も多いかもしれませんが、実は“最初の1本の歯”が生えてきた段階で、すでにスタートラインに立っているのです。
・乳歯が生え始めたら、実はもうスタートライン
小児歯科の定期検診は、何か問題が起きた時にだけ行く“病院”ではなく、むしろ問題が起きないように予防する“生活の一部”として活用するのが理想です。具体的に「いつから通えばいいか」という目安としては、乳歯が最初に生えてくる生後6ヶ月〜1歳頃が推奨されています。この時期に初めての歯が確認できたら、小児歯科での受診を検討してみましょう。
定期検診というと「虫歯を見つけるため」と思われがちですが、実際には歯の生え方、歯ぐきの状態、噛み合わせ、授乳や離乳の進行度、口呼吸の有無など、総合的な視点から子供のお口の健康状態をチェックする場です。早期にプロの目で確認してもらうことで、成長段階でのトラブルを未然に防ぐことができます。
・初めての受診は“診療”より“慣れる”ことが目的
「まだ小さいのに歯医者さんに行っても、何をされるんだろう…」と心配される方もいらっしゃいますが、初めての小児歯科受診は、治療をするためのものではありません。むしろ、歯科医院の雰囲気に慣れたり、スタッフや先生とコミュニケーションを取ったりすることが最大の目的です。
この“慣れ”が、将来的に歯科への苦手意識を減らし、通院を習慣にする第一歩となります。小児歯科では、お子さまのペースに合わせて優しく対応してくれるため、「歯医者さんって怖くない」と思ってもらえる工夫がたくさんあります。
また、保護者の方に対しても、仕上げ磨きの方法や歯ブラシの選び方、食生活に関するアドバイスなど、日常生活で役立つ知識を得られる場となります。ご家庭でのケアを強化するためにも、専門家からの具体的なサポートを受けることは非常に有益です。
子供の成長はあっという間に進みます。歯の健康も、放っておくと取り返しがつかないトラブルに繋がることがあります。「小児歯科の定期検診は、子供がいつから通えばいいの?」と迷った時こそ、早めの一歩が将来のお口の健康を守るカギになります。
2. 定期検診の目的は“治療”ではなく“予防”です

・小児歯科でしかできない成長観察とは?
「子供に虫歯がなければ、歯医者に行かなくてもいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、小児歯科の定期検診は、単なる虫歯のチェックにとどまりません。お子さまの成長過程に応じて、歯の生え方や顎の発達、噛み合わせの変化などを総合的に観察することが大切です。
特に乳歯の時期は、歯の位置や並びにクセが現れやすく、将来的な歯並びや発音、噛み合わせに大きく影響する可能性があります。小児歯科の専門家による定期的なモニタリングを受けることで、早期の対応が可能になり、重篤なトラブルを未然に防ぐことができます。
・虫歯ゼロを叶えるプロのケア
小児歯科の定期検診では、毎日の歯みがきだけでは落としきれない汚れを専門的な器具で取り除いたり、歯の表面にフッ素を塗布して虫歯予防を行ったりします。家庭でのケアだけでは限界があるため、歯科医院での定期的なクリーニングは非常に有効です。
特に子供の歯は大人の歯よりもエナメル質が薄く、虫歯の進行が早いという特徴があります。初期段階の小さな虫歯は、痛みを感じないまま進行してしまうこともあるため、定期検診での早期発見が重要なのです。
・親だけでは気づけない“リスクの芽”を早期発見
お子さまの口の中は、日々変化しています。親御さんが毎日仕上げ磨きをしていても、見逃してしまうリスクのサインが潜んでいることもあります。例えば、歯と歯の間の汚れや、歯茎の腫れ、頬づえや口呼吸などの生活習慣からくる歯並びの乱れなど、小児歯科ではそうした“小さな変化”にも敏感に対応しています。
また、食生活やおやつのタイミングなど、家庭の生活スタイルも虫歯リスクに直結します。小児歯科では、歯の診察に加えて生活習慣へのアドバイスも行い、ご家庭全体の予防力を高めるお手伝いをしています。
定期検診の本当の目的は、“虫歯の治療”ではなく、“虫歯をつくらないこと”。子供の歯を守るためには、トラブルが起こる前からの継続的な予防ケアが不可欠です。「小児歯科 子供 定期検診 いつから」と迷ったら、まずは“予防のために行く”という意識に切り替えてみましょう。それが、お子さまの一生の歯の健康を支える第一歩となります。
3. 1歳〜3歳は「通う習慣」をつくる大事な時期

・月齢に応じた診察内容の違い
1歳から3歳頃にかけては、子供の歯やお口の中の状態が大きく変化していく大切な時期です。この年齢では、歯が次々と生え揃い、噛む力も発達し始めます。また、離乳食から幼児食へと移行するため、食習慣が安定してくる一方で、虫歯のリスクも高まっていきます。
小児歯科では、お子さまの年齢や月齢に応じて診察内容を調整し、それぞれの成長ステージに合ったサポートを行っています。例えば、1歳児であれば歯の本数や生える順番、2歳になると歯並びや噛み合わせのチェック、3歳頃には歯の磨き残しや食べ方の癖なども確認対象となります。
このように年齢ごとの特徴にあわせて適切なタイミングでフォローアップを受けることは、将来的なトラブルの予防にもつながります。
・歯ブラシ指導と食習慣アドバイスも受けられる
「うまく仕上げ磨きができない」「子供が歯磨きを嫌がる」など、1歳〜3歳の保護者が抱える悩みは少なくありません。小児歯科では、そうした不安に対して、専門的な立場から歯ブラシの選び方や持ち方、磨き方のコツを丁寧にレクチャーしています。
さらに、この時期は“食べ方”や“おやつの与え方”が、虫歯リスクに直結する重要なポイントになります。例えば、「ジュースをダラダラ飲ませていませんか?」「寝る前に甘いおやつを与えていませんか?」といった習慣も、定期検診時に確認される内容です。
小児歯科では、こうした生活習慣への具体的なアドバイスも受けることができるため、ご家庭での予防意識を高める大きなきっかけになります。
・親子で“予防意識”を育てる時間
この時期の定期検診のもう一つの大きな目的は、“通う習慣”を自然に身につけることです。子供にとって歯科医院が特別な場所ではなく、「当たり前に行く場所」になることで、将来的な医療嫌いや受診拒否を防ぐことにもつながります。
また、定期的に歯科医院に通うことで、保護者の方自身も自然とお口の健康に関心を持つようになり、家族全体の予防意識が高まります。子供と一緒に通院しながら、歯磨きの習慣や食生活の見直しにも目を向けることができれば、より質の高い“お口の育児”が実現できるでしょう。
「小児歯科の定期検診って、子供はいつから通えばいいの?」という疑問に対して、「1歳を過ぎたら、通う習慣を作っていくことが大切です」とお伝えしたいです。この習慣こそが、お子さまの将来の口腔健康を守る大きな財産になります。
4. 幼稚園・保育園に入る前に“慣らし受診”を

・環境の変化でむし歯リスクも変わる?
幼稚園や保育園への入園は、子供にとって社会生活の第一歩です。新しい環境、新しい生活リズムが始まるこのタイミングは、実はお口の健康にも大きく影響を与える時期でもあります。毎日のスケジュールが変わることで、これまでの歯磨きの習慣が乱れたり、おやつや食事の内容が変化することがあります。
こうした環境の変化によって、これまで虫歯がなかった子でもリスクが高まることがあるため、小児歯科での定期検診を見直す良い機会でもあります。特に入園前のタイミングで一度“慣らし受診”を行っておくことで、新生活を安心してスタートさせることができるのです。
・集団生活に備えたお口の健康チェック
集団生活では、食事や歯磨きのタイミングが家庭と異なる場合も多くなります。また、歯ブラシを自分で持って行うことが増えるため、「ちゃんと磨けているか」「歯磨きのクセがついていないか」といった点も気になるところです。
小児歯科の定期検診では、歯の状態をチェックするだけでなく、園での生活に向けたアドバイスも受けることができます。仕上げ磨きが必要な年齢であることを再確認しつつ、保護者がどこに気をつけるべきかも具体的に指導されます。
また、食事中の姿勢や飲み込みのクセ、口呼吸の有無など、成長発達に関わる口腔機能もこの時期に評価することで、早期の対応が可能になります。
・苦手意識を作らない「楽しい通院」のコツ
小児歯科に通ううえで大切なのは、“歯医者さんは怖いところ”という印象を持たせないことです。特に、入園前の子供はまだ感受性が強く、不安や恐怖心を抱きやすい時期でもあります。そのため、治療の必要がない時期に“慣らし受診”として通うことが、長期的に見ても非常に有効です。
例えば、検診だけで終わる回であれば、「今日は何もしないよ」「歯医者さんでスタンプをもらおうね」といった声がけを通じて、ポジティブな経験として記憶に残すことができます。小児専門の歯科医院では、お子さまの不安を軽減するような工夫がたくさん取り入れられているため、楽しく通うことができる環境が整っています。
「小児歯科の定期検診って、子供はいつから通えばいいの?」と悩まれているなら、まさにこの“入園前”の時期が絶好のチャンスです。定期検診の目的は治療ではなく予防。そして、「通いやすさ」や「慣れ」も立派な予防につながります。幼稚園・保育園という新たな生活のスタートを、お口の健康面でも安心して迎えられるよう、ぜひ一度小児歯科を訪れてみてください。
5. 「むし歯がなくても通う」ことの大切さ

・痛みが出てからでは手遅れになることも
「子供の歯に異常がなければ、わざわざ歯医者に行かなくても大丈夫」と思っていませんか? 実は、むし歯や歯肉炎といったトラブルは、痛みなどの症状が出る前に進行してしまうことが珍しくありません。特に子供の歯は大人よりも虫歯の進行が早いため、「気づいた時にはかなり進んでいた」というケースも少なくないのです。
こうしたリスクを避けるためには、症状が出る前の“予防的な受診”が欠かせません。定期的に小児歯科でチェックを受けていれば、初期段階のむし歯や歯ぐきの腫れ、歯並びの変化なども早期に発見・対処が可能です。「小児歯科 子供 定期検診 いつから通えばいいの?」と迷ったときは、“むし歯がなくても通う”という意識に変えてみましょう。
・“異常がない”を確認する安心感
定期検診のもう一つの大きな意味は、「何も問題がないことを確認する」という安心感です。歯の生え変わりが始まる頃や、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期には、見た目ではわからないトラブルの種が潜んでいることもあります。
例えば、乳歯の裏側で隠れて生えてくる永久歯の向きや位置、前歯のすき間や奥歯の咬み合わせなど、小児歯科では成長を見据えた視点で確認してくれます。問題がないと分かれば、保護者としても安心ですし、仮に初期段階の異常が見つかったとしても、早い段階ならば比較的簡単な処置で対応できます。
・フッ素塗布やシーラントで予防強化
むし歯の治療が目的ではないからこそ、小児歯科の定期検診では予防処置が重要な役割を果たします。中でも代表的なのがフッ素塗布とシーラントです。フッ素は歯の再石灰化を助け、むし歯菌の働きを抑える効果があり、年に数回の定期的な塗布によって歯を強く保ちます。
また、奥歯の溝は複雑で汚れがたまりやすいため、シーラントという樹脂で溝を埋めてむし歯予防を行う処置も有効です。これらの処置は痛みもなく、短時間で完了するため、子供にとってもストレスが少ないのが特徴です。
自宅でのケアに加えて、歯科医院でのプロフェッショナルケアを取り入れることで、むし歯を未然に防ぐ力が大きく高まります。
「むし歯ができたら行く場所」ではなく、「むし歯をつくらないために行く場所」。それが現代の小児歯科のあり方です。「小児歯科 子供 定期検診 いつから」と検索している保護者の方こそ、この“予防の視点”を大切にしていただきたいと思います。定期検診を通じて、トラブルのない健康な歯を未来へつないでいきましょう。
6. 成長とともに変わる“歯並び・噛み合わせ”への配慮

・見逃しやすい“乳歯のゆがみ”
子供の歯並びは、生まれつき完璧なものとは限りません。乳歯の段階であっても、「少しずれて生えてきた」「噛み合わせが浅い気がする」といった違和感は、将来的な歯列不正の兆候かもしれません。しかし、乳歯はいずれ抜けるからと軽視されがちで、問題が見過ごされるケースも少なくありません。
小児歯科では、定期検診を通じて乳歯の生え方や顎の発育状況、噛み合わせのバランスなどを細かくチェックしています。こうしたチェックによって、ご家庭では気づけない“歯並びのゆがみ”を早期に把握することが可能です。
「小児歯科 子供 定期検診 いつから通えばいい?」という疑問を持たれている保護者の方も、歯並びのチェックという観点から、できるだけ早い受診が有効です。
・早期発見で将来の矯正負担を軽減
歯列や噛み合わせの問題が早期に発見されれば、それに応じた対処法を検討できます。例えば、顎の成長をコントロールするための“咬合誘導”や、口腔習癖(指しゃぶり、舌癖など)へのアプローチを早い段階で取り入れることで、将来の本格的な矯正治療の必要性やその負担を軽くすることが可能です。
特に3歳〜6歳の間は、顎の成長が活発に進む時期でもあり、ちょっとしたズレが大きな影響を及ぼすこともあります。この時期に小児歯科での定期的なチェックを受けていれば、必要に応じて咬合育成や機能訓練の提案を受けることができるのです。
・小児専門ならではの発育評価
小児歯科では、単に歯の状態を見るだけでなく、顎の成長や顔貌のバランス、呼吸や嚥下(飲み込み)などの機能面にも注目して評価を行います。こうした“全体的な発育”の視点を持って診療にあたるのは、小児を専門とする歯科医院ならではの強みです。
たとえば、片方だけで噛む癖がある、舌を前に出す癖があるといった場合、それが顎の左右非対称を生むこともあります。そうした細やかな変化も、定期的に通ってこそ経過観察が可能となり、必要に応じて専門医と連携した対応がとれるようになります。
「見た目がきれいな歯並びになってほしい」と願うのは、すべての親に共通する想いです。だからこそ、“今は乳歯だから”と後回しにせず、子供の成長段階にあわせた継続的な観察とサポートが必要です。小児歯科における定期検診は、そうした未来の健康と自信につながる第一歩です。
7. 子供の「嫌がる・泣く」への対応も小児歯科の腕の見せどころ

・無理なく慣れていくステップ診療
「うちの子、歯医者さんに行くと大泣きしてしまって…」というお声は、小児歯科ではよく聞かれるものです。実際に初めての診療や治療に対して、強く不安を感じたり、過去の痛い経験がトラウマになっていたりする子供も少なくありません。
しかし、小児歯科ではそうした子供の心理に配慮し、いきなり治療に入るのではなく、「まず慣れること」を第一の目的とした“ステップ診療”を行っています。例えば、初回は診察台に座ってみるだけ、次はお口を開けてみるだけ、と段階的に少しずつステップアップしていく方法です。
このように、恐怖心を刺激せず、子供のペースに合わせて通院を進めることで、次第に歯科医院に対する抵抗感が薄れていきます。
・保護者ができる“心の準備”とは?
子供の不安や緊張は、実は保護者の表情や声のトーンからも大きな影響を受けています。たとえば、「今日は痛いことしないからね」と言ってしまうと、逆に「いつか痛いことをされるのでは」と思わせてしまう場合も。
小児歯科でよく推奨されるのは、治療内容をあえて細かく伝えすぎず、「先生とお話して、お口をきれいにしてもらおうね」と前向きな言葉で安心感を与える声かけです。
また、診療後はたくさん褒めてあげることも大切です。「ちゃんと椅子に座れたね」「上手にお口を開けられたね」と、些細なことでも肯定的に伝えることで、自信や達成感が生まれ、次回以降の受診もスムーズになります。
・それでも泣いてしまった時の対処法
どんなに気をつけていても、子供が泣いてしまうことはあります。そんな時、無理やり押さえつけて治療を進めてしまうと、かえって恐怖心が強く残り、今後の受診そのものを嫌がるようになってしまいます。
小児歯科では、泣いている子供に対しても無理に進めず、その日は診察だけで終えたり、短時間で区切って何度か通ってもらうなど、子供にとって無理のない対応を心がけています。
また、スタッフ全員が子供の扱いに慣れているため、泣いても責めたり焦らせたりすることはありません。親御さんも必要以上に気に病まず、「泣いても大丈夫」と思って安心して通院を続けていただければ、それだけで子供の気持ちは軽くなります。
「小児歯科 子供 定期検診 いつから通えばいいの?」という疑問の背景には、「ちゃんと通えるかな?」という不安もあるかもしれません。ですが、子供が嫌がったり泣いたりするのは自然なこと。大切なのは、信頼できる小児歯科と一緒に、その気持ちに寄り添いながら、ゆっくり“通える習慣”をつくっていくことです。
8. 子供のための“通いたくなる歯医者選び”とは?

・小児専門の診療体制があるかどうか
「小児歯科 子供 定期検診 いつから通えばいいの?」と悩む保護者の方にとって、実は“どこに通うか”も同じくらい大切なポイントです。特に初めての受診や、歯科医院に不安を感じやすい年齢の子供にとって、選ぶ医院の診療体制や雰囲気は、通院の成否を左右すると言っても過言ではありません。
小児歯科専門、もしくは小児診療に力を入れている歯科医院では、子供の成長に合わせた診療計画が立てられたり、泣いたときや嫌がるときの対応ノウハウが豊富です。また、虫歯予防、歯並びチェック、口腔機能の発達評価など、定期検診で提供される内容も年齢や発達段階に応じて細かく設計されています。
まずは公式サイトなどで「小児歯科に力を入れているか」「小児専用の設備やメニューがあるか」を確認してみるのがおすすめです。
・院内環境・スタッフ対応で変わる印象
子供にとって歯医者は、未知の世界。最初に感じる“印象”が今後の通院継続に大きく影響します。そのため、院内の雰囲気やスタッフの声かけひとつで、子供が安心するかどうかは大きく変わるのです。
たとえば、待合室に絵本やぬいぐるみがある、キッズスペースが設けられている、診察室の壁紙が可愛いキャラクターで彩られているなど、子供がリラックスしやすい空間づくりは、通いやすさの大事なポイントです。
また、スタッフが子供に優しく声をかけてくれるか、笑顔で対応してくれるかどうかも重要です。小児対応に慣れているスタッフがいると、それだけで子供の緊張がほぐれやすくなります。
・子供にとっての“楽しい場所”になる工夫
小児歯科のゴールは、治療だけではありません。むしろ「歯医者さんは怖くない」「また行ってもいい」と子供自身が思えることこそが、大きな意味を持ちます。
そのために多くの小児歯科では、通院を“楽しい体験”に変える工夫を凝らしています。たとえば、診察後にシールやご褒美がもらえたり、診療ごとにスタンプカードを進めたりすることで、子供が自発的に「行きたい!」と思えるようにしています。
また、子供の成長を一緒に喜びながら褒めてくれる先生やスタッフの存在も、大きな安心感につながります。こうした“ポジティブな通院経験”を積み重ねることで、定期検診が自然と習慣になっていくのです。
「子供を歯医者に通わせたいけど、どこを選べばいいのかわからない」という方は、ぜひ「子供が楽しめる」「無理なく続けられる」視点で小児歯科を選んでみてください。小さな“通院の成功体験”を積み重ねることで、お子さまの将来の歯の健康が、しっかりと守られていきます。
9. 定期検診を続けるとどんな変化があるの?

・むし歯ゼロを継続できる理由
「小児歯科 子供 定期検診 いつから通えばいいの?」という問いに対して、“早くから、そして定期的に”という答えが多くの専門家の共通認識です。では、実際に定期検診を続けることで、どんな変化が見られるのでしょうか?
まず大きな成果として、「むし歯ができにくくなる」「むし歯ゼロをキープできる」という点が挙げられます。定期的なチェックによって初期むし歯を早期発見・早期対応できるほか、フッ素塗布やクリーニング、シーラント処置などで虫歯予防を強化できます。
さらに、正しい歯みがき習慣や食生活のアドバイスを受けられるため、ご家庭でのケアの質も自然と向上します。こうした相乗効果によって、むし歯ゼロを維持しやすくなるのです。
・子供自身の“お口の自立心”が育つ
定期検診を通じて得られるのは、単なる予防効果だけではありません。何度も通ううちに、子供自身がお口の健康に対して関心を持ち、自分で守ろうとする意識=“お口の自立心”が育っていきます。
たとえば、歯医者さんで褒められたことで自信がついたり、「自分で磨いたらシールがもらえた」といったポジティブな経験が通院へのモチベーションにつながります。やがて、歯みがきの大切さを自分から話すようになったり、食べ方に気をつけるようになったりと、日常生活の中で自然に行動が変化していきます。
このように、歯科医院は“教育の場”としても非常に重要です。定期検診を通じて、子供が自らの健康を守る第一歩を踏み出せるようサポートすることが、小児歯科の大切な役割のひとつなのです。
・将来の医療費や矯正の負担も減る
定期検診をきちんと受けてきた子供と、トラブルが起きた時だけ通っていた子供とでは、将来に大きな差が出ることがあります。虫歯や歯周病の予防ができることで、将来的に治療が必要になる回数が減り、結果的に医療費の節約にもつながります。
また、早期からの歯並びチェックや咬合誘導によって、本格的な矯正治療が必要になる前にコントロールできる場合もあります。たとえ矯正治療を受けることになったとしても、期間や費用を抑えられる可能性が高くなるのです。
つまり、小児期の定期検診は“今”だけでなく“未来”のための投資でもあります。子供の健康な笑顔と将来の負担軽減、そして家族の安心感――すべてがつながっていくのが、定期的な小児歯科通院の魅力です。
10. まずは1歳のお誕生日検診から始めてみませんか?

・「まだ早い」はもう昔の話
「1歳で歯医者に行くなんて、まだ早すぎるのでは?」と感じる保護者の方は少なくありません。しかし最近では、“1歳のお誕生日に小児歯科デビュー”という考え方が広まりつつあります。実際、日本小児歯科学会などの専門団体も、「1歳頃からの歯科受診」を推奨しています。
これは、最初の乳歯が生え始めるのが生後6ヶ月〜10ヶ月頃であり、1歳の頃にはすでに複数の歯が生えているケースが多いためです。歯が生えるということは、虫歯のリスクが始まるということでもあります。「小児歯科 子供 定期検診 いつから行けばいい?」という問いには、「1歳になったら、まず一度受診を」と自信を持ってお答えできます。
・初回はカウンセリングだけでもOK
「うちの子、人見知りでじっとしていられるか心配」「泣いてしまって診察どころじゃないかも」――そんな不安を抱える方にこそお伝えしたいのが、小児歯科での初診は“治療”ではなく“慣れること”が目的だという点です。
初回は、診察台に座ってみるだけ、お口の中をちょっとだけ見てもらう、保護者の方と先生がカウンセリングをする…といった軽い内容で終えることも多いです。それでも十分に意味があり、「歯医者さんは怖くない場所だ」と感じてもらう大切なきっかけになります。
また、保護者の方にとっても、仕上げ磨きの方法、歯ブラシやフッ素の選び方、食生活の注意点など、家庭で役立つ情報を得られる場となるため、安心して相談できる関係づくりにもつながります。
・お子様の笑顔を守る第一歩を一緒に
1歳から始まる定期検診は、「早すぎる」のではなく「最も適切なスタート」です。乳歯の健康は、永久歯の正しい成長にも大きく関わってきます。だからこそ、初めての歯が生えたタイミングで受診し、正しいケアと予防を学ぶことが、お子さまの未来の健康な笑顔へとつながっていくのです。
また、小児歯科では一人ひとりの発育状況や性格に合わせて診療計画を立てるため、安心して長くお付き合いできる環境が整っています。通いやすい医院を見つけ、家庭でも定期受診の習慣をつけておけば、虫歯や歯並びの問題に悩むことのない子育てを目指すことができます。
「いつか行こう」ではなく、「まずは1歳のお誕生日に行ってみよう」。それが、お子さまの一生を左右する大切なスタートラインです。小さな一歩が、未来の大きな安心へとつながっていく――その第一歩を、ぜひ小児歯科で踏み出してみてください。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより