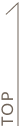1.「もしかしてうちの子、八重歯かも?」と気づいたら

見た目でわかる八重歯・乱ぐい歯のサイン
お子さまの歯並びを見たとき、「なんだか歯がガタガタしている」「犬歯が外に飛び出している」——そんな違和感を覚えたことはありませんか?それは、歯並びの乱れである「叢生(そうせい)」、いわゆる“八重歯・乱ぐい歯”の可能性があります。
叢生とは、あごの骨に対して歯の大きさが合っておらず、歯がきれいに並びきらずに重なって生えてしまう状態のこと。特に乳歯から永久歯へ生え変わるタイミングで目立ち始めることが多く、見た目にわかりやすい特徴でもあるため、早期に気づきやすい歯並びのトラブルです。
「成長すれば自然に治る」は正しい?
「まだ子どもだし、成長すれば自然と治るのでは?」と考える保護者の方も少なくありません。確かに、成長によってある程度歯並びが整うケースもありますが、叢生はほとんどの場合、自然に改善することはありません。
むしろ、永久歯がすべて生えそろったあとに問題が顕著になり、歯列全体が大きく乱れてしまうこともあります。また、見た目の印象だけでなく、噛み合わせのバランスが崩れることで、咀嚼効率の低下や発音障害、歯磨きのしづらさによる虫歯・歯肉炎のリスクも高まります。
早めの対応で将来の選択肢を広げる
歯並びの問題は、早い段階でアプローチすることで治療の選択肢が広がり、負担も軽減できます。特に叢生は、あごの骨の発育や舌の使い方など、成長期にコントロール可能な要因が関係していることも多く、混合歯列期(5~8歳頃)に専門医の診断を受けることで、抜歯をせずに整えられる可能性もあります。
当院では、取り外し可能なマウスピース型矯正装置やプレオルソなど、削らず・抜かずに対応できる「成長誘導型」のやさしい矯正を導入しています。装置の使用により、歯が並ぶスペースを自然に確保しながら、あごの発育をサポートすることができます。
こんな様子が見られたら、まずは専門医へ
以下のような症状が見られた場合には、一度矯正歯科の専門医に相談することをおすすめします。
- ・犬歯が他の歯よりも高い位置に生えている
- ・歯が重なっていて歯磨きがしにくい
- ・笑ったときに歯がデコボコに見える
- ・噛むときに歯がうまく当たらない
これらは、叢生の初期サインであることが多く、放置すると症状が進行してしまうこともあります。
「歯並びは遺伝だから仕方ない」と思わず、まずは専門家の目で現在の状態を確認してもらいましょう。早期発見・早期対応が、お子さまの健康と笑顔につながります。
2. 成長にともなうあごと歯並びのバランスに注目

歯が並ばないのは「スペース不足」が原因
「なぜ八重歯や乱ぐい歯(叢生)が起きるのか?」——それは、主に「歯が並ぶためのスペースが足りない」ことが原因です。
お子さまの成長期において、あごの骨の大きさと歯の大きさには個人差があります。あごが小さく、そこに大きな永久歯が生えてこようとすると、歯が重なったり、飛び出したように生えたりして、きれいに並ぶことができません。
つまり、乱ぐい歯は“歯そのものの問題”ではなく、“土台となるあごの発育”に大きく関係しているのです。
骨格の問題か?それとも生活習慣の影響か?
乱ぐい歯の原因には大きく2つのタイプがあります。
1つ目は「骨格性の問題」。これは、生まれつきあごが小さい、もしくは上あご・下あごの成長バランスに偏りがあることにより、歯が並ぶスペースが確保されにくい状態を指します。
2つ目は「機能性の問題」。これは、指しゃぶり、口呼吸、舌で歯を押す癖、うつ伏せ寝などの生活習慣が、長期的にあごの発育や歯の向きに影響を与えてしまうケースです。
特に乳幼児期から続く悪習癖は、顎骨の正常な成長を妨げることがあるため、早期の介入が望まれます。
「ゴールデンエイジ」は見逃せないチャンス
歯並びやあごの発育に関しては、「成長期にしかできない治療」が存在します。
特に5〜8歳頃の「混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざっている時期)」は、成長の力を利用してあごの骨格そのものを整えることができる、まさに“ゴールデンエイジ”です。
このタイミングで正しい矯正治療を行うことで、永久歯が生えそろった後の矯正の必要性を減らせたり、抜歯を避けられたりする可能性が高まります。
逆にこの時期を逃してしまうと、骨格が完成に近づくため、あごを広げたり方向づけるといった“成長誘導”が難しくなり、ワイヤー矯正や外科処置が必要になることもあります。
あごの成長を味方につけた矯正を
当院では、お子さまの成長段階に応じて、マウスピース型の機能的矯正装置(プレオルソなど)や拡大装置を使用し、歯が自然ときれいに並ぶための“土台作り”を行います。
これにより、スペース不足が原因の叢生に対して、歯を無理に動かすのではなく、あごの成長方向そのものを整えていくことが可能になります。
お子さまの年齢と成長に応じた“今しかできない治療”を提案することで、身体にやさしく、将来の選択肢も広がる治療を実現しています。
気づいたその時が、治療のチャンス
「ちょっと気になるけれど、まだ様子を見ていても大丈夫かな?」と迷われることもあるかもしれません。
しかし、叢生は時間とともに自然に改善することはほとんどなく、むしろ永久歯が生えそろうほどに問題が複雑化していく傾向があります。
早期に正確な診断を受けることで、必要であれば負担の少ない初期治療を行い、将来的な本格矯正の必要性を減らすことも可能です。
まずは、お子さまの成長ステージに合った正しいアドバイスを得ることから始めてみてください。
3. 放置するとどうなる?八重歯・乱ぐい歯(叢生)が与える影響
が与える影響.jpg)
見た目の印象だけで済まない“歯列不正”のリスク
「歯並びが少しデコボコしているけど、特に困っていないし…」——そう感じている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、八重歯や乱ぐい歯(叢生)は、ただの“見た目の問題”ではありません。
放置してしまうことで、噛む・話すといった日常動作に支障が出たり、全身の健康状態にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
ここでは、叢生を放置した場合に起こりうるリスクについて詳しくご説明します。
噛み合わせの不調が“消化器官”に与える負担
叢生があると、上下の歯が正しくかみ合わず、前歯で食べ物をうまくかみ切れなかったり、奥歯に偏って負担をかけるようになります。
結果として、咀嚼(そしゃく)効率が低下し、食べ物を十分に噛み砕かずに飲み込むことで胃腸に負担がかかり、消化不良を引き起こすことも。
「よく噛む」ことは、子どもの身体の発育や集中力にも影響する大切な機能です。叢生を放置すると、こうした重要な機能が正しく発揮されなくなってしまいます。
発音が不明瞭に?滑舌の悪化と自信の低下
歯並びの乱れは、発音にも影響します。特にサ行・タ行・ラ行といった音は、歯と舌の位置関係が重要で、乱ぐい歯によって舌がうまく動かせず、発音が不明瞭になってしまうことがあります。
小学校に入っても滑舌が気になる、話すときにモゴモゴしてしまう——このような場合は、叢生が原因である可能性も考えられます。
「話し方が変」と指摘されることで、子どもが人前で話すことに自信を持てなくなってしまうこともあり、早めの対処が求められます。
歯磨きが難しくなり、むし歯や歯肉炎の温床に
歯が重なり合って生えている叢生の状態では、歯ブラシが届きにくい部分が増え、どうしても磨き残しが多くなります。
その結果、歯垢(プラーク)がたまりやすくなり、むし歯や歯肉炎のリスクが高まります。
特に子どもは自己流の歯磨きになりやすく、保護者の仕上げ磨きが欠かせない年代でもあります。叢生があると磨き残しのチェックが難しくなり、知らないうちに虫歯が進行していたというケースも少なくありません。
顔貌や表情、姿勢にも影響が及ぶことも
歯並びは顔の印象にも大きく関係しています。八重歯が目立つことで口元が突出して見えたり、上下のあごのバランスが崩れると、横顔や全体の顔貌にアンバランスさが出てしまうこともあります。
また、噛み合わせのズレは頭の位置や肩・背中のバランスにも影響し、猫背や側弯などの“姿勢の悪さ”として現れるケースも。
このように、歯並びの問題は「お口の中」にとどまらず、全身の成長や印象にまで関わってくるのです。
将来的な矯正治療の負担を増やす可能性
叢生をそのままにしておくと、歯や顎の成長が定着し、大人になってからの矯正治療では抜歯や外科的な処置が必要になることもあります。
子どものうちであれば、顎の成長を促しながら歯並びを整える“成長誘導”が可能ですが、大人になると骨格自体は完成してしまうため、限られた方法でしか対応できなくなってしまいます。
つまり、叢生は「今の問題」だけでなく、「将来の選択肢」を狭めてしまうリスクがあるということを忘れてはなりません。
「気になったらすぐ相談」が未来を守る
叢生による影響は一つではありません。食べる、話す、笑う——毎日の生活に深く関わる問題だからこそ、早めの対応が何よりも大切です。
「少し歯が重なっているだけ」と軽く考えず、少しでも気になった段階で、専門医による診査を受けてみてください。早期に気づき、適切な時期に対策を取ることで、将来の健康と笑顔を守ることができます。
4. 小児矯正は“早いほうが良い”って本当?

混合歯列期にできる「成長誘導」の重要性
「子どもの矯正はいつから始めればいいのか分からない」「早く治療を始めすぎても意味がないのでは?」と疑問に思う親御さんは少なくありません。
実際、小児矯正において最も大切なのは“早く始めること”ではなく、“適切な時期に始めること”です。
特に注目されるのが、乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」と呼ばれる時期。一般的に5〜8歳頃を指し、この時期は顎の骨が柔らかく、成長スピードも速いため、矯正治療によって顎のバランスや歯の生えるスペースをコントロールしやすいのです。
この「成長誘導」とも呼ばれるアプローチは、歯並びだけでなく顎の発育や噛み合わせにまで影響を与えるため、将来的な歯列不正の予防にもつながります。
歯を抜かずに整えられる可能性が広がる理由
矯正治療を検討する際、多くの親御さんが心配されるのが「永久歯を抜かないと治らないのか?」という点です。
実は、成長期に正しいタイミングで治療を始めれば、顎の成長を誘導することで、歯がきれいに並ぶためのスペースを確保することができます。
たとえば、顎が小さくて歯が並びきらない場合、早期に顎の幅を広げるような装置を使うことで、将来的に歯を抜かなくてもきれいに整えることが可能になるのです。
一方、永久歯がすべて生えそろってから矯正を始めた場合は、スペース不足が解消されないまま歯を並べようとするため、抜歯が必要になるケースが増えてしまいます。
つまり、小児矯正は“非抜歯矯正”を実現するための重要なステップであり、お子さまの将来の負担を軽減する意味でも大きな価値があるのです。
適切なタイミングでのアプローチとは
では、具体的にいつから矯正を検討すれば良いのでしょうか?
一般的には、前歯の永久歯が生え始める5〜8歳前後がひとつの目安とされており、ここから始めることで、上顎や下顎のバランス調整、悪習癖の改善、歯列のスペース確保など、さまざまな効果が期待できます。
この時期に矯正を始めるメリットは、“歯を動かす”のではなく、“骨の成長方向を整える”ことができる点にあります。
一方、顎の成長がほぼ止まってしまう中高生以降では、このような骨格へのアプローチは難しくなり、装置の装着期間が長くなったり、外科的な対応が必要になる可能性も否定できません。
特に叢生(八重歯・ガタガタの歯並び)や反対咬合などの兆候が見られるお子さまは、できるだけ早めに専門医に診てもらうことで、最適なタイミングでのアプローチが可能となります。
「何歳から始めればいいのか分からない」という状態で放置せず、「今がその時期かもしれない」と気づいた段階で一度専門医へ相談してみることが、後悔のない矯正治療の第一歩です。
5. 当院が行う“削らず・抜かない”やさしい矯正

プレオルソやマウスピース型装置で顎の成長をサポート
「できるだけ歯を抜かずに整えたい」「子どもに負担をかけずに治療したい」——そんな親御さまの想いに応えるのが、私たちが提案する“やさしい矯正”です。
当院では、5〜10歳頃の混合歯列期に行うⅠ期治療において、プレオルソやムーシールドといったマウスピース型機能矯正装置を活用しています。
これらは取り外し可能な装置で、日中1〜2時間+就寝時に装着するだけで、舌の位置・呼吸・咀嚼機能を改善し、顎の成長方向をコントロールする働きがあります。
プレオルソは特に上顎前突(出っ歯)や叢生(ガタガタの歯並び)に有効で、柔らかい素材のためお子さまにも優しい設計となっています。
叢生の根本原因にアプローチする治療法
叢生(八重歯・乱ぐい歯)は、単に歯が大きくて並びきらないというだけではありません。実は、その背景には「顎が小さい」「舌の位置が悪い」「口呼吸や頬杖などの習慣」など、さまざまな機能的な問題が隠れていることが多いのです。
従来の矯正治療では、歯を抜いてスペースを確保するのが一般的でしたが、当院では、根本的な原因を改善することに重きを置いています。
たとえば、口呼吸をしているお子さまには、呼吸訓練を取り入れることもあります。
舌癖が原因の場合は、舌の位置を正すトレーニングを実施し、装置の効果を最大化させる取り組みを行っています。
このように、装置をただ使うのではなく、日常の生活習慣の見直しを含めた「機能的アプローチ」によって、将来にわたる歯並びの安定を目指します。
お子さまに負担の少ない治療スタイル
子どもの矯正において、最も大切なのは「本人が嫌がらずに治療を続けられること」です。
そのため、当院では痛みが少なく・取り外しも可能・目立ちにくいといった条件を満たす装置を選定し、できるだけストレスの少ない治療環境を整えています。
特にマウスピース型装置は、食事や歯磨きの際に外せるため衛生面でも安心です。
さらに、治療の進捗に合わせて装置をステップアップさせたり、定期的なカウンセリングでお子さまのモチベーションを確認したりと、心理的なサポートにも力を入れています。
装置の使用時間が守れているか、正しく装着できているかなどは、親御さまとの連携も重要です。私たちは、ご家族と一緒に治療を進めていく“チーム医療”の姿勢で、毎回の診察を大切にしています。
子どもの成長を利用し、歯や骨を“削らず・抜かず”に整えるこの治療法は、将来の本格矯正の負担を軽減し、健康的で自然な笑顔を育てる最善の方法といえます。
6. 治療が必要かどうかの見分けポイント

正面・横顔からのチェック方法
「矯正が必要かどうか、親が見て判断できるの?」と感じる方も多いかもしれません。実際の診断は専門医による精密な検査が必要ですが、ご家庭でもできる“気づきのサイン”はあります。
まず、正面から見て歯がガタガタに並んでいないかを確認してみましょう。特に上の前歯の重なりやねじれ、下の前歯が奥まって生えているような場合は注意が必要です。
次に、横顔に注目します。鼻先からあご先までを一直線で結んだラインに対し、上下のあごのバランスが極端にズレていないかを確認します。
あごが引っ込んで見える(上顎劣成長)・前に突き出ている(下顎前突)などの場合、骨格的な不調和が考えられます。これらは歯並びだけでなく、顔貌にも大きな影響を与えます。
噛み合わせ・歯の生え方から見えるサイン
鏡で噛み合わせを見たときに、上の歯と下の歯の中心がズレている、噛んだ状態で下の前歯が見えない(過蓋咬合)、または上下の歯がかみ合わずに隙間がある(開咬)といった場合も、矯正治療が必要になる可能性があります。
また、乳歯の段階で既にスペース不足がある場合、永久歯が生え変わる際に叢生(乱ぐい歯)になりやすくなります。
そのほかにも、「前歯が交差している」「奥歯だけでしか噛めていない」といった兆候が見られる場合は、噛み合わせに異常があるかもしれません。
お子さま自身が「食べづらい」「噛みにくい」と訴えることがあれば、それも立派なサインです。成長期の子どもは、顎の大きさと歯のサイズが一致しないことで歯列の乱れが起こりやすいため、早めの判断がカギとなります。
こんな習慣が要注意(指しゃぶり・口呼吸など)
歯並びや噛み合わせの乱れは、実は生活習慣とも密接に関係しています。
たとえば、指しゃぶりを3歳以降も続けている場合、前歯が前に出る・上顎が狭くなるなどの影響が出やすくなります。
また、常に口が開いている「お口ポカン」の状態や、鼻ではなく口で呼吸している口呼吸も、歯列や顎の発達に悪影響を与えることがあります。
他にも、頬杖・うつ伏せ寝・舌で歯を押す癖などは、顎や歯並びの左右非対称を招く原因にもなり得ます。
このような習慣は、見逃しがちではありますが、放置することで徐々に歯列に影響を及ぼします。
矯正治療では、こうした悪習癖の改善から取り組むことで、根本から歯並びを整えるアプローチが可能になります。
気になる癖や症状がある場合は、まず専門医に相談してみましょう。「何もしない」がリスクになる前に、できることを始める——それが、お子さまの未来の笑顔を守る第一歩です。
7. 矯正を続けるために大切なのは“気持ち”

お子さまが矯正を嫌がらないために
子どもの矯正治療において、実際に装置を装着し、日々のルールを守っていくのはお子さま自身です。
そのため、いかにスムーズに矯正生活に入っていけるか、そして“嫌がらずに続けられるか”が治療成功のカギを握ります。
特に、取り外し式のマウスピース型装置は、決められた時間装着しなければ効果が出ません。
「なぜ治療が必要なのか」「どうすればきれいな歯並びになるのか」をお子さまにもわかりやすく伝えることが、モチベーションを高める第一歩です。
私たちの現場でも、お子さまが自ら進んで装置を使えるよう、年齢に合わせた言葉で丁寧に説明しています。
「痛い」「めんどくさい」と思わせない環境づくり
矯正装置をつけることに対して、お子さまが不安や抵抗感を持つのは当然のことです。
「学校で目立ったらどうしよう」「つけると痛いのかな」「めんどうだから外しちゃおうかな」——そんな気持ちを抱えながら治療を続けていくのは大変なことです。
だからこそ、私たち大人は、治療を「怖いもの」「我慢するもの」ではなく、「自分のためになること」として認識してもらうことが大切です。
たとえば、装着が上手にできた日には「よく頑張ったね」と声をかけたり、カレンダーにシールを貼って達成感を味わえるようにするなどの工夫も効果的です。
当院では「がんばりカード」や「治療ノート」などを用意し、子どもが“ゲーム感覚”で治療を前向きに取り組めるようにサポートしています。
保護者と歯科医が協力してサポートすることの重要性
子どもが治療を継続するうえで、最も重要なのは周囲のサポートです。
ご家庭での声かけや日々のケアはもちろん、歯科医師やスタッフとの信頼関係があってこそ、お子さまは安心して治療に取り組めます。
「今日は装置を使ったかな?」「少し痛くなかった?」と、何気ない会話の中で治療を身近に感じてもらうことが、継続への大きな力になります。
また、保護者の方が過度に心配したり、ネガティブな言葉をかけてしまうと、逆にお子さまが不安を感じることもあるため注意が必要です。
大人が“味方”であることをしっかり伝え、困ったときに相談できる安心感を与えてあげましょう。
私たちも、お子さまだけでなくご家族の皆さまとの連携を大切にし、成長を支えるチームとして寄り添いながら治療を進めていきます。
8. Ⅱ期治療(本格矯正)が必要になる場合とは?
が必要になる場合とは?.jpg)
小児矯正だけで終わらないケースも
「Ⅰ期治療(成長誘導)だけで矯正が終わる」と思われる方もいらっしゃいますが、すべてのお子さまがⅠ期治療のみで完了するとは限りません。
Ⅰ期治療は、顎の骨のバランスを整えたり、悪習癖を改善したりすることで、将来的な矯正の負担を軽減することが目的です。
しかし、歯の生え変わりや顎の成長が続く中で、歯列全体のバランスや噛み合わせが理想から外れてしまうケースもあります。
このような場合、永久歯が生えそろった段階で行う「Ⅱ期治療(本格矯正)」が必要となります。
永久歯列が完成してから行う仕上げの治療
Ⅱ期治療は、永久歯がすべて生えそろった中学生以降に行うことが多く、歯を理想的な位置に正確に並べることを目的としています。
Ⅰ期治療で顎のバランスが整っていても、歯の大きさや生え方によってスペースが足りない場合や、軽度な歯のねじれ・回転などがある場合は、Ⅱ期治療によって最終調整を行う必要があります。
この「仕上げの矯正」によって、見た目の美しさだけでなく、正しい噛み合わせと機能の安定を得ることができます。
治療期間や方法の選択肢(ブラケット・マウスピース)
Ⅱ期治療では、主に以下の2つの方法があります。
- ・ワイヤー(ブラケット)矯正:歯に装置を付け、ワイヤーで力を加えて動かしていく方法。複雑な症例にも対応可能。
- ・マウスピース型矯正(インビザラインなど):透明で取り外し可能な装置を使用。目立たず、衛生的で続けやすいのが特長。
当院では、ティーン向けのマウスピース矯正にも対応しており、学校生活や部活動と両立しやすい治療スタイルをご提案しています。
Ⅰ期治療をきちんと行っていれば、Ⅱ期治療は短期間で済んだり、抜歯を避けて対応できる可能性が高まります。
治療方法や装置は、お子さまの性格・ライフスタイル・希望をふまえ、矯正専門医が一緒に最適な選択を考えますのでご安心ください。
Ⅱ期治療は、子どもの成長の集大成として“より理想に近い歯並び”を完成させるための大切なステップです。
Ⅰ期治療と比べて少し本格的にはなりますが、お子さまが大人になる前に健康な口腔環境を整えることで、将来的な虫歯・歯周病・顎関節症などのリスクを大幅に減らすことができます。
「今、Ⅱ期治療が必要なのかどうか」は、お子さまの成長段階や口腔の状態によって異なります。定期的なチェックやご相談を通じて、最適なタイミングを見極めていきましょう。
9. 矯正中の虫歯予防と口腔ケアの工夫

矯正中はなぜ虫歯になりやすい?
矯正治療中は、装置の影響で歯ブラシが届きにくくなり、食べカスや歯垢(プラーク)が溜まりやすくなります。
ワイヤー矯正では、ブラケットやワイヤーの周囲に汚れがたまりやすく、マウスピース矯正でも、装着中に飲食したり、十分に歯を磨かずに再装着したりすると、細菌が繁殖しやすくなります。
その結果、虫歯だけでなく、歯肉炎や歯周病のリスクも高まってしまうのです。
フッ素・シーラントなどの予防処置の重要性
当院では、矯正治療中のお子さまに対して、定期的な予防処置を強くおすすめしています。
フッ素塗布は、歯の再石灰化を促進し、歯を強くする働きがあります。特に矯正中は、フッ素を定期的に塗布することで虫歯予防効果が高まります。
また、生えたばかりの永久歯や奥歯にはシーラントという処置が有効です。これは歯の溝をレジンでコーティングし、汚れの付着を防ぐものです。
これらの予防処置を行うことで、矯正治療中も安心して治療を続けることができます。
親子でできる毎日のケア習慣
虫歯予防の基本は、毎日の丁寧な歯みがきです。特に小さなお子さまの場合、自分だけで完璧に磨くのは難しいため、保護者による仕上げ磨きが非常に重要です。
以下のような工夫を取り入れて、毎日のケアを“習慣化”することがポイントです。
- ・マウスピースを外すたびに歯を磨くことを徹底する
- ・夜は必ず仕上げ磨きを行い、磨き残しをチェック
- ・歯ブラシだけでなく、タフトブラシやフロスを活用する
- ・磨けた日にはシールを貼る「がんばりカレンダー」を導入
こうした小さな取り組みが、お子さまの“自分でお口を守る力”につながっていきます。
歯科衛生士によるプロのケアとの連携
矯正中は、歯科医院での定期的なメンテナンスが不可欠です。
当院では、担当の歯科衛生士が専門的な器具を使って歯垢や歯石を除去し、お子さまのお口の状態を細かくチェックします。
さらに、「ここがよく磨けているね」「この部分は少し意識してみよう」など、褒める・励ます声かけで、お子さまのモチベーションを育てることも大切にしています。
また、見た目にはわからない初期虫歯や歯肉の炎症なども早期に発見できるため、安心して矯正を続けることができます。
矯正治療は、見た目を整えるだけでなく、生涯にわたるお口の健康づくりの第一歩でもあります。
治療中に適切なケアを行えば、虫歯リスクを大幅に減らし、治療の質を高めることが可能です。
保護者と歯科医院が連携しながら、楽しく・継続できるケア習慣をお子さまに育てていきましょう。
10.「治療、どうしよう」と思ったら今が相談のタイミング

相談=治療の決断ではありません
「矯正が必要かもしれないけれど、まだ早いかな?」「子どもが嫌がったらどうしよう?」——そう思って、受診をためらっていませんか?
歯並びに関する相談は、必ずしも「すぐに治療を始める」という意味ではありません。
むしろ、相談の時点でお子さまの状態を知ることが、今後の選択肢を広げる第一歩となります。
「まだ必要ない」という判断が得られることもありますし、「将来的に矯正が必要になる可能性がある」とわかるだけでも、安心して備えることができます。
今の状態を知ることが、最善の第一歩
叢生(八重歯・乱ぐい歯)は見た目の問題だけでなく、虫歯や歯周病、かみ合わせ不良など、機能面にも影響する可能性があります。
そのため、見た目だけで判断するのではなく、専門医による精密な診断が欠かせません。
初診相談では、歯の生え方・顎の発育状態・口腔習癖・生活環境などを総合的に診査し、「今すぐ治療が必要か」「経過観察でも大丈夫か」を客観的にご案内します。
お子さまの成長スピードや性格に応じて、最適な治療開始時期も変わってきますので、個別の判断が重要なのです。
成長に合わせた“今できる治療”を一緒に考える
当院では、保護者の方の不安や疑問に丁寧に耳を傾け、お子さまの状態と成長を見据えた治療プランをご提案しています。
たとえば、5〜8歳の混合歯列期であれば、顎の発育をコントロールするプレオルソやマウスピース型の機能的矯正装置を活用して、「歯を抜かずに整える」可能性を高める治療が選択できます。
また、「今はまだ経過観察でよい」と判断した場合でも、次回のチェックタイミングやご家庭で気をつけるポイントなどもお伝えし、安心して様子を見られるようサポートします。
一方的な治療の押しつけは一切なく、ご家族と一緒に治療方針を考える姿勢を大切にしています。
初診カウンセリングは気軽な一歩から
初めての矯正相談は、お子さまにとってもご家族にとっても緊張するものです。
当院では、カウンセリングの段階でいきなり装置を装着したり、無理に治療を勧めたりすることはありません。
写真撮影や模型の確認などを通じて、現状を「見える化」し、お子さまにもわかるよう丁寧にご説明します。
相談の目的は「治すこと」ではなく「知ること」。その先に、お子さまに合った最適な選択が生まれます。
「気になっていたけれど、もっと早く相談すればよかった」——多くの親御さまが、診断を受けた後にそうおっしゃいます。
迷っている今こそ、お子さまの未来にとって大切なタイミングかもしれません。
治療を始めるかどうかを決めるのは、診断を受けたあとで大丈夫です。まずは一度、ご相談ください。
矯正治療は、“いつか”より“今”の気づきが未来を変える——私たちはその第一歩を全力でサポートします。
監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより