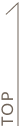1.「もしかしてうちの子、受け口?」と思ったら

見た目で気づける初期サインとは
お子さまの歯並びを見たとき、「下の歯が前に出ているような気がする」「なんだかしゃくれたように見える」など、ちょっとした違和感に気づいたことはありませんか?これは、下顎前突、いわゆる“受け口”の初期サインかもしれません。 受け口は、上下の前歯が逆に噛み合う「反対咬合」とも呼ばれ、見た目の印象だけでなく、噛み合わせや発音、さらには骨格の成長にも深く関係する咬合異常の一つです。自然に治ると思って放置しても大丈夫?
「乳歯だからそのうち治るかもしれない」と思って様子を見る方もいらっしゃいます。しかし、自然に治るケースはごくわずかで、大半はそのまま成長とともに骨格的な問題が固定化してしまうリスクがあります。 一見すると軽度に見える受け口も、放置することで下顎がどんどん成長してしまい、後になって外科手術が必要になるケースもあるため、慎重な判断が求められます。早期発見の重要性
受け口は、早期に発見し、適切な時期に対応することで、顎の成長方向をコントロールする「成長誘導」というアプローチが可能になります。 特に5歳〜8歳の混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざっている時期)は、骨がまだ柔らかく、成長をコントロールしやすい“ゴールデンタイム”です。この時期を逃すと、将来的に大掛かりな矯正や外科的処置が必要になることもあります。お子さまの小さなサインに気づくことが第一歩
日常の中で、次のようなサインが見られる場合は、早めの相談をおすすめします。- ・正面から見て、下の前歯が上の歯より前に出ている
- ・食事の際に噛みにくそうにしている
- ・発音が舌足らず、滑舌が悪い
- ・下顎が前に出ているように見える
- ・唇が閉じにくく、常に口が開いている
迷ったときこそ、専門医の診断を
「今すぐ治療を始めるべきかどうか迷っている」「放置しても大丈夫か知りたい」——そんなときこそ、矯正専門医への相談が重要です。 初期段階での診断であれば、治療の選択肢も広がり、歯を抜かずに整えることができる可能性も高まります。また、生活習慣や癖が原因の場合は、それらの改善だけで症状が軽減されるケースもあります。 受け口は単なる“見た目”の問題ではありません。お子さまの健やかな成長と、将来の健康を守るための重要なサインです。「もしかして…」と思ったら、それは治療への第一歩。まずはお気軽に、矯正相談から始めてみてください。2. 成長と共に変わる“あごのバランス”に注目

子どもの下あごが前に出る理由
「なぜうちの子のあごが出てきたのか?」——そう感じたとき、最初に知っておきたいのが“骨格の成長バランス”です。 受け口(下顎前突)は、下あごが過剰に発達していたり、逆に上あごの成長が足りないことで起こる状態です。これらのアンバランスは遺伝的要因のほか、生活習慣や口腔機能の発達にも深く関係しています。 特に、成長期の子どもは顎の骨が柔らかく日々変化しており、些細な習慣でも成長方向に大きな影響を与える可能性があります。骨格性?それとも癖や生活習慣?
受け口には大きく分けて「骨格性」と「機能性」の2つのタイプがあります。 骨格性の受け口は、上顎と下顎の骨格バランスが崩れている状態で、親からの遺伝によって起こることもあります。一方、機能性の受け口は、舌で歯を押す癖や口呼吸、頬杖、うつ伏せ寝などの生活習慣が原因で下あごが前に出やすくなる状態です。 初期の段階では機能性だったものが、成長とともに骨格性へと進行してしまうこともあり、早期の判断と対応が非常に重要になります。成長に合わせた治療ができる“ゴールデンエイジ”とは
顎の成長にアプローチできるタイミングは限られており、特に5歳〜8歳の混合歯列期は“ゴールデンエイジ”と呼ばれています。 この時期は、乳歯と永久歯が混在しており、骨格の成長を正しい方向に誘導しやすい時期です。マウスピース型の機能矯正装置などを活用することで、無理に歯を動かすのではなく、顎そのものの成長バランスを整えることが可能です。 この段階でアプローチすることにより、後の本格矯正の必要がなくなったり、抜歯や外科的治療を避けられる可能性が高まります。 また、この時期は生活習慣の改善にも効果的です。舌の使い方、呼吸の仕方、口腔筋機能などをトレーニングで正しく導くことで、顎の成長だけでなく発音や咀嚼機能の改善にもつながります。 保護者の方が「今しかできない治療がある」という意識を持っていただくことで、お子さまの将来の選択肢は大きく広がるでしょう。3. 放置するとどうなる?受け口が与える影響

噛みにくさや消化不良につながるリスク
受け口(反対咬合)を放置してしまうと、まず顕著に現れるのが「噛みにくさ」です。 通常、食べ物を前歯で噛み切る動作は、上の前歯が下の前歯を覆うような形で行われます。しかし受け口の場合は、下の歯が前に出ているため前歯同士がうまくかみ合わず、食べ物を細かく噛み切ることが困難になります。 その結果、奥歯ばかりを使って咀嚼するようになり、消化に時間がかかったり、胃腸に負担がかかったりすることもあります。 このような咬合機能の低下は、日々の食事だけでなく、成長期の栄養吸収にも影響するため、見逃せない問題です。発音・滑舌が悪くなる原因にも
受け口は歯の位置だけでなく、舌の動きにも大きく影響を与えます。 特に「サ行」や「タ行」など、舌先を使って発音する音が不明瞭になることが多く、周囲の人に聞き取りづらく感じられるケースも少なくありません。 このような発音の不明瞭さは、幼少期の言語発達や学校生活でのコミュニケーションにも支障をきたす可能性があります。 「うちの子、ちょっと滑舌が悪いかも?」と感じたときは、単なる発音のクセではなく、噛み合わせの問題が原因であることも視野に入れる必要があります。顔貌や姿勢への影響も
受け口が長期的に続くことで、骨格そのものに影響が及ぶこともあります。 下あごが前方に突出している状態が固定化されてしまうと、顔立ちが“しゃくれた”印象になったり、横顔のバランスが崩れてしまうことがあります。 また、噛み合わせのズレによって左右の筋肉の発達バランスが乱れ、あごや首・肩の筋肉に余分な力がかかることで、姿勢の悪化にもつながります。 「猫背ぎみになった」「片方の肩だけが下がっている」など、一見歯並びとは関係なさそうに思える変化も、実は受け口が関係していることがあるのです。心理的な影響も見逃せない
外見に変化が表れやすい受け口は、思春期に近づくにつれてお子さま自身がコンプレックスを抱えやすくなる傾向があります。 口元が気になって笑顔を控えてしまったり、人前で話すことに自信を持てなかったりと、自己肯定感に影響を与えるケースも少なくありません。 また、思春期以降になると矯正装置への抵抗感が強くなり、治療に消極的になることもあるため、可能な限り早い段階で取り組むことが、心理面のサポートとしても有効です。早期対応が将来の負担を減らす
受け口は「成長とともに自然に治ることもある」と誤解されがちですが、実際にはその可能性は極めて低いのが現実です。 特に骨格性の受け口は、時間の経過とともに症状が固定化し、矯正だけでは治療が難しくなることがあります。 そうなると、成人後に外科的処置(顎の骨を切る手術)が必要になるケースもあり、心身ともに大きな負担を伴います。 その一方で、5~8歳頃の“成長誘導”が可能なタイミングであれば、取り外し可能なマウスピース型の装置で、無理なく治療を始めることができます。 受け口がもたらす影響を深刻化させないためにも、「今」できることを選ぶことが、お子さまの未来のための最良の選択です。4. 受け口の治療に“早すぎる”はない

混合歯列期(5〜8歳)が最適なタイミング
「まだ乳歯だし、矯正はもう少し大きくなってからでも大丈夫では?」——このように考える保護者の方は少なくありません。 しかし、実際には乳歯と永久歯が混在する“混合歯列期(5〜8歳頃)”こそが、受け口の治療を始めるためのベストタイミングなのです。 この時期は、顎の成長が活発で骨が柔らかく、成長の方向性を整える「成長誘導」が可能な貴重なチャンスです。 大人になってからの治療では、すでに成長が完了しているため骨格にアプローチすることはできません。場合によっては外科手術が必要になることもあるため、「治しやすい今こそ、始める価値がある」ということを知っておいていただきたいと思います。骨の成長誘導ができるのは今だけ
成長期のお子さまに対しては、歯そのものを動かすのではなく、顎の骨格の成長方向をコントロールする「成長誘導治療」が行えます。 具体的には、上顎の成長が遅れている場合にはその成長を促し、下顎が過剰に前に出ている場合にはその成長を抑制するような治療が可能です。 このような骨格の成長調整は、成長期にしかできない治療であり、一度成長が終わってしまえば、こうした自然な誘導は行えなくなります。 将来的に本格的な歯列矯正(Ⅱ期治療)が必要になったとしても、この段階でバランスを整えておくことで、治療期間の短縮や、より簡易的な治療ですむ可能性が高まります。歯を抜かずに治す可能性を広げるために
早期治療のもう一つの大きなメリットは、「非抜歯矯正」の可能性を高められる点です。 永久歯が生えそろったあとで受け口を治そうとすると、歯をきれいに並べるためのスペースが足りず、抜歯が必要になることもあります。 しかし、混合歯列期のうちに顎の幅や位置を調整しておけば、歯が自然と正しい位置に生えるよう導くことができるため、スペースの問題も回避しやすくなります。 つまり、早期治療は「歯を削らず・抜かずに治す」という選択肢を広げる手段でもあるのです。子どもの成長はあっという間だからこそ
子どもの成長はとても早く、気がつけば永久歯が生えそろい、骨格の成長も一段落していたということは珍しくありません。 だからこそ、気になったその時点で専門医に相談することが大切です。 「今はまだ早いかも?」という判断は、ご家庭だけで行うのではなく、専門的な診断を受けたうえで決めるのが最も安心です。 多くのケースでは「今はまだ様子を見ましょう」「半年ごとにチェックしましょう」といった経過観察になることもありますが、中には「この時期にしかできない治療があります」というタイミングもあるため、見極めが非常に重要です。“治すなら今”が未来の笑顔を守る
受け口の治療に「早すぎる」ということはありません。 むしろ、早い時期に適切な治療を始めることで、お子さまの将来の治療負担を軽減し、コンプレックスのない健やかな成長をサポートすることができます。 「まだ小さいから様子を見よう」と思わずに、まずは正しい診断を受けることから始めてみてください。 お子さまの成長ステージに合わせた最適な治療プランをご提案するためには、早めの相談こそが最大のチャンスです。5. 当院が提案する「成長誘導型のやさしい矯正」

削らず・抜かずに整えるマウスピース矯正とは
「矯正=歯を抜く・痛い・見た目が気になる」——そんなイメージをお持ちの方も少なくありません。 しかし、近年ではお子さまの成長に合わせた“削らず・抜かずに整える”マウスピース矯正が主流となりつつあります。 この治療法は、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期に行う「Ⅰ期治療」の一環として、成長中の骨格を正しい方向へ導くことを目的としています。 当院では、プレオルソやムーシールドといった機能的矯正装置を活用し、身体への負担を最小限に抑えながら自然な矯正を行っています。プレオルソやムーシールドなどの取り外し式装置
マウスピース型の矯正装置には、日中や就寝時に装着する「プレオルソ」や「ムーシールド」などがあります。 これらは取り外しができるため、歯みがきや食事への影響が少なく、お子さまのストレスを最小限に抑えながら治療を進められる点が特徴です。 プレオルソは、舌の位置や唇の筋肉、呼吸の仕方など、歯並びや顎の成長に影響を与える要素にアプローチし、機能面から受け口の改善を促します。 ムーシールドは、下顎の突出を抑える目的で使用されることが多く、特に就寝中の装着によって顎の成長をやさしくコントロールします。 これらの装置は、痛みが少なく慣れやすいため、矯正への抵抗感があるお子さまにも取り入れやすい治療方法です。生活習慣から改善する“根本治療”へのアプローチ
受け口の原因には、骨格的な問題だけでなく、舌のクセや口呼吸、指しゃぶり、うつ伏せ寝といった生活習慣が深く関係している場合があります。 当院では、単に装置を装着して歯を動かすのではなく、こうした“悪習癖”にも丁寧にアプローチすることで、再発のリスクを最小限に抑える治療を心がけています。 具体的には、口腔筋機能療法(MFT)を取り入れた指導を行い、舌の正しい位置や呼吸法、飲み込みのトレーニングを通じて、お口まわりの筋肉バランスを整えます。 これにより、見た目の改善だけでなく、「噛む・話す・飲み込む・呼吸する」といったお口の基本機能が向上し、全身の発育にも良い影響を与えます。お子さまに負担の少ない治療プランとは
成長期のお子さまにとって、矯正治療は決して無理に進めるものではありません。 当院では、一人ひとりの性格・生活リズム・装置の装着状況などを丁寧に把握したうえで、「無理なく続けられる治療計画」をご提案しています。 初回カウンセリングでは、保護者さまのご不安やご希望を伺いながら、必要に応じて検査・診断を行い、治療開始の適切なタイミングや装置の選択肢についてわかりやすくご説明します。 また、矯正に不安を感じるお子さまに対しては、楽しく通院できるような工夫(がんばりシールや治療カレンダーの導入など)を取り入れ、前向きに取り組んでいただける環境づくりを行っています。矯正は“成長を助ける治療”という考え方へ
「歯並びを整える」ことだけを目的とした矯正治療は、すでに過去のものとなりつつあります。 現在は、お子さまの健やかな成長と発育を支える“成長誘導型”の矯正が主流です。 骨格のバランスを整え、正しい機能を習得しながら歯並びを導いていくこの方法は、お子さまの将来の健康と自信につながります。 受け口に気づいたときは、ぜひ「いつかやろう」ではなく、「今できることがあるかも」と前向きにご相談ください。 大切なのは、“削らない・抜かない・痛みの少ない”やさしい治療を、適切なタイミングで受けられることです。6. 治療が必要かどうかを見極めるチェックリスト

噛み合わせの違和感
受け口(反対咬合)は、歯が噛み合う位置にズレが生じている状態です。 本来、上の前歯が下の前歯よりも前に位置しているのが正常な咬み合わせですが、受け口の場合はこれが逆転しています。 そのため、噛み合わせ時に「違和感がある」「うまく噛み切れない」といったサインが現れます。 小さなお子さまの場合、自覚症状としては表れにくいため、保護者が食事中の様子や発話時の動きを観察することが重要です。 もしお子さまが「前歯でうまくかめない」「お肉が切れない」などと感じている場合、それは治療の必要性を示す一つのサインかもしれません。横顔であごが出ているように見える
受け口の特徴のひとつに、「横顔の輪郭に違和感がある」という見た目の変化があります。 正面からは分かりにくくても、横から見ると下あごが突き出している、いわゆる“しゃくれた”印象が強くなっているケースがあります。 これは、骨格的な下顎前突(かがくぜんとつ)が進行している可能性があるサインであり、自然に治ることは稀です。 特に、小学生低学年までの成長期であれば、あごの成長方向をコントロールすることが可能なため、見た目の変化に気づいた段階で早めに矯正専門医に相談することが望ましいです。食べにくい・話しにくい・唇が閉じにくい
受け口は機能的な問題も引き起こします。 たとえば、前歯の噛み合わせが逆転していることで、食べ物をうまくかみ切れず、食事に時間がかかったり、飲み込みづらさを訴えたりすることがあります。 また、舌の位置や唇の動きにも影響を与えるため、「サ行」「タ行」「ナ行」などの発音がこもって聞こえるといった言語発達の遅れにもつながるケースがあります。 さらに、下あごが前に出ていることによって、自然に唇を閉じることが難しくなるお子さまも多く、常に口が開いた状態(いわゆる「お口ポカン」)になっている場合も注意が必要です。チェックポイントの例
以下に、受け口の可能性がある代表的なサインをまとめました。複数当てはまる場合は、早めの相談をおすすめします。- ・前歯の噛み合わせが上下逆になっている
- ・横顔で下あごが出ているように見える
- ・言葉が聞き取りにくい/滑舌が悪い
- ・食べ物を前歯で噛み切れない
- ・口が常に開いていることが多い
- ・指しゃぶりや舌で前歯を押すクセがある
- ・あごや口元に左右非対称な動きが見られる
チェックリストは“診断の入り口”です
このようなチェックリストは、あくまで“治療の必要性を判断するきっかけ”であり、すべてのケースで矯正が必要というわけではありません。 一方で、「様子を見ていていいのか」「いま始めた方がいいのか」という判断は、専門的な診査・検査がなければ難しいのも事実です。 矯正のタイミングを見極めるうえで大切なのは、自己判断で放置せず、まずは専門医のカウンセリングを受けてみることです。早期対応で広がる未来の選択肢
成長期の今だからこそできることがあります。 下顎の成長を適切な方向に導くことで、将来的に大がかりな治療や外科的処置を回避できる可能性も高まります。 また、骨格の成長をコントロールできる“限られた時期”を逃さず対応することで、歯を抜かずに矯正ができる、短期間で終えられるなど、お子さまにとっても負担の少ない選択肢が広がります。 受け口かな?と思ったら、まずは気軽な相談から始めてみてください。お子さまの将来にとって、最善のタイミングを一緒に見つけていきましょう。7. 子どもが安心して治療に向き合えるために

矯正に対する不安や抵抗をやわらげる工夫
矯正治療が必要と診断されても、多くのお子さまは「装置をつけること」に不安を感じます。 「痛いのかな?」「変な顔にならないかな?」「友達にからかわれないかな?」——そんな気持ちを持つのは、自然なことです。 その不安を和らげるために最も大切なのは、保護者が子どもの気持ちに寄り添いながら、一緒に前向きに治療に向き合うことです。 矯正治療は、見た目だけでなく健康や将来にも大きく関わる大切なステップ。だからこそ、「なぜ矯正が必要なのか」をお子さま自身が理解できるように伝える工夫が必要です。「痛い」「恥ずかしい」と感じさせない声かけ
大人の何気ないひと言が、子どもにとってはプレッシャーになることもあります。 「ちゃんとやらないと歯並びがぐちゃぐちゃになるよ」「我慢しなきゃ」ではなく、「一緒にがんばろうね」「装置を使えばもっと笑顔が素敵になるよ」といった、安心感を与える声かけが大切です。 また、「矯正をしている子がほかにもたくさんいるよ」「先生たちがサポートしてくれるから安心だよ」と、仲間意識や安心感を育む言葉をかけることも、前向きな気持ちを育てるポイントになります。楽しみながら続けられる診療体制
子どもが矯正を前向きに受け入れられるよう、治療そのものに楽しさを取り入れることも効果的です。 たとえば、治療ごとに“がんばりシール”を貼ったり、使用状況を記録する「チャレンジカード」を使ったりすることで、装置の装着や歯磨きの習慣を「ゲーム感覚」で続けられるようになります。 また、クリニック側でも、イラストや模型を使ったわかりやすい説明を行い、子ども自身が「自分の治療内容」を理解できるようサポートすることが重要です。 「なんとなく治療している」ではなく、「自分の歯を整えるチャレンジをしている」という意識が芽生えることで、治療への前向きさは格段に変わってきます。家族とのコミュニケーションがやる気を支える
矯正治療の成功には、家族の支えが不可欠です。 特に装置が取り外し式の場合、装着時間の管理やケアの習慣づけは、お子さま一人では難しい場面もあります。 「今日は何時間つけられた?」「もうすぐ交換日だね」といった日常的な会話の中で、自然と治療への関心を持たせていくことが大切です。 小さな達成を一緒に喜び、失敗しても叱らずに励ます——その積み重ねが、お子さまの「がんばる気持ち」を引き出してくれます。矯正を通じて得られる“自己肯定感”
矯正治療の最大の価値は、見た目の変化だけではありません。 「自分のために頑張った」「きれいな歯並びになった」という実感は、お子さまの自己肯定感や自信に大きく影響します。 この成功体験は、勉強やスポーツ、日常のさまざまな場面でも前向きに取り組む姿勢を育ててくれます。 矯正治療は、「歯を治すこと」以上に、お子さまの“成長”を支える機会にもなるのです。治療への信頼を育むために
子どもにとって安心して治療に向き合うためには、治療を受けるクリニックとの信頼関係も欠かせません。 歯科医院全体が子どもにとって「また行きたい」「ここなら安心」と感じられる場所であることが、治療の継続性にもつながります。 そのためには、丁寧な対応・痛みへの配慮・楽しい空間づくりなど、医院側の環境整備も大切な要素の一つです。 矯正治療は、お子さまと保護者、そして医療スタッフが“三位一体”で取り組むもの。 子どもが安心して治療に向き合える環境を整えることで、スムーズかつ効果的な治療を実現することができます。8. 成長にあわせて必要になるⅡ期治療とは?

Ⅰ期治療とⅡ期治療の違い
子どもの矯正治療には、大きく分けて「Ⅰ期治療」と「Ⅱ期治療」の2段階があります。 Ⅰ期治療は5〜10歳頃の成長期に行われる「成長誘導型」の矯正で、顎のバランスを整えたり、歯が正しく並ぶスペースを確保することが目的です。 これに対してⅡ期治療は、すべての永久歯が生え揃った後に行う「本格的な歯列矯正」のステージです。 あくまでⅠ期治療で土台を整えたうえで、最終的に歯並びを仕上げる段階と考えると分かりやすいでしょう。永久歯列が完成したあとの“仕上げ矯正”
Ⅱ期治療は、おおよそ中学生以降(12〜15歳ごろ)に開始するケースが一般的です。 この時期は、すでに顎の骨の成長がある程度落ち着いており、歯を動かして理想的な位置に整えることが主な目的となります。 使用する装置には、ワイヤーを使った「ブラケット矯正」や、透明で目立ちにくい「マウスピース矯正(インビザラインティーンなど)」などがあり、症例やライフスタイルに合わせて選択されます。できるだけ短期間で終わらせる工夫
Ⅰ期治療で顎のバランスや歯列の土台を整えておくことで、Ⅱ期治療の期間を短縮できるケースは多くあります。 たとえば、スペース不足を早期に解消しておけば、Ⅱ期での抜歯や大がかりな治療を回避できる可能性も高まります。 また、あらかじめ生活習慣や舌のクセを改善しておくことで、歯の後戻りを防ぐ効果も期待できます。 Ⅱ期治療の成功のカギは、「いかにⅠ期治療で良い準備ができているか」に大きく左右されるのです。Ⅱ期治療における装置の選択肢
本格矯正では、症例に応じてさまざまな装置を使用します。 代表的なものとしては以下の通りです。- ・ブラケット矯正(メタル・セラミック)
- ・マウスピース型矯正装置(インビザラインティーンなど)
- ・舌側矯正(裏側に装着する目立たない装置)
「非抜歯」で進められるかどうかの判断
Ⅱ期治療で多くの方が気にされるのが「歯を抜かないといけないのか?」という点です。 Ⅰ期治療でスペースを十分に確保できていれば、Ⅱ期でも非抜歯で矯正できる可能性は高まります。 一方、顎の幅と歯の大きさに明らかなアンバランスがある場合は、抜歯が必要になることもありますが、その判断は専門医の精密な検査によって慎重に行われます。 当院でも、可能な限り抜歯を避け、身体への負担を最小限にする治療方針を重視しています。本人の理解と協力が成功の鍵
Ⅱ期治療は、子どもから“思春期の若者”へと成長する時期に行われます。 そのため、本人の理解とモチベーションが治療成功の大きなカギになります。 「どうして矯正が必要なのか」「どうすれば早く終わるか」などをきちんと共有し、治療への前向きな姿勢を育てることが大切です。 当院では、治療内容をわかりやすく説明し、お子さまが自ら取り組む意識を持てるようサポートしています。Ⅱ期治療は“未来の健康”への投資
Ⅱ期治療は単なる見た目の改善だけでなく、「噛む・話す・笑う」といった日常生活の質を向上させ、将来的な虫歯や歯周病、顎関節症などの予防にもつながります。 つまりこれは、美しさと機能性の両立を目指す、“未来への健康投資”なのです。 Ⅰ期での準備が整っていれば、Ⅱ期治療はよりスムーズかつ軽度に済ませられることが多いため、成長段階に応じた治療のステップアップはとても重要です。9. 矯正治療中の虫歯予防とケアのポイント

装置があるからこそ必要な“仕組み化された歯みがき”
矯正治療中の最大の課題のひとつが「虫歯リスクの増加」です。 装置を装着していると、歯と歯ぐきの間にプラーク(歯垢)が溜まりやすくなり、清掃性が大きく低下します。特にワイヤー矯正の場合、ブラケット周囲の細かい部分に歯ブラシが届きにくいため、どうしても磨き残しが増えてしまいます。 マウスピース矯正の場合も、装着したまま飲食をしてしまう、磨かずに再装着するといった使い方が習慣化すると、口内に糖分が滞留し虫歯菌の活動が活発化します。 こうした背景から、矯正中は「毎日の歯みがきを仕組み化」することが非常に大切です。 朝起きたらすぐ、マウスピースを外したら必ず歯みがき、夜寝る前には仕上げ磨きと、ルーティンを決めることで自然とケアの質が高まります。歯科衛生士によるプロのケアとの連携
家庭でのセルフケアに加えて、歯科医院でのプロフェッショナルケアを定期的に受けることが、矯正中の虫歯予防において非常に重要です。 歯科衛生士によるクリーニングでは、磨き残しのチェックはもちろん、フッ素塗布や歯ぐきの状態の確認、装置まわりのプラーク除去などを徹底的に行います。 特にお子さまの場合、「しっかり磨いているつもり」でも、装置の隙間や歯の裏側などにプラークが溜まっていることは少なくありません。 第三者の視点でフィードバックを受けることで、親御さんもお子さまも磨き方の改善ポイントに気づくことができます。親子でできる習慣づくり
矯正中の歯みがきを成功させるためには、親御さんのサポートが欠かせません。 特に小学校低学年までは、自分だけで装置のまわりを丁寧に磨くことは難しいため、夜の仕上げ磨きを保護者が行うのが理想です。 「ここが上手に磨けていたね」「今日はピカピカだね」と声をかけながら褒めてあげることで、歯みがきが前向きな習慣になります。 また、「がんばり表」や「カレンダーにシールを貼る」など、目に見える工夫も効果的です。 毎日の努力を“見える化”することで、歯みがきに対するモチベーションが自然と高まります。矯正と虫歯予防は“セットで考える”べき理由
「矯正治療をしている=歯に対して関心が高い」からといって、虫歯にならないわけではありません。むしろ、装置があることで虫歯リスクは高くなります。 そのため、矯正を始めた時点で「虫歯予防も含めたトータルケア」を意識することが重要です。 フッ素入り歯みがき粉の使用や、デンタルフロス、タフトブラシといった補助清掃具の活用もおすすめです。 マウスピース矯正の場合は、装着時間を守ることはもちろん、毎回の装着前に口の中とマウスピースを清潔に保つことも忘れてはいけません。大人になっても続く“予防の意識”を育てるチャンス
矯正治療中に身につけた歯みがき習慣や予防意識は、将来にわたってお口の健康を守る財産になります。 「装置があるから」「矯正中だから」丁寧に磨くのではなく、「健康な歯を守るために」日々のケアを積み重ねる。 この意識を育てることは、成人後の虫歯や歯周病の予防においても非常に効果的です。 矯正中だからこそ、お子さまの歯に対する意識を高める“教育のチャンス”とも言えるのです。 正しいケアの習慣が身につけば、装置が外れた後も美しい歯並びと健康な口腔環境を長く維持できるでしょう。10.「治療するか迷っている」その気持ちこそ、相談のタイミング

相談=治療開始ではありません
「うちの子、もしかして受け口かも…」 そう思っても、「いつ相談すればいいのか分からない」「まだ早いかもしれない」と迷ってしまう保護者の方は多くいらっしゃいます。 ですが、矯正の相談は“治療の開始を決める場”ではなく、“現在の状態を知るためのステップ”です。 相談したからといって、必ず治療を始めなければならないというわけではありません。 歯科医師は、今のお子さまの噛み合わせや骨格、生活習慣を丁寧に確認したうえで、「現時点で必要な治療はあるのか」「それはいつ頃から始めるべきか」といった“客観的な判断”をしてくれます。 そのため、「迷っている今こそ」が、最も自然で適切な相談のタイミングなのです。専門医と一緒に考える“今できる最善”とは
受け口の治療には、タイミングが非常に重要です。 特に5歳〜8歳の混合歯列期は、骨格の成長にアプローチしやすい貴重な時期。このチャンスを逃すと、将来的には外科的な処置が必要になる可能性もあります。 とはいえ、すべての受け口が「すぐに治療が必要」というわけではありません。 中には経過観察で十分なケースや、生活習慣の改善だけで済む場合もあります。 大切なのは、自己判断ではなく、専門家の目で“適切なタイミング”を見極めることです。 歯科医院では、問診や写真撮影、咬合状態のチェック、必要に応じて模型分析などを通して、総合的に判断を行います。 治療の必要がない場合には、「このまま経過を見ましょう」「半年ごとにチェックを」といった提案がされることも珍しくありません。未来の後悔をなくすために、今一歩踏み出す大切さ
受け口の治療において、最も避けたいのが「もっと早く相談しておけばよかった…」という後悔です。 成長期の子どもたちは、数ヶ月の間にも骨格や噛み合わせが大きく変化します。 その中で、受け口が進行してしまうと、治療の選択肢が狭まってしまうこともあります。 逆に言えば、早期に相談することで得られるメリットは多くあります。 ・治療の必要性が明確になる ・最適な開始時期を見極められる ・必要以上の治療や負担を避けられる ・お子さまが前向きに矯正に取り組みやすくなる こうした好循環を生み出すきっかけになるのが、初回相談です。 保護者の「なんとなく気になる」という直感は、多くの場合で重要なサインです。 お子さまはまだ、自分で異常を訴えることができないからこそ、大人の気づきが将来を左右します。「やさしい矯正」は、まず“安心できる対話”から
私たちは、無理な治療や過度な介入を前提とした診療は行いません。 お子さまと保護者の気持ちに寄り添い、「安心して相談できる環境づくり」を第一に考えています。 初診カウンセリングでは、お悩みやご希望をじっくり伺い、専門用語はできるだけ使わず、模型や画像を使ってわかりやすくご説明します。 お子さまが安心して前向きに取り組めるよう、丁寧な対話を心がけています。 矯正治療は「削らずに整える」ことができる時代です。 マウスピース型矯正装置や取り外し式の機能的装置など、お子さまの成長を活かした“やさしい治療”が可能になっています。 「迷っている今」が、もっとも適切なタイミングかもしれません。 受け口かな?と思ったら、ぜひ一度、気軽にご相談ください。 お子さまの将来のために、最善の選択を一緒に考えましょう。監修:松本デンタルオフィスforキッズ
所在地:東京都東大和市向原4丁目1−2
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィスforキッズ
ドクター 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
2025年 医療法人社団桜風会松本デンタルオフィスforキッズ 開院予定
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより